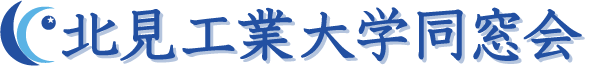母校だより 2014(平成26年度)
- 会誌発行に寄せて 学長(名誉会長) 髙橋 信夫
- 会誌の発行に寄せ 会長 谷 浩二
- 定年退職を迎えるに当たって
- 退職のごあいさつ 電気電子工学科 谷藤 忠敏
- 自分の立つ位置、目指した道 バイオ環境化学科 鈴木 勉
- いまだ果たされぬ課題探究 共通講座(人間科学) 照井 日出喜
会誌発行に寄せて
北見工業大学学長(同窓会名誉会長) 髙橋信夫
同窓会会員の皆様におかれましては、益々御清栄のこととお慶び申し上げます。
本学は、平成22年に創立50周年の節目を迎え、卒業生の数も14,000名を超え、着実に発展を遂げております。卒業生の皆様も、日本全国で力強くご活躍されている状況で、大変喜ばしいことと思っております。まず、北見工業大学の近況を報告させていただきたいと思います。
この3月に、鮎田学長が退職されました。先生には、45年の長きにわたり、教育・研究・社会貢献、そして本学の運営にご尽力いただきました。その他に、5人の先生方が退職されました。田牧純一先生、庄子仁先生、高橋修平先生、後藤隆司先生、そして青山政和先生です。先生方にも、激動の大学時代にあらゆる場面において、北見工業大学のために多大なご貢献をいただきました。ここに改めて感謝申し上げます。
さて、私は、3月までの35年間、教員として勤めさせていただくとともに、最後の6年間は、理事・副学長(総務担当)として勤めさせていただきました。その間、同窓会の皆様には、様々な局面においてお世話になってまいりました。大変、有難うございました。この4月から、鮎田耕一学長の後任として、学長職を勤めさせていただくことになりました。そして、新しい執行部体制となり、吉田孝理事、田村淳二理事、柴野純一副学長、そして野矢厚副学長の先生方に、これまで以上に大学運営にご協力いただくことになりました。私同様、新執行部の先生方にも、ご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
施設面におきましては、第3総合研究棟(5階建て、1,290m2)が竣工しました。教育・研究用のスペースが拡充され、大学として推進するプロジェクト型の教育プログラム及び研究プログラムの場所の確保が容易となりました。本学の特色ある教育・研究の場として活用したいと思っております。
次に、女子学生専用の学寮を設置しました。名称は公募により、「北桜寮」と決定しました。3階建、24室で、なかなか素晴らしい寮です。昔に比べて女子学生の数も増加し、平成26年入学者についてみますと、総数453人のうち63人が女子学生です。今後も、その割合は増加することが予想されます。明るい元気な女子学生がたくさん入学し、そして、これまで以上に社会において大きく活躍してくれることを期待しております。
さて、皆様もご存知のように、「国立大学」が法人化されて10年が経過しました。その間、高等教育を取り巻く環境は激変しています。大学運営経費として重要な、国からの「運営費交付金」は毎年1%減少しております。さらに、少子高齢化の進展もあり、本学も含まれる「地方国立大学」を取り巻く環境は、益々厳しい状況となっております。
まず、入学志願者数の点から見ますと、多くの地方の私立大学において「定員割れ」が起こる中、本学では、現時点では「定員割れ」の危機的状況には至っておりません。日本全国から多くの志願者を集めています。しかし、今後、さらに少子化が進み、「2018年」の厳しい状況を乗り切るためには、さらにしっかりと志願者確保に向けて取り組む必要があります。
また、大学運営は、平成24年、当時の民主党政権は、「大学改革実行プラン」を発表しました。その後、政権は自民党に代わりましたが、高等教育の施策についてはほとんど継続され、昨年は「ミッションの再定義」が実施されました。本学では、「広い視野を備えた科学技術者の養成」、「特色ある研究の推進」、そして「地域貢献・社会貢献の充実・発展」を今まで以上に進めることが確認されました。さらに、昨年の11月には、「国立大学改革プラン」が発表されました。このプランでは、国立大学に対し、「さらに大胆な改革の実行」を求め、平成26・27年度は「改革加速期間」として位置づけています。ミッションの再定義に沿っての本学の「機能強化」につながる「改革」を進める必要があります。
このような状況下、同窓生の皆様の中には、「北見工大は大丈夫か?」と心配される方々も多いと思います。地元の北見支部の皆様からも、激励のお言葉をいただいておりますし、複数の先輩が訪ねてくださり、「同窓生としてできる限りの協力は惜しまない、北見工大の名前を消すようなことはあってはならない」と叱咤激励されたところでもあります。本学では、学生・教職員全員が一丸となって、より魅力ある北見工業大学に発展させるべく、来年には、「明るい」報告をさせていただけるよう、最大限の努力を払ってまいります。その際、私どもにとりまして、日本全国でご活躍の同窓生の存在は、大変心強いものであります。
最後になりますが、同窓生の皆様の益々のご健勝とご発展をお祈り申し上げますとともに、本学に対しまして、これまで以上のご指導・ご支援をお願い申し上げます。
会誌の発行に寄せ
同窓会会長(昭和53年機械工学科卒業) 谷 浩二
同窓会会員の皆様方には、益々ご健勝でご活躍のことと心からお慶び申し上げます。
さて、日本の経済を見ますと、アベノミックス効果により景気回復が見られる業種、企業が増え、今後の日本経済回復への期待感が高まってきています。早く地方経済にも景気回復が実感される大きな波となって日本全国に広がってほしいものです。
また、産業界を見ますと近年のグローバル化により、企業の海外進出がますます進み、国内産業の空洞化、技術の空洞化に懸念が示されるようになってきています。今日の世界的競争力優位を後押ししてきたものの一つが、伝統的なものづくりの上に立脚した高い技術力です。このものづくりを国内に残し、発展させていくことが、国際競争力を維持していくのに必要なことではないでしょうか。
一方、日本国内を見ますと、地球規模での気候変動に伴う、局所豪雨による災害、火山爆発による災害など、現在の予知科学をもってしても防げない、大きな自然災害による甚大な被害も頻発しています。このような過去の災害をデータベース化して、予知科学の発展により、災害による甚大な被害を未然防止できる日本を創っていきたいものです。
このような伝統的なものづくり、自然災害を予知する科学が、明るい日本の未来を創っていくものと思います。つまり、日本の明るい未来、技術立国日本を背負って立つのが、北見工業大学の同窓生の皆様だと思っています。
同窓会の目的は、「会員相互の親睦を厚くし、北見工業大学並びに会員の隆盛を図ることを目的とする。」と、また目的を達成するため、「会誌の発行。大学活性化支援。講演会その他事項。」の事業を行うと会則に定めています。この目的を達成するため、従来から行っている会誌の発行、大学活性化支援に加え、その他事項として卒業生への記念品贈呈の検討を進めているところです。さらにホームページの充実化を行い、会員相互の交流促進や、支部活動支援等広く同窓生に情報発信を行っていく予定です。
同窓会支部活動を見てみますと、各支部積極的に色々な活動を展開中であります。これも各地の支部役員の方々、支部活動に積極的に参加される方々のおかげと感謝しております。
同窓会には、毎年約380名の卒業生が、新入会員として同窓会に入ってきていますが、一部の新入会員を除き、各地方の支部活動に必ずしも積極的に参加していただけない状況が続いています。これからの同窓会を末永く維持し、発展させていくには、若い同窓生の積極的な参加なくしては成り立たないことと思います。
これからは若い同窓生が積極的に支部活動に参加し、支部活動の運営に携わっていただけるように、若い同窓生が支部活動に積極的に参加する支部活動の在り方、若い同窓生にとって魅力ある同窓会活動とは、との問いかけを行い、支部活動の活性化、同窓会活動の活性化を図っていきたいと思います。
若い同窓生が支部活動に、支部運営に加わることにより、マンネリ化した支部活動も活性化していくことと思います。支部活動が活性化し、同窓会活動が活性化することにより、同窓生の連携の取れた力強い同窓会となります。同窓生皆様の知恵と行動力を結集して、北見工業大学の最大の応援団として大学とともに同窓会も大きく成長していきたいと思います。
最後に同窓生皆様のご健勝とご活躍をご祈念申し上げます。
〈定年退職を迎えるに当たって〉退職のごあいさつ
電気電子工学科 谷藤 忠敏
1998年10月1日に本学に職を与えられ、16年半に亘り教育と研究に携わることが出来たのは、偏に皆様のご指導の賜物であると感謝致しております。24年半の会社務めを含めると半世紀近い41年の歳月を一貫して科学技術に直接携わる仕事に就けたことに大変満足しています。退職後は傍から科学技術の発展を眺めつつ、趣味に費やす時間を増やして行こうと考えています。
本学で全く自由に研究させて頂いた時間は、あらためて自分自身のキャリアパスをリフレッシュする貴重な場を与えてくれました。通常会社勤務後大学教員に転身した多くの先生は、それまでの分野の延長上で研究を行っています。私は会社で光ファイバの伝送特性解析と計測、光ケーブルの高密度化と接続技術等の技術開発を行ってきました。本学赴任時は、光ファイバの研究で培った光伝搬解析と光計測技術を生かせる光生体工学関係のテーマに転換しました。赴任当時は21世紀直前で、バラ色の次世紀論が盛んに議論されていました。とりわけ私は『21世紀は生物の世紀である』という説に取り憑かれ、前述のテーマに転換しました。着任後数年間は論文発表が途絶え、苦しい時期が有りましたが、全く自由に研究させて頂いた結果、それなりの研究成果が得られ、僅かながら科学技術の発展に貢献出来たと自己満足しています。今になって世の中を窺がうに、2014年8月末にシカゴで開催された米国電気電子学会(IEEE)の医療工学関係の国際会議(EMBC’2014)でkeynote lectures 10件程度のうち少なくとも2件は細胞培養に関する講演だったのが特に印象的でした。
科学技術は目覚ましい勢いで進んでいると言われています。機械学習により今後十数年の間に人間より賢いコンピュータが実現される、再生臓器により物理的な寿命が160年と言われている人間が好きなだけ生ることが出来る、等々・・。約40年前大学を卒業した時と現在では街の風景や人々の生活にそれ程大きな変化が有るとは思えません。40年前も新幹線は有った、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、クルマも有った。ただ、その間computer & communicationが誰の手にも行き渡り世の中を国内分業から国際分業に変えてしまった、つまり世の中の仕組みが一番大きく変わったのかな、と考えています。
今後の科学技術の発展と世のしくみの変化を想像すると、大変楽しみである(バラ色)と同時に底知れぬ(?)こわさも感じます。今後の皆様のご活躍とご多幸を祈念して退職のご挨拶とさせて頂きます。
有難う、応用電気研究室!(提供:写真工房ピクセル・グラフィックス)
〈定年退職を迎えるに当たって〉自分の立つ位置、目指した道
バイオ環境化学科 鈴木 勉
来年3月末の定年退職まで残り半年を切った。丸35年の本学勤務であり、幾多の出来事がふつふつと心に甦る。今となっては事の是非や成否にかかわらず、それぞれが人生に豊かな彩りを添えてくれた貴重な経験、体験であり、これからも折に触れて懐かしく思い起こすに違いない。絶好の機会である、順を追って整理し、心の動きを辿ってみる。
昭和54(1979)年4月1日環境工学科講師として着任した。配属先の環境制御工学研究室では、本間恒行助教授(後教授、故人)と山田哲夫助手(後准教授、2008年3月退職)が石炭の触媒ガス化を手掛けていた。この研究は既に世界中が取り組み、レベルは高かった。セルロース研究室(北大・工・応用化学科)出身の私はズブの素人に近く、直ちに山田先生から実験研究の手ほどきを受けた。参考書、論文等を読み漁り、基礎知識を蓄えていったが、新しい方向は見えなかった。着任日前夜大雪の国鉄北見駅に妻と降り立ち、「ここに骨を埋める」と決意した。不本意な状況を打開すべく、バイオマス(木材)ガス化への転向を申し出て了解をもらったのは着任3年後である。木材パルプ化で学位(工博)を取得し、それなりの自信はあったが、この材料は新規性、先端性を重視する工学部向きではない。また、木材の流体燃料化は石炭優先の日本では異端であり、当初の評価は低かった。しかし、木材学会誌投稿論文がきっかけで京大・白石信夫教授の面識を得たことが迷いを払拭させた。この木材研究の大家が語る先駆的研究の冷遇さは、まだ実績の乏しい30代の私には大きな励ましとなった。10年経った1989年4月家族同伴で渡米し、NY州立大学シラキュース校のポスドクとして1年4ケ月勤務した。研究中断のマイナスより、分野が異なる日本人研究者と交流したことのプラスははるかに大きかった。分子ふるい膜が専門の山口大・喜多助教授(現教授)とは今も共同研究が続き、シラキュースの縁で学会仲間が増えた。帰国後再開した木炭触媒ガスの評価は次第に上がってきた。1993年4月の学科再編で化学システム工学科所属となり、研究室名を現在の「炭素変換工学」と変更した。修士学生が増え、研究テーマを燃料ガス以外の用途開発へと広げた。40代前半は勢いがあり、学生達に実験を頼み、私は論文書きに励んだ。Fuel投稿論文は、東北大・富田彰教授に見て頂いた。丁寧な添削を受けたこと以上に感謝しているのは「今の仕事を一般のサイエンスレベルに引き上げなさい」というアドバイスであった。1996年6月教授に昇任し、省庁の技術評価委員や学会役員等の学外仕事が増えた。議論の仕方、民間企業人との付き合い方等を学びながら、社会人としての成長を自覚、実感する日々であった。
21世紀に入り、50歳となった。2001年2月の日本木材学会賞受賞は、恩師(林治助北大名誉教授、故人)のお蔭である。最初はお断りしたが、応募を催促された。その後科研費申請が順調に採択されたのは、このことを見越した忝いご配慮である。今は亡き高橋行雄君(准教授、2006年2月没)が受賞を喜んでくれた。学生時代の友人を失った心の空洞は修復が効かない。新材料開発へとシフトし始めた頃であり、シラキュース仲間の三重大・舩岡教授に委託された「リグニンからの電磁波シールド材製造」を中国人留学生、王君の学位取得(2004年3月)のテーマとした。団塊世代の私には彼にポストを世話できなかった悔いが大きく、以後博士院生は受け入れなかった。妻は私の出身研究室の1年後輩で、この頃民間との共同研究を手伝ってくれた。以前から本業研究について議論し、それが知的興味を刺激した。本学法人化の翌(2005)年4月、妻は博士課程に入学し、3年後現在の木炭機能化研究の基礎となる「触媒炭化によるウッドリファイナリ」で博士号を取得した。日本材料学会木質部門学術賞も受賞した57歳の快挙である。2009年還暦を迎え、着地点を意識し始めた。前年バイオ環境化学科と改称されたが、研究展開が変わるはずもなく、科研費Bで他大学の仲間と共同研究を実施した。全国区とはなったが、これ以上の大型予算獲得は望まなかった。妻は非常勤技術補佐員という立場で木材由来結晶性メソ孔炭素(CMC)の難解な微細構造解明とEDLC電極炭素の開発に向かっていた。高い集中力を研究組織のマネージメントに向けるのは、勿体なさ過ぎる。私は科研費C研究の水蒸気ガス化による高効率水素製造で特許出願し、締め括ることとした。我々が研究室の学生諸君を鼓舞しながら放った矢の数は多くはなかったが、的の中心を射抜いている。特異な結晶形態を有するCMCは、今後他大学が実施する大型プロジェクト研究に利用される。異分野の進展に寄与することで、自分が目指した道は正しかったと納得している。
本学の看板を背負って活動し、多くの友人=財産を得たことは最大の慶びである。本学科教員諸氏特に岡崎文保准教授には長年に渡りご援助、ご協力頂いた。技術職員の橋本晴美氏には最後までお手伝い頂いた。衷心よりお礼を申し上げる。事務系職員の方々には色々とご迷惑をお掛けしたが、どうかご容赦願いたい。皆様のご健勝をお祈りしてご挨拶とさせて頂く。
〈定年退職を迎えるに当たって〉いまだ果たされぬ課題探究
共通講座(人間科学) 照井 日出喜
北見での年月を顧みれば、芸術社会学を専攻する者としては、みずからの非力のみを自覚せざるを得ない、というのが実感です。
理論的な領域においては、かつてみずからの問題設定としてそれなりに構想したものには、とうてい、はるかに及びもつかぬ状態のままで終わっています。ともあれ、わたし自身がこれまでに収集した蔵書を、それなりに読破するためには、おそらくは、もう一度、人生をやり直したとしても、なお絶対的に時間が足りぬであろうと思われるほどであり、読まねばならぬものに四方八方を取り囲まれ、つねに、それらからの暗黙の叱責の視線を感じながらも、見て見ぬふりをして避けて通っていたわが身を、悔悟の念とともに思い起こさざるを得ません。じっさい、美学の基本的な古典的文献、ヘーゲルやカントといったドイツ観念論哲学、何人かのドイツの作家・詩人たちの諸作品をシステマティックに読み進めるという作業も、断片的ないしは散発的にしか行うことはできず、膨大なドイツ語文献は、文字通り「死蔵」されているのみの惨状を呈しています。
フィールドワークとして設定した、現代ドイツの演劇状況の調査も、ある程度の時間をかけ、さまざまな都市の劇場を回ったとはいえ、成果としては、まだきわめて中途半端なものにとどまっていると判断せざるを得ません(もちろん、さまざまな戯曲のさまざまな演出が、いずれも強烈な個性を携えて、まさしく綺羅星のごとくに出現し、観る者の心をとらえ続けるドイツの劇場群の軌跡を追うことも、本質的に終わりのないものであり、むしろ、終わりがあってはならぬものであることは事実ですが)。この十数年にわたるフィールドワークとしての演劇研究は、その多くがベルリンを本拠地としておりましたが、さまざまな劇場の役者や文芸部員、演出家といった人びととの遭遇は、わたしにとってはきわめて貴重な経験であり、ドイツの文化状況の全体を認識するうえでも、それは大きな役割を演じておりました。個々の舞台の成果もさることながら、「劇場」という存在が「都市機能」の一つであり、芸術文化が現代において生き延びていくうえで、それがいかに重要な属性をなすものであるかということを、そしてまた、そういう性格を持つ存在としては、「劇場」がいかに日本には存在していないかということを、ベルリンやウィーンで、しばしば痛感させられることになりました。ともあれ、北見での日々は、来るべきフィールドワークの準備のための諸資料を収集し、読むことと、その後の作業として、諸資料をさらに読み、原稿を仕上げることに費やされていました。しかしながら、舞台演出の百花繚乱の多彩さと、劇場の果たすべき社会的機能の諸相とを包括的にとらえていく、という問題の設定は、まだたんなる仮説としてあるのみであることも事実です。
美学・芸術学を研究対象として専攻する場合には、なんらかのジャンルにおいて、ある程度の実践的な知識ないしは技法の学習を必要とする、というのが、わたし自身の確信的願望でした。多少なりとも「創造」に関わらぬ者には、創造する者たち(芸術家)の心情もしくは感性的意志を想像することは不可能であるからです。とはいえ、たとえば写真に関わる分野においても、所詮はたんなるアマチュアの限界を超え出ることはありませんでした。20世紀以降におけるカメラの機構的な変遷や、写真が持つ社会的な性格の変化の過程を理解しつつ、写真の個々のジャンルにおける多彩な撮影技法を、ある程度、消化するということは、一朝一夕で可能となるものではないということを、思い知らされることになりました。(ともあれ、じっさいの撮影やフィルム現像に際し、機材の調整や準備等について、本学のさまざまな学科のさまざまな方々に、きわめて多くのことを教えていただき、協力していただいたことに、深く感謝いたします。)
日本の近現代の演劇史との関連で、とりわけ日本映画の全盛期と言われる1950年代から60年代の初頭にかけて、演劇畑の役者たちが膨大な映画に出演していることを知ったことをきっかけに、日本の映画史についても、さまざまな監督たちの強烈な感性的主張に触れつつ、初歩的な事柄については、多少の知識を得ることができました。半世紀もしくはそれ以上も前の役者たちの、若々しく、凛々しく振る舞う姿を眼前にし、その彼らの圧倒的多数が、もはや現世に別れを告げているという悲しくも厳然たる事実にも思いを馳せながら、溝口健二、小津安二郎、小林正樹、といった、戦中・戦後の監督たちの創り出した「虚構」の世界に、あるいは、「事実を超える虚構」として、レンズの中へと取り込まれていった映像の世界に、社会や人間を観る彼らの眼の厳しさを感じ取っていました。ただ、この領域においても、歴史的あるいは全体的な流れを十全に把握するほどの蓄積があるわけではありません。
こうした意味においては、わたし自身の周囲に広がるありとあらゆる領域において、課題探究の旅は、いまだまったく五里霧中、たんなる途上にある、ということになります。それは、しかし、当然のこととして、これからなすべきことの方向をも示している、ということでもあります。
同窓生の活躍
○卒業生の協力で技術セミナーを開催
北見工業大学では社会貢献の一環として、本学出身技術士の協力のもと、社会人を対象とした技術セミナーを平成19年から開催しています。
同セミナーは(1)技術士の資格取得希望者を対象に講義や添削指導等を通じ資格取得を支援する「技術士養成支援講座」、(2)土木・建設関係技術士に最新技術動向や建設コンサルタントを取り巻く状況等について情報提供を行う「CPDプログラム認定講座」の2種類の内容で実施しています。
技術士養成支援講座は札幌会場と本学の2会場。CPDプログラム認定講座は本学を会場に開催しました。
今年の技術士養成支援講座は、札幌会場講師に福田朗裕氏(昭和55年土木工学科卒 福田アキヒロ技術士事務所)、林克恭氏(昭和59年土木工学科卒 (株)福田水文センター)、岩倉敦雄氏(昭和59年土木工学科卒 (株)構研エンジニアリング)、小杉勝則氏(平成2年土木工学科卒 (株)北未来技研)、佐藤之信氏(平成2年開発工学科卒 (株)豊水設計)、天内和幸氏(平成8年卒 (株)FAプロダクツ)、岩渕直氏(平成17年土木開発工学専攻修了 (株)構研エンジニアリング)。また、北見会場講師に橘邦彦氏(昭和51年開発工学科卒 ㈲パル設計事務所)、牧野勇治氏(昭和55年開発工学科卒 (株)中神土木設計事務所)、平成晴氏(平成11年土木開発工学専攻修了 網走市役所)、大澤公浩氏(平成10年土木開発工学科卒 遠軽町役場)の11人の技術士が講師となり開講しました。
本講座はきめ細かな講義や個人指導を無料で受けられることから、募集と同時に定員に達するほど大変好評な講座で、これまでも22人の方が晴れて試験に合格されています。
また、当講座から合格された方が、今度は講師としてその経験を活かし、次の受験生の支援を行うというのも特徴的なところです。本学出身の講師の方々は夜間や土曜日など、忙しい仕事の合間を縫って試験情報収集、資料作成や講義と献身的に活動されています。今年も受講生から多数の合格者が出ることが期待されます。
また、本学教員と技術士養成支援講座講師が講師を務める「CPDプログラム認定講座」も毎年本学を会場に開催し、オホーツク地域に限らず釧路や帯広からも参加者が集まります。受講機会の少ない地域のため、建設業等関係者からの強い要望があり継続して実施しています。
今年のCPDプログラム認定講座は、本学社会環境工学科伊藤陽司准教授、牧野勇治氏、林克恭氏、岩淵直氏の4人が講演しました。
本学卒業生が中心となり、継続して実施している事業です。同窓生のご協力に感謝申し上げます。
(研究協力課)

技術士養成支援講座開講式(札幌会場):髙橋学長挨拶

CPDプログラム認定講座の講義風景
今年度から、新たに「同窓生の活躍」をスタートさせました。今号では、札幌近郊、オホーツク管内で活躍中の卒業生のご協力をいただいて実施している北見工業大学主催の、「技術士養成講座」(平成19年度~)につきましてご紹介いたしました。同窓生同士のネットワークの強化・拡大につながるよう、同窓会誌ではみなさまのご活躍を紹介していきたいと考えております。
ぜひ、みなさまのご活躍について同窓会事務局までお寄せください。お待ちしております。
=学科だより=
機械工学科
卒業生の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと存じます。本年は、台風などの大雨による浸水・土砂災害や火山噴火など、自然災害が全国各地で数多く発生しています。このような災害の被害防止や復興などの問題に対峙するたび人間の無力さを実感いたしますが、その反面、科学技術による防災・減災、復興支援などの重要性も年々高まっているのではないでしょうか。一方、明るい話題としては、本年のノーベル物理学賞を青色発光ダイオードの発明に関わった日本人科学者3人が受賞いたしました。受賞に至るまでの研究・開発経緯を鑑みますと、まさに科学技術立国日本を象徴するような実用的イノベーションに結び付いた発明であると感じます。スポーツの分野では仁川アジア大会が開催され、多くのメダル獲得を実現しました。金メダル数、獲得メダル総数ともに中国、開催国である韓国に次ぎ第3位となり、東京オリンピック開催に向けて大いに弾みがつきました。スポーツエリートアカデミーによる若手選手の育成が成果を出した結果となり、スポーツ科学による選手育成支援が話題となりました。私たちの研究成果が、人々の豊かで安全な生活に役立つことを願っている次第です。
さて、機械工学科では平成元年4月に着任された田牧純一教授が本年3月に定年退職されました。先生は、マイクロナノ加工学研究室の教授として機械工学科の教育・研究に貢献されるとともに、本学の技術部長、副学長、理事を歴任され本学の発展に大きく寄与されました。また昨年度、生体メカトロニクス研究室の助教として着任した星野洋平先生が、10月に准教授に昇任しました。今後、振動制御技術を基に農業機械の自動化の分野などでの活躍に期待が寄せられております。平成26年度卒業生・修了生の就職状況については、昨年と同様に民間企業への就職決定率はほぼ100%となり、全国的に見ても大変良好な結果となりました。ご尽力いただいた就職担当の尾崎教授と松村准教授には感謝申し上げます。次年度は就職活動の開始時期が大幅に変更となりますが、引き続き高い就職内定率が確保されることを期待しております。今年のNHK大学ロボコンでも、羽二生教授の熱心なご指導により見事、本選出場を果たしましたが、惜しくも決勝トーナメントに進むことができませんでした。同窓会関東支部の皆様には、ご支援を賜りましたこと厚く御礼申し上げます。次年度以降の活躍に期待しております。
最後になりますが、卒業生皆様の益々のご活躍をご祈念申し上げます。
(学科長 鈴木聡一郎 記)
○材料力学研究室
卒業生の皆様、お元気ですか。平成26年度のスタッフは昨年に引き続き柴野、三浦先生と技術部大森さんの3名で、学生はM2:3名、M1:3名、4年生:6名です。4年生の進路とM2の就職も全員決まりました。4年生は1名が大学院進学です。研究テーマとしてはX線回折を利用した応力・ひずみ評価に関する研究が多くなりました。今年は約2年ぶりに SPring-8での実験を行います。実験課題が採択されたことは嬉しいのですが、また徹夜に近い実験が続くことを考えると少々気が重い年齢になりました。今年度中には2次元検出器を利用した応力評価の検討を開始します。超音波顕微鏡によるウロコの研究も再開しました。三浦先生はAEや超音波による研究のまとめや学生実験・講義に相変わらず大忙しです。大森さんも様々な学内業務で多忙ですがGo on Footは続けています。末筆ながら皆様のご健康とご活躍を祈念しております。
(柴野純一 記)
○計算力学研究室
今年度の計力研究室は大橋教授、長谷川技術員、特任研究員の安田さん、佐藤を含めスタッフ4名、後期課程2年リディアナさん、1年奧山君、前期課程6名、学部8名と20名の大所帯です。大橋先生は米国、英国、台湾・・・の海外出張で世界中を飛び回っており、今年も大変多忙です。安田さんと後期課程の二人も国際会議へデビューするなど、多くの国内外での学会発表を行っています。院生、学部生は金属材料や半導体素子をタイトルとした修論・卒論の研究に精力的に取り組んでいるところです。恒例の大雪山登山は台風の通過により断念、日にちを改めて雌阿寒岳に登り、オンネトーでキャンプを行いました。厚い雲に覆われて山頂からの壮大な景色は真っ白で何も見えませんでしたが、温泉と焼き肉、キャンプファイヤーを楽しんで来ました。
皆様の益々のご活躍をお祈りしています。また、皆様の近況を是非ともご連絡下さい。
(佐藤満弘 記)

雌阿寒岳山頂(標高1499m)にて 2014年9月14日
○設計工学研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。現在の設計工学研究室は博士前期課程1名、学部生3名で学部生は2月の卒業研究の発表に向けて研究を進め、院生は講義と研究両方に励んでいます。研究テーマは、人体にかかる荷重・鋳鉄の成長のシミュレーション・QVICを使った降雪のシミュレーションとなっており異なる分野の研究となっていますが、研究内容で困ったことがあればお互いに相談し、協力し合って日々研究を進めています。また、今年も大学祭ではQVICを使った出し物を他学科の研究室と合同で行い大盛況でした。この大盛況の流れを卒業研究の発表の時まで持っていけるように研究室一同、てんやわんやしながら努力していこうと思っております。
最後になりますが、もし今後機会がありましたら今の設計工学研究室をご覧いただければと思います。
(菅原幸夫 記)

研究室風景
○エネルギー・環境工学研究室
卒業生の皆様、お元気でご活躍のことと思います。研究室のスタッフは、佐々木教授、遠藤助教、学生は社会人ドクター1名(燃料電池)、M2・2名、4年生・6名、の計11名で構成されています。研究テーマは、地中熱ヒートポンプ冷暖房システムの家屋熱収支予測と採熱管熱干渉解析、網走湖内メタン輸送および大気拡散の解析とメタン収支解析および大気と永久凍土地帯の湖沼における融解過程解析等となっています。
卒業生の皆様、来北の際は、是非研究室にお立ち寄り下さい。
(遠藤登 記)
○伝熱システム研究室
今年度は、M2:増山、M1:伊藤、内田、嵯峨の各君と、4月に配属された4年生:5名の計9名の学生で構成され、相変わらずチームワーク良好な研究室です。進路について、増山君のほか4年生の太田・今野・篠原の3君は順調に企業から内定を頂き、また、齋藤・五月女の両君は前期課程に進学予定です。8月2日、恒例の「おもしろ科学実験」では、学生諸君らが例年通り未来の若い担い手(子供)達に熱血指導してくれました。9月27日には、増山君が日本機械学会北海道支部の講演会(室蘭)で立派な発表を行いました。私はと言えば、2年間の学科長任期を(やっと)終え、体調を整え普通の生活?にもどりつつあります。一方、中西さんは今年より技術部の室長となり、さらなる責務を担いつつ元気にされています。最後に、卒業生皆様の今後のご活躍・ご健勝をお祈り申し上げます。
(山田貴延 記)
○エンジンシステム研究室
皆さん、お元気でご活躍のことと思います。今年は大学院生2名と4年生7名が配属され狭い居室で研究に取り組んでいます。新たにコモンレール噴射方式に改造した小型を含め3台のディーゼルエンジンで、低温始動時の排気臭気、アルデヒド類の特性、噴霧の壁面付着、すす粒子の構造をレーザー解析により研究を進めており、内燃機関シンポ(つくば)で発表の予定です。林田先生は科学技術振興機構の(SPP)でオホーツク管内3校の高校生20名に熱エネルギに関する授業・実験を行いました。私は体力の衰えを感じつつ、教職員や学生とバドミントンを楽しみながら体力維持に努めています。恒例のママチャリ12時間耐久レースに参加し私も走行し楽しんできました。ご支援をいただきましたメカトロ・エンジン両研究室の卒業生の皆様には心から感謝いたします。卒業生の皆さん私もあとわずかで北見工大卒業となりますので、時間を作って顔を出してください。
(石谷博美 記)
○流体工学研究室
卒業生の皆様方におかれましては、元気にご活躍のことと存じます。今年度の流体工学研究室は博士後期が1名(社会人)、博士前期が5名、学部が7名です。研究は流れのスイッチング現象、渦構造、流力振動などの課題を継続しています。また開発中の空撮システムは大幅な進化を遂げています。
今年の話題は3Dプリンタとボートの導入です。3Dプリンタは年度初めに導入され、実験室のものづくり環境が大きく変わりました。大学院生と小畑技術員を中心にいろいろなところで活用しています。また昨年度の空撮システム回収における川渡りの経験からゴムボートが導入されました。ボートでは状況判断力とその対応力が養われるとして、羽二生教授が先頭となって学生達と湖や河川でゴムボートを活用しています。
卒業・修了予定の学生の進路もほぼ決まり、研究と生活の充実を努めています。北見・道東方面にお越しの際には、ぜひ研究室にお立ち寄り下さい。
(高井和紀 記)
○流体制御工学研究室
卒業生の皆様、如何お過ごしでしょうか。今年度は弓道部が2人、元剣道部が1名の個性豊かな4年生3人と私(宮越)で、「ノズル内の円柱後流による噴流の混合・拡散制御」「カーリングにおけるスウィーピング力測定ブラシの開発」を進めています。ものづくりセンターの堂田さん、山田さん、石澤さんに噴流風洞のダクトを製作して頂きました。ご協力に感謝するとともに、良いデータを出して行かなければと思っています。スウィーピング力の測定では、これまで苦労してきた信号の送受信が容易になりました。その一方で新たな課題も出てきましたが、実用化を目指して頑張っています。技術部の佐藤敏則さんと長谷川稔さんにはいつも多くのご支援を頂きながら研究を進めております。来北の際には当研究室にもお立ち寄り下さい。皆様のご健康とご活躍をお祈り致します。
(宮越勝美 記)
○計算流体力学研究室
研究室卒業生の皆様お元気ですか?2014年度は、4年生3人と私の計4人でコンパクトにやっています。少人数ながら、日本人の男子学生1名、女子学生1名、マレーシアからの男子留学生1名というバラエティーに富んだ構成となりました。3人には、固気粒子分散流とマイクロバブル分散流に関するテーマに取り組んでもらう予定です。今後の努力に期待したいと思います!卒業研究以外では、熱の計算の準備を進めています。研究にもますます熱が入ることと思います。11月には、2014年3月に修了した池田君の修士論文の内容をサンフランシスコで開催される米国物理学会流体力学部門年会で発表してきます。皆様のご多幸をお祈りしています&機会があったら是非研究室へ遊びに来てください。
(三戸陽一 記)
○応用流体工学研究室
今年度の学生は、4年生(4人)、M1(2人)、M2(1人)の合計7人です。院生が3人減り、ちょっと寂しくなりました。ここ数年連続参加している機械学会流体工学部門主催の「流れの夢コンテスト」では、昨年度も3位相当の賞をいただきました。今年も富山で開催される予定で、学生達や佐藤技術員は連続上位入賞を目差して一生懸命準備しています。研修打ち上げ(ゆうゆ温泉コテージ)、焼肉レイノルズ(大学祭)、紙飛行機(おもしろ科学実験)、夏のキャンプ(然別峡)、学会発表(釧路、仙台、富山、室蘭)など、例年通り盛りだくさんの行事をこなしています。キャンプでは、木々の間に張られたワイヤーを滑車で滑り、鳥の視線で森を観察するエアートリップを初体験しました。また3月の卒業旅行では、知床で流氷ウォークを初体験し、流氷といっしょにプカプカ浮いて楽しみました。相変わらず道東の自然を満喫しています。
(松村昌典 記)
○生産加工システム研究室
卒業生の皆様におかれましては、ご壮健にてご活躍のことと存じます。4月から「マイクロ・ナノ加工学研究室」を「生産加工システム研究室」に研究室名を変更し、次のテーマについて研究が行われています。「フラクタル図形の製造法、インターネットを用いた次世代生産システム、異なる材質で構成された部品の加工法、次世代工作機械、超精密表面トポグラフィモデリング、持続可能生産、製品開発、ツルーイング・ドレッシングなど」。今年度の当研究室は、大学院生5名、学部生7名、また8月で留学を終え帰国した留学生1名が、スタッフ3名の下で活動しています。研究室の近況としまして、ウラ准教授が国際会議Eco Design 2013(韓国)、院生2名が国際会議CAD’14(香港)、久保助教が国際会議ISAAT2014(ハワイ)に参加しました。留学生のAshrafulさんは今年3月に博士学位を修得し帰国しました。今年3月で定年退職された田牧名誉教授の退職記念祝賀会を5月に北見市内で開催しました。卒業生を含め参加者の皆様に感謝致します。田牧名誉教授は現在本学の特任教授として「スーパー連携大学院担当」でご活動を続けておられます。
(ウラシャリフ 記)
○光計測研究室
光計測室の構成員は1名のM2生と4名の卒研生で、以下に諸先輩によせた彼らの言葉を紹介します。M2の立花侑也君:「約半年後には就職ということで、不安もありますが、社会人としてのマナーや常識、仕事の基礎など、教えられたことをいち早く覚えるよう努力したいと思います」といっています。つぎに名簿順に卒研生は、明石靖生君:「大学生活やサークルで学んだ事を活かして、一人前の社会人になれるよう頑張っていきたいです」、川崎涼太君:「4年間北見工業大学で勉強して、知識を身につける以外にもたくさんのことを学ぶことができました。このことをこれからも大切にしていきたいです」、工藤岳君:「私は奇術部で部長を経験し、サークル連合でも役員を務めました。大学祭などを他のサークルと協力して作り上げたことは、大変なことばかりでしたが、私の大学生活を充実させました」、そして韓国からの留学生の申容周君:「日本での留学生活も、早4年。恵まれた北海道で生活できたことに幸運だと思っています。日本の文化など肌で直接味わえる環境で過ごすのも大人になれる良い経験だったと思っています」といっています。今後とも彼らをよろしく。
(尾崎義治 記)
○生体メカトロニクス研究室
卒業生の皆様、元気でご活躍のことと思います。今年の研究室のメンバー構成は、星野が准教授に昇任し、9月に博士後期課程を修了したゾイ君がポスドク研究員として加わってスタッフが3名となり、M2が3名、M1が3名、B4が7名です。研究面では、本邦初のスキーシミュレータを活用したスキー研究の成果が挙がり始めました。受動歩行、パワーアシスト膝継手、腰部負担軽減の研究でも興味深い結果が得られています。さらに、農業機械や除振台などの機械システムの振動解析・振動制御に関する研究も始まりました。恒例のママチャリ耐久レースでは、エンジンシステムとの混成チーム2つと教員チームが出場し、それぞれ総合11位、13位、50位と健闘しました。ご支援頂いた卒業生の皆様には心から感謝いたします。さらに今年度から道内ロボコン “ロボットトライアスロン”に参加し、初出場ながら完走を果たしました。皆様も是非、研究室に遊びに来てください。
(星野洋平 記)
○生産工学研究室
3月に、博士前期課程1名、4年生4名が無事に卒業しました。大学院への進学者いませんでしたので、現在の陣容は、学部4年生4名です。相変わらずこじんまりしており、和気あいあいでやっています。4年生3名の就職が内定しています。研究は相変わらずの摩擦圧接です。私は、あと1年 ちょっとでお役御免となりますので、昨年からの終活にさらに力を注いでいます。教員室、研究室、実験室のゴミも大分片付けました。研究室のコンパでは、めげずに「たこ焼きの最適加熱条件の設定実験」を続けています。景気の先行きは相変わらず不透明で、卒業生の皆様もまだまだご苦労が多いかと思います。ご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
(冨士明良 記)
○知的システム工学研究室
研究室の名前の由来は、遺伝的アルゴリズム(GA)、人工ニューラルネットワーク(ANN)、機械学習(ML)、人工生命(AL)、エージェント等の技術がスマートエンジニアリング(知的工学)と呼ばれ、これらの新技術を用いて工学的に色々な実問題へ取り組みたいとの思いから付けました。主な研究内容は、進化計算と機械学習による自律的な行動獲得、大規模問題によるハイパフォーマンスコンピューティング、物理法則に基づくアニメーティッドロボットの三本柱となっております。
研究室では、昨年同様に北海道支部や全国の学会で活発に研究成果を発表しています。また9月には、北海道情報大学古川研究室、北見工業大学鈴木研究室と知的システム工学研究室の3研究室(30数名)で1泊2日の夏旅行(当麻スポーツランド)が開催され、学生同士の交流が行われました。
卒業生の皆様、北見にお越しの際には是非知的システム工学研究室にお立ち寄り下さい。
(渡辺美知子 記)

2014年度研究室夏旅行(当麻スポーツランド)
社会環境工学科
卒業生の皆さんお元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。今年に入って、気象庁から豪雨に関する注意喚起情報が頻繁に発せられており、広島県の豪雨による大規模土砂災害では急激な都市開発の影に潜む身近な自然環境の危険性が浮き彫りになりました。また、御嶽山の水蒸気噴火など自然災害によって多くの尊い人命が失われております。本学科の卒業生が活躍されているフィールドはまさにこの中心にあり、日頃からこのような災害対策の最前線に居る方も多いのではないでしょうか。
社会環境工学科として平成20年にスタートして7年目を迎えます。卒業生をこれまでに、103人を輩出しております。さらに昨年度は大学院博士前期課程の土木開発工学専攻が名称変更した社会環境工学専攻からも初めての修了生14人を輩出しております。昨年度の就職状況は、政権交代に伴う景気浮揚策と国土強靱化政策などの影響で、建設業界の求人意欲の高揚と公務員採用枠の急増によって好調を維持しております。昨年度は求人のために来学された多くの卒業生とお話しすることが出来ましたが、それぞれの活躍分野で生きがいを感じて仕事の話をしている姿は技術者としての成長を強く感じました。反面、求人の要望に添うことが出来ない状況が続いることが残念です。
さて、昨年度末をもって定年退職を迎えた教職員と今年度より新に本学科に加わったフレッシュな教員については研究室便りにも触れられておりますので簡単にご紹介いたします。鮎田耕一先生は本学科の前進である土木工学科創設期から教育研究をリードされ、最後は学長として任期を満了されました。定年退職教員は、高橋修平教授、庄子仁教授、後藤隆司准教授の3人です。それぞれの分野の研究室からお話しがあります。また、昭和48年に開発工学科に赴任してから学生実験や卒業研究などで学生の信望が厚かった岡田抱儀技術員が退職致しました。今後は2012年に国会議員となった桜井衆議院議員の政策秘書として活躍されることになりました。今年度、新にコンクリート工学が専門の崔希燮(チェ・ヒソプ)助教(前職は東北大学)、地盤工学が専門の川尻峻三助教(前職は鉄道技術総合研究所)の2人の先生が加わっております。
カリキュラム改革の一環として昨年より開講されてきた「オホーツク総合演習」は今年前期に最初の発表会を行いました。この科目ではオホーツク地域に関連した道路や防災さらに地域振興などの課題をテーマに、網走開発建設部や北見市に協力頂き現場で起きている課題や取組を紹介してもらい、この題材から学生が問題を掘り起こしグループで正面から向き合い問題の解決策を提案する科目です。今年度は19グループがポスターで成果を発表しました。参加者からの指摘やアドバイスなど意見交換が行われ初年度として立派な成果を残しました。
昨年より学科ホームページを新しくし、ホームページ管理チームによって学科関連の最新情報の公開を進めるようにして参りました。いま学科でなにが起こっているかいち早く伝えることが出来るようになりますのでご期待下さい。
最後に卒業生の皆様のご健勝をご祈念申し上げます。また、お仕事などで北見にお越しの際には是非大学にお立ち寄りください。
(学科長 三上修一 記)
○河川防災システム研究室
平成26年度は、修士1年4名、学部4年4名、社会人博士課程3名の構成になっています。蚊やダニと悪戦苦闘する常呂川の浸食箇所の調査では、例年行っている測量に光波を用いることで飛躍的に作業効率が上がったため、ADCPによる流速観測も実施しました。また、札内川での擬似洪水放流の調査では監視カメラを利用した流況観測の試みも行い、現地観測も充実してきています。定例の夕方から始まるミーティングもほぼ毎月開催しております。北見においでの際には開催日をあわせることが可能ですので、ぜひ事前にご連絡をいただけると幸いです。
(渡邊康玄 記)
○水圏環境研究室
今年度は新4年生4名に加え、アルジェリアから国費留学生を1名、大学院前期課程に受け入れました。パナマからの留学生、およびJSPSの外国人特別研究員であるベトナムからの研究者との研究も順調に進んでおります。非常勤研究員の松本さんを中心とした知床での栄養循環に関する研究も順調に進んでおり、それも全てよい学生やスタッフにも恵まれた結果だと思います。学外との交流を通じた学生への教育も進めることが出来ております。今後とも、ご支援のほどよろしく申し上げます。
(中山恵介 記)

研究室歓迎会
○河川・水文学研究室
今年の研究室メンバーはM2-1名、M1-2名、学部生-4名の計7名です。今年の就職は順調で、春先にゼネコン・コンサルへ各1名、公務員は8月末までに国・北海道・市役所へ内定しました。
研究テーマはこれまで河川関係と水文学の両方を取り組んでいましたが、今年度は水文学の人気がなく、藻琴川の畑地からの浮遊土砂流出調査はメンバー全員で取り組んでいます。河川関係は釧路川の旧川復元河道以外に蛇行河川の調査や河床低下対策工の検証実験などに取り組んでいます。
現地調査は学生が技術者としての経験を積む最適な場であり、暑さや虫、茂みとの格闘は良い思い出になっています。研究室OBの皆様、機会があれば是非とも研究室にお立ち寄り下さい。なお、4月から教員室が3階へ移転しました。
(早川博 記)
○環境水理研究室
卒業生の皆様は元気でご活躍のことと思います。本年度の当研究室は私と修士1名、学部生3名の計5名体制で、ここ数年、解析を行っている北海道の気候変動特性変化の解析を進めています。お陰様で4年生3名は早々に就職も決まり、今は日々卒業研究に励んでいる毎日です。仕事柄か北海道のみならず日本各地で極端な猛暑や局所的豪雨が今年は多く連日のように自然災害の報道を目にするようになりました。皆様も思わぬ自然災害に巻き込まれぬよう益々ご活躍されますことを願っております。また、来北の節は是非とも当研究室にもお立ち寄りください。
(中尾隆志 記)
○水処理工学研究室
今年度も勉強熱心な学生が集まり、日々、教育・研究に奮闘しています。研究内容は引き続き、道東地方の汽水湖、湿原、森林域、瀬戸内地方の陸域~海域、豪州の砂浜~マングローブ帯、ペルーのアンデス山脈~海岸砂漠地帯等のフィールドを中心に、汽水域の水質や底質改善、湿原の生態系保全、浅場~都市港湾域の環境再生、濁水浄化、水生生物の保全、水資源の将来予測等の研究を行っています。研究面での進展を目指して、学生達は研究に取り組む上で分析装置の扱いや学術的なことを勉強しながら、互いに協力し合い刺激しあうことで日々成長しています。学生たちは身近な社会人である卒業生から学ぶことも多いので、機会があればぜひ気軽にお立ち寄りください。どうぞよろしくお願いいたします。
(駒井克昭 記)

冬期の河川水質調査
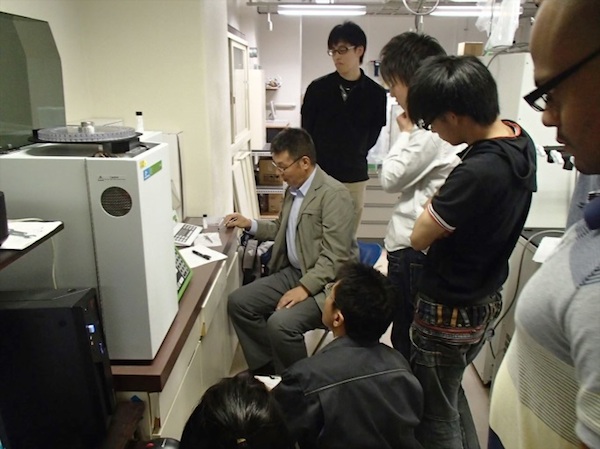
元素分析装置の講習会
○地盤工学研究室
卒業生の皆様、元気にお過ごしでしょうか。今年の研究室の学生メンバーは、小川君(M2)、大島君(M1)、清君(M1)と4年生4名です。4年生では2名が進学予定なので、来年度はここ数年では最も人数が多くなりそうです。地盤系研究室は、伊藤先生、川口先生、中村先生と山下の4研究室があり、毎週合同の凍裂ゼミを現在も続けています。地盤系には今年4月に川尻助教が着任し、来年度は新助教も着任予定です。山崎助教、平田技術員、平松技術員とあわせて地盤系は総勢9名の教職員となります。ハイドレート関係では、今年から紋別沖での海洋実習が始まり、バイカル湖、サハリン沖、網走沖(今年は十勝沖)と年に4回の海洋調査が定例化となりました。山下は久しぶりにバイカル湖調査に参加してきました。また、液状化に関する研究も継続的に行っています。三軸液状化試験装置(BE付)が久しぶりに稼働しています。
(山下聡 記)
○凍土・土質研究室
卒業生の皆様、お元気でしょうか?早いものでこちらに赴任して4年目となりました。現在、研究室にはM2が2名、M1が2名、4年生が4名おり、さらに社会人の大学院生2名も加わって、赴任した当初に比べると研究室にいる学生さんの数もすごく多くなりました。さらに、本年度4月からは地盤系の助教として川尻峻三先生も加わり、ありがたいことに多くの人が常に慌ただしく動いている、本当に活気あふれる研究室となりました。
卒業生の皆様、お近くにお越しの際は是非凍土・土質研究室にお立ち寄り頂き、近況などを聞かせてください。お待ちしています。
(川口貴之 記)
○寒地岩盤工学研究室
卒業生の皆様、お元気でしょうか?今年度の寒地岩盤工学研究室のメンバーは、教員が中村と平松技術員、4年生が小田原、金子、隅屋、宮川の合計6名です。少人数ではありますが、研究やコンパ等楽しく過ごしております。長年に渡って岩盤工学研究室を率いてこられた後藤先生は2014年3月末日に定年退職されました。後藤先生の岩盤工学研究室のように楽しい研究室となるよう、寒地岩盤工学研究室も盛り上げていきたいと考えています。卒業生の皆様、来北の際には、是非、研究室へ顔を出してください。
(中村大 記)
○地圏環境防災研究室
皆様、お変わりありませんか?今年の研究室には4年生4名が所属し、知床の地すべり活動性評価やカムイワッカ川での斜面変動解析、津別チミケップ湖岸の切土法面の安定性評価などに取り組んでいます。
今年は国内各地で大雨による土砂災害が相次ぎ、多くの方が犠牲となっています。極端になってきている降雨状況への警戒とともに、私たちの生活する土地の成り立ちとそこでこれまで何が起こってきたのかを確認することが、ハード、ソフト両面の安全対策にとって不可欠です。私たちの生活を支えるインフラの劣化は、ソフト面も含めて確実に進行しています。私たちの生活のしかたにも発災要因、被災要因が潜んでいます。
皆さんが担っている“安心・安全の確保”、“自然環境の保全”、“健康環境の創造”という役割は、ますます重要になってきています。
私自身、在職期間も少なくなり、皆さんと取り組んできた調査の総まとめに取り組んでいますが、これらのことを盛り込むことを強く意識しています。
近くに来た際には是非、顔を見せて下さい。健康第一!慶事は、一報を!
(伊藤陽司 記)

知床カムイワッカ川での調査を終えて。
今年のウインブルドン焼肉パーティーは、庭園(?)改装のため中止となりました。
○構造・材料系研究室(維持管理工学研究室・コンクリート工学研究室・地震防災工学研究室)
卒業生の皆様にはお元気でご活躍の事と存じます。昨年度同様、構造・材料系3研究室合同で研究活動を行っております。本年度から三上教授が社会環境工学科学科長に就任され、いっそう多忙な日々をおくられております。また東北大学から崔(チェ)助教が赴任され、学生へのご教示頂いております。昨年に引き続き、大島特任教授、三上教授、宮森准教授、井上准教授、山崎助教、齊藤助教、坪田技官、研究補助員の北尾さんにもご助力頂きながら、総勢28名で日々研究や講義に励んでおります。
維持管理工学研究室では、三上教授、山崎助教、M1が2名、4年生が3名で研究を進めております。主な研究内容は、PVDF加速度計を用いた振動測定システムの検討、局部振動加振による損傷検出に関する研究、橋梁点検データを用いた劣化予測の検討、電磁波レーダー法を用いた床版の劣化予測などの研究を行っております。
地震防災工学研究室では、宮森准教授、齊藤助教、D1が1名、M2が4名、4年生が4名で研究を進めております。主な研究内容は、モード振幅の変化を利用した橋梁の損傷位置同定、スマートセンサーを用いた橋梁振動実験、釧路市における既存構造物を用いた津波避難に関する検討、サブストラクチャハイブリッド実験システムの構造実験部分の複数個所対応などの研究を行っております。
コンクリート工学研究室では、井上准教授、崔助教、M2が1名、4年生が4名で研究を進めております。主な研究内容は、亜硝酸系補修剤の浸透性および溶脱、インピーダンスハンマーによる既存コンクリート構造物の劣化診断技術、低品質再生骨材の表面改質によるコンクリートの性能改善、自己治癒機能を有する短繊維補強コンクリートの耐凍害性、寒冷地対応の新型耐寒剤の開発などの研究を行っております。
最後になりましたが、北見にお越しの際には是非研究室にお立ち寄り下さい。また、その際には実社会での体験などをお聞かせ頂ければと思います。卒業生皆様のご健康と益々のご活躍お祈りしております。
(井上真澄 記)

○雪氷系研究室(雪氷科学研究室・雪氷防災研究室・氷海環境研究室・寒冷地環境工学研究室)
2013年度末で高橋修平先生が定年退職されました。高橋先生は1979年4月に北見工業大学一般教育等物理に赴任され、その後35年の長きに渡り、北見工業大学の物理教育とともに雪氷学の教育と研究に大いに尽力されました。それを記念して、2013年1月31日(金)には北見工業大学C122講義室にて最終講義、3月8日(土)にはホテル黒部にて退職記念祝賀会を開催いたしました(写真1)。この祝賀会には高橋修平先生の指導を受けた学生の皆さんも多数参加されました。多くの卒業生に連絡したはずですが、もしかしたら連絡が行かなかった卒業生の方もいるかもしれません。この場を借りてお詫び申し上げます。
また、高橋先生の退職を記念して、退職記念誌『雪と氷とともに』(A4版349ページ)を作成しました。若干の残部がありますので、希望する方には1冊3,000円でお送りします(送料込み、先着順)。希望者は下記まで連絡してください。
連絡先:亀田貴雄(kameda@mail.kitami-it.ac.jp、0157-26-9506)

写真1 退職記念祝賀会での高橋先生と奥様

写真2 雪壁雪渓測量調査隊(2014年9月14日早朝、高原温泉)
また、9月14日大雪山系の雪壁雪渓測量調査に行きました。メンバーは亀田、白川、山本(白川研M1)、春島・山崎(白川研4年)、原田(学部2年、山岳部)の計6名でした(写真2)。昨年は過去20年間で雪壁雪渓の面積が最も大きい状況でしたが、今年は例年なみの大きさでした。夏の暑さ、降雨、冬季の積雪の何が効いているのかは今後の研究課題です。
(亀田貴雄 記)
○雪氷科学研究室
今年の雪氷科学研究室はD3の学生が3名(日下、横山、平松)、4年生が4名(太田、大野泰輔、久次米、崎山)です。4年生の卒論テーマは南極ドームふじの積雪データの解析(太田)、南極氷床氷の含有空気量の測定(大野泰輔)、雪結晶生成実験(久次米)、氷結晶中のチンダル像の研究(崎山)です。これらの学生を亀田と大野浩助教で指導しています。含有空気量の測定実験では信山技術員に協力していただいています。学生さんの部屋はこれまで総合研究棟7階でしたが、今年から以前の高橋先生の学生さんの部屋に移動しました。また、亀田の教員室もこれまでの部屋から二つ奥の高橋先生の場所に移動しました。
亀田は厚さ1~2cm程度の水で飽和したぬれ雪表面にできる白い斑点模様(「斑点ぬれ雪」と命名)を調べており、英語論文が受理されました。信山は9月4日から3日間、北海道大学で技術職員の総合技術研究会に参加し、北大の低温研を見学して来ました。低温室はどこも寒さは変わらないと実感し、もう低温室はいいなと思いました。
先日、求人関係で五明龍哉くん(14期)がひょっこり来ました。相変わらず体が大きく、元気そうでした。遠軽高校で南極の話を亀田がした際に、遠軽町役場に勤めている田嶋啓造くん(11期)と山口香澄さん(15期)に会いました。2人とも元気そうでした。卒業生の皆さんは北見に来ることがあれば研究室に顔を出して下さい。
(亀田貴雄 記)
○雪氷防災研究室
永年にわたり本研究室を主宰されてきた高橋修平先生が無事定年を迎えられ、3月末にご退職されました(写真)。先生は4月から道立オホーツク流氷科学センターの所長として月に1回の頻度で紋別に通われています。先生より「皆さまによろしく」とのことでした。4月以降は私(白川)が研究室を引き継ぎました。これまでの伝統を大切に、明るく活気のある研究室を目指していきます。OBの皆さん、ぜひ研究室にお立ち寄り下さい。
(白川龍生 記)

○氷海環境研究室
舘山です。卒業生の皆さんお変わりありませんか?今年から雪氷系研究室の学生部屋がそれぞれ独立することになり、氷海研は第一総合研究棟7階に残りました。研究室の雰囲気が大きく変わりましたので、是非遊びに来て下さい。
氷海研の今年の4年生は高瀬雄麻君と森下裕士君、吉田僚君の3名が配属されました。高瀬君と森下君は大学院進学が決定、吉田君はゼネコン系の会社に就職を目指して活動中です。今年の主な活動を報告します。9月21日から10月17日にかけて、博士後期課程3年の田中君と前期課程2年の星野君の2名がカナダ砕氷船ルイSサンローランに乗船しています。また、今年度から新しい教育プログラムとして海洋調査実習が始まり、ガリンコ号IIでの紋別沖実習、おしょろ丸での十勝沖実習にも参加しています。

氷海に沈む夕陽
(舘山一孝 記)
○寒冷地環境工学研究室
寒冷地環境工学研究室は早いもので今年で9年目を迎えました。今年度も3名の卒研生が配属になりました。全員土木の関連分野で各自の希望の就職先に内定しました。卒業研究のテーマは、今年度は諸事情により例年と異なり3名ともガスハイドレートに関する計算を中心にする予定です。また、今年度は雪氷系の研究室とは独立に活動していますが、今後はこの分野で他の研究室との研究上の交流がはかれれば良いと思います。
(堀彰 記)
○交通工学研究室
現在、研究室には、川村教授を代表に、筆者(富山)、博士後期課程1名(留学生)、博士前期課程2名、学部生4名が在籍しています。現在、昨年度よりスタートした、海外の大学との共同研究も活発化し、成果発表に向けた準備に取りかかっています。また、筆者が筆頭となりまとめた、本学発の路面測定技術を活用した舗装モニタリングに関する研究で,土木学会第18回舗装工学奨励賞を受賞するなど、研究室は非常に活気づいております。卒業生の方々のご活躍ぶりを耳にすることも多く、ご多忙のこととは存じますが、近くにお越しの際には、是非ご歓談の機会を持てますと幸いです。

舗装工学奨励賞授賞式にて(筆者)
(富山和也 記)
○都市・交通計画研究室
本年は豪雨災害に火山噴火と、日本に災害が立て続けに押し寄せています。研究室の研究も防災を主軸に地域交通問題など、常に人々の生活や暮らしに直結したテーマを継続しています。特に今年は北大と共同で冬季の暴風雪災害について取り組んでおり、合同でヒアリング等を実施するだけでなく研究以外での交流も行いました。また10月には本学と室工大、北大と続く防災リレーシンポジウムの企画も担当することとなり、研究活動が少しでも国土の強靭化に貢献できればと思うこの頃です。
(高橋清 記)
○ハイドレート研究室
卒業生の皆様、ご無沙汰しております。ハイドレート研(環境・エネルギー研究推進センター)では今年3月に庄子教授が定年退職し、八久保研究室のみとなりました。今年度は卒論生の太田・中山・淀川、院生の清水の計4名が研究活動に勤しんでいます。すでにサハリン島沖(6-7月)、バイカル湖(8月)の恒例の海外調査を終え、M1の清水君がGHガスサンプリングで活躍しました。9月にはガリンコ号による紋別沖での海洋調査実習、という初の試みが控えています。全学から募った40名以上の学生が乗船します。その後、11月には十勝沖で初の表層型GH調査を実施します。また、今年の雪氷学会(9月、八戸)では、私と学生で合わせて8件の研究発表をする予定です。そうそう、忘れられないのは今年8月、研究室卒業生OBの中川亮さんの結婚式に出席したことで、2次会宴会がほぼ研究室の同窓会、多くの懐かしい面々に会うことができました。皆様もお忙しい日常かと思いますが、もうすぐ涼しくなる季節、くれぐれも風邪など召されぬようご自愛下さい。北見に来られる際には、是非とも研究室にお立ち寄りください。
(八久保晶弘 記)
電気電子工学科
暑かったり寒かったりした夏もようやく終わり、北見ではもう紅葉が始まったこの頃ですが、皆様にはお元気でご活躍のことと存じます。同窓会の皆様にはいつも大変お世話になっており、この場を借りて御礼申し上げます。さて、私、はからずも2期続けて学科長を拝命することになりましたが、皆様のご協力をたまわって、何とかやって行きたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
学科の新メンバーをご紹介いたします。まず、吉田策先生の後任として昨年10月に黒河賢二教授(電気基礎研究室)が着任されました。黒河先生は光ファイバーがご専門で、講義は電気磁気学などをご担当いただいています。ご着任早々、岸本先生とともに「電気磁気学演習II」で平成25年度のベストティーチング賞を受賞されるなど、精力的に活動なさっていらっしゃいます。また、本年4月には保苅和雄先生の後任として、酒井大輔助教(応用電気研究室)が着任され、学生実験等でご活躍中です。酒井先生は本学大学院ご出身の同窓生でいらっしゃいますので、今後同窓会活動にもご尽力いただけるものと期待いたしております。さらに、電気電子工学科を5年間ご担当頂いた学科事務の高橋麻奈美さんが3月で退職され、代わって菊地麗心さんが採用になり、伊藤孝子係長の指導の下、4月から事務関係をお世話頂いております。他のメンバーは相変わらず元気に活躍しています。
学科として大変喜ばしいこととして、田村淳二教授が学務担当の理事・副学長となられ、野矢厚教授が研究担当の副学長に就任されました。学科の運営に直接学科の事に関わることは次第に減り、大学全体に関わるお仕事が増えるものと思いますが、本学のいっそうの発展にご尽力いただけるよう、学科一同ご協力させて頂きたいと考えております。
さて、この原稿を書いているところへ、赤崎、天野、中村の三氏に対するノーベル物理学賞受賞のニュースが届きました。青色LEDの開発に対する功績ということですが、この三氏は工学部所属ということで、特にうれしく思います。物理学というより、世の中(=人々の暮らし方や経済など)に与えたインパクトが評価されたものと思います。工学部は人類の役に立つことを教育・研究する所で、ノーベル賞に工学賞はありませんが、広い意味で我々の分野から受賞者が出たのは大変喜ばしいことです。将来本学からノーベル賞受賞者が出るかはわかりませんが、我々も日々励みたいものだと思いました。
これから寒い季節に向かいますが、同窓生の皆様にはお元気でお過ごし下さいますように。
(学科長 谷本洋 記)
○電気基礎研究室
卒業生の皆様、お元気にお過ごしでしょうか。昨年の10月に吉田先生の後任として着任しました黒河と申します。電気基礎研が今後も益々発展するよう微力ながら尽力してまいりたいと思いますので、よろしくお願い致します。
さて、今年は、4年生11名、大学院修士1年1名の合計12名が所属しております。1名の大学院生は、研究活動、TA、4年生の指導と大忙しですが、元気に頑張っております。また、4年生の就職希望者も無事内定をもらい、残り少ない学生生活を満喫しつつも卒論に向けて研究に励む日々です。
今年の北見は、6月に37.2℃という観測史上最高気温を記録するなど異常に暑い夏となりました。川村先生は、国際会議でフィンランドに出張するなど制御工学をベースとしたロボット・ITSの研究を強力に推進されるとともに、精力的に学生の育成に取り組まれています。岸本先生は、学生実験、電気磁気学演習、そして4年生の指導と大忙しです。大内先生は、学生実験のサポート、ロボット部品加工等、引き続きご活躍いただいています。黒河は初めての4年生と一緒に、ファイバヒューズと呼ばれる光ファイバの燃焼伝搬現象の研究に取り組んでいます。
卒業生の皆様の益々のご活躍を期待しております。お近くにいらっしゃる機会がありましたら、ぜひお立ち寄りください。皆様にお会いできるのを一同とても楽しみにお待ちしています。
(黒河賢二 記)
○応用電気工学研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年は全国各地で異常気象が頻発しており、北見でも突発的な雨や急激な温度変化が見られます。体調管理には十分気をつけたいと思います。現在の応用電気工学研究室についてご報告いたします。
今年度は、新たに酒井助教が着任されました。その為、医用生体工学を研究している谷藤教授、ブレイン・マシン・インターフェースの研究をしている橋本准教授に加え、酒井助教のもと機能性光学材料に関する研究も開始されました。研究室のメンバーは、修士2年生が2名、修士1年生が1名、学部4年生が10名です。
特に今年度は、学部生の内4名が本学大学院、1名が他大学大学院へと進学することが決定しており、来年以降の研究室も先輩とともに頼もしく引っ張ってくれることでしょう。他のメンバーにおきましても無事に就職が決まり、メンバー一同、各々の修士論文や卒業論文に向けて奮闘をしております。日夜研究に取り組み、時には辛い顔を見せることもありますが皆、楽しく研究をしていることが伺えます。
しかし、今年度は谷藤教授が退任される別れの年でもあります。長年務められており、私共々お世話になった方も多いのではと思います。卒業生の皆様、ご多忙ではあるかと思いますが北見にお越しの際はぜひお気軽にお立ち寄り下さい。教員・学生共々、皆様との歓談の機会を楽しみにしております。皆様のご健康と一層のご活躍をお祈りいたします。
(M2松本峻 記)
○電力工学研究室
平成26年度は、博士課程3名、修士課程9名、学部10名、研究生1名の全23名の学生と、小原、植田先生、仲村先生、モレル・ホルヘ特任研究員のスタッフ4名で、合計27名の大所帯です。本年度の電気システムコースの就職は小原が担当しましたが、景気の上昇を背景にして非常に多くの求人がありました。特に電気エネルギー関連の技術者を求める企業、官庁、役所、団体が多く好調でした。当研究室の修士2年は三菱電機、北海道糖業に内定し、学部4年の6名は全員大学院への進学を決めました。当研究室ではマイクログリッドなどの分散エネルギーについて研究を進めていますが、これに関連して電力事業の発送電分離や、住宅などを対象とした電力小売り自由化が近く予定されています。これらの動きに対応するため、文部科学省の大型予算でスマートグリッドシミュレータを社会連携推進センターに導入しました。また、学生が自由に使える数値解析用ワークステーションの整備や、大所帯となった研究室の再編、研究室の学生による社会貢献活動なども行っております。積極的な学生が多く、明るい研究室ですので是非お立ち寄りください。
(小原伸哉 記)

○電気機械研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。現在の電気機械研究室は、本年度の4月からLINDA SARTIKAさん(インドネシア)が博士課程に、10月から張洪銘さん(中国)が修士課程にご入学されて、博士課程1名、修士課程9名、卒研生10名と田村教授、高橋准教授、梅村助教、小竹技官、Marwan研究員の総勢25名と大変賑わっております。
研究室の状況といたしましては、国内での学会参加のほか、7月に東京で開催された The Grand Renewable Energy 2014 International Conference などの国際学会に参加しております。また、9月にイタリアで開催されたRPG2014にも参加予定でしたが、飛行機乗り継ぎ先の航空会社がまさかのストライキ活動により、イタリアへ飛べず学会へ参加できませんでした。
近年の地球環境問題や原子力発電の見直しから当研究室で行っている風力発電の研究はますます重要になってきており、各々の学生が自分なりに研究に取り組み、さらに学部生および修士の学生は隔週に1度の研究報告会で自身の研究結果を発表する等,学生間または先生を含めた議論も行われております。その他,研究室の活動はホームページに記載されておりますのでご覧いただけると幸いです。
このように電気機械研究室は大変賑わっておりますので、卒業生の皆様、お近くにお越しの際は是非お気軽にお立ち寄りください。卒業生の皆様の益々のご健康とご活躍を祈念しております。
(M2井口智博 記)

Grand Renewable Energy 2014 International Conference会場前にて会議へ参加のMarwan研究員(右から二人目)とそのご友人達
○集積システム研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年は、谷本教授、吉澤准教授、大学院生7名、学部生10名、計19名の体制で日々励んでおります。今年は大学院生が増えたこともあり学会発表の機会が多くなるようです。7月の電子回路研究会や9月の電気学会C部門大会で学生が成果発表を行いました。今後も北海道連合支部大会やAVIC2014国際会議、APCCAS2014国際会議などの発表を予定しています。また、2月に追いコン、3月にワカサギ釣り大会、5月に4年生歓迎会、7月にバーベキューパーティ、9月に9月卒業学生の送別会などの研究室行事を行いました。写真はワカサギ釣り大会の様子です。天候には恵まれたのですが時期が遅いこともあり、あまり釣れませんでした(私とS君はボウズ)。来年はリベンジしたいところです。北見近くにお越しの機会がありました際には是非研究室にお立ち寄りください。
(吉澤真吾 記)
出雲大社にお参りしましたら、内定通知や論文の採録通知が届くなど不思議なことがありました。
(谷本洋 記)
とうとう研究室に博士課程に進学する学生がでました。M2になってもまだチャレンジャーが居ます。
(D.S. 記)
とうとう博士課程に進学することになりました。
(T.S. 記)
マレーシアの原住民と戯れる予定です。
(R.I. 記)

○波動エレクトロニクス研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。2014年度の波動エレクトロニクス研究室のメンバーは大学院生2人、学部4年生7人となっております。特に、大学院生は修士論文作成に向けて研究を進めており、7月に室蘭で開催された光・電波ワークショップや10月開催の北海道支部連合大会で研究成果の発表を行っています。
一方で教員はといいますと、杉坂純一郎先生は実サイズの回折格子に対する電磁界解析に取り組まれており、光エレクトロニクスや電磁界解析の分野でご活躍されております。教育では学生実験と電気回路演習をご担当されています。
平山浩一先生は光・マイクロ波帯でのデバイスの最適設計や、マイクロ波・ミリ波帯での材料定数の推定方法に関する研究に取り組まれております。教育では電気回路基礎と高周波計測をご担当されています。
安井は光導波路デバイスの最適設計に取り組むとともに、超音波デバイスの数値解析手法に関する研究も少しずつ進めております。教育では電気回路Ⅰと電磁波工学を担当しています。
近くにお越しの際には研究室にも是非お立ち寄りください。卒業生の皆様のご活躍を祈念しております。
(安井崇 記)
○通信システム研究室
卒業生の皆様におかれましてはお元気でご活躍の事と存じます。現在、通信システム研究室の構成は柏教授、田口准教授、今井助教の教員3名、そして、学部生7名の計10名となっており、日々研究に励んでおります。また、来年度は2名の学部生が大学院へ進学する予定となっております。
本研究室では、現在、主に高度情報化社会及びユビキタス社会を見据えた高度な移動通信システムを構築するための研究を行っております。その一環としてITS技術を利用した自動車衝突防止システムに関する研究、マイクロ波・ミリ波・光波に関する研究、自動車搭載アンテナの最適設計に関する研究等を行っております。また、電波吸収体に関する研究も行っております。他にも、科学研究費テーマ及び企業との共同研究等に対しても研究室一丸となり精力的に取り組んでおります。更に、本年度は柏教授が電子情報通信学会エレクトロニクスシミュレーション研究会の委員長へ就任、本学で9月に開催されたEMCJ・EST研究会において特別講演を行う等、学会活動にも精力的に取り組んでおります。
尚、研究室近況は通信システム研究室ホームページにて公開し、随時更新しております。お時間がある時にでもご覧頂けると有り難いです。
(田口健治 記)
○集積エレクトロニクス(旧電子物理学)研究室
卒業生の皆様お元気にご活躍でしょうか?
研究室だよりを書く季節となりました。今年は天候の異変も多く、噴火もありで、日本も大変な状況になっておるようです。北見も、結構雨が多く、夕立などという可愛らしいものでもなくなってきております。また、いつになく秋が足早に訪れており、ご老体に寒さが沁みます。
今年も、スタッフは、野矢、武山、佐藤に変わりはありません。野矢はそろそろ身辺整理の時期となりましたが、片付けは得意でなくさっぱり進んでおりません。武山先生は、親分の研究フィールドから独自の研究テーマへと移行が進んでおります。佐藤はもっぱら体で働いておりますが、見ていると空回りの感も拭えません。
今年は7名の卒研生を迎えました。7人7様?で、何かやっておるようです。最近の学生さんは、自分を変えようとしない傾向が強いので、何かを言っても徒労に終わりますので、好々爺よろしくハイハイということが多くなって参りました。今年のぼやきはこれだな。
(野矢厚 記)
情報システム工学科
卒業生の皆様、お元気で御活躍のことと思います。
今年度の情報システム工学科は、昨年度から教職員の転入・転出はなく、同じメンバーで日々の業務に励んでおります。こう書くと平穏な日常を想像されるかもしれませんが、実は現在、国立大学は風雲急を告げるとでも言うべき状況となっており、その詳細につきましては、おそらく学長がお書きになっているのではないかと思います。
文科省が主導する国立大学改革プランにより、これからの何年かで北見工大は大きな改革を迫られることになるかもしれませんが、情報システム工学科の教職員は、持前のポジティブ思考で変革期をチャンスに変え、荒波を乗り越えて行ってくれるものと思います。
幸い、この2~3年で情報関係の就職状況もかなり改善されてきており、情報技術者の需要がますます高まることが予想されていることは、我が情報システム工学科にとっては追い風になるものと思っております。
卒業生の皆様の益々の御活躍、御発展をお祈りいたしております。
(学科長 三波篤郎 記)
○知的システム設計分野
・システム制御研究室(榮坂俊雄研究室)
卒業生の皆様お久しぶりです。今年は学生11名が在籍し、ゼミや研究、就職活動はもとより、プログラミングコンテストへ友達と一緒に取り組んでいる学生も居てそれなりに人の気配する研究室になっています(笑)。
研究は、制御系のシミュレーションの他、ロボットやスマートフォンなども導入し、制御理論内での研究から複数の分野の知識も求められる研究まで幅広く行っています。ただ、実際の成果はこれからという感じですが、例年以上に就職活動が順調でしたので、後期からは何の憂いも無く研究活動にまい進してくれるものと期待しています。
最後に、来学された折には、ぜひ研究室にも立ち寄ってください。そして、大学と卒業後の経験談を聞かせて頂ければ、学生には新しい刺激になるかと思います。
(宿院信博 記)
・情報通信システム工学研究室(中垣淳研究室)
卒業生の皆様、元気でお過ごしでしょうか?
当研究室は新たな学生が増え計13人になり、よりいっそう賑やかに過ごしています。
研究は今まで同様に音声評価システムの構築、雑音抑圧、音声分析をすすめています。また、新たにマイクロホンアレイを用いた研究を始めました。今までと同様の研究をしている学生は変わりないですが、マイクロホンアレイを用いた研究を始めた4年生は頭を悩ませながら頑張っています。
進路の方はほとんどの人が決まり、中垣先生もホッとしているのではないかと思います。
今年は他の研究室との交流も増え、合同での飲み会や、ゲストとして学生を呼んだりしてスペアリブ、中華料理、チーズケーキなど料理の幅を広げつつ皆でワイワイと楽しくやっています。
もし、当研究室出身のOB、OGの皆様が近くにお越しの場合は、ご一報頂ければ料理に腕をふるって歓迎会をしたいと思います。
(M2 石山貴彦 記)
・鈴木育男・岩館健司研究室
本研究室は、M2:1名、M1:1名、4年生:6名の学生を鈴木育男准教授、岩舘健司助教の2名の教員で研究指導を行っています。
本研究は、(1)人間行動解析システムの構築と運動学習支援に関する研究、(2)仮想物理環境下における仮想生物の行動生成・学習に関する研究、という2つの研究テーマで研究活動を行っております。また、昨年度より同じ知的システム設計工学分野の4研究室で「複雑進化系設計研究ユニット」を立ち上げ、その中で(3)人とロボット間のコミュニケーションの獲得に関する研究も実施しております。
卒業生の皆様、お近くにお越しの際は是非お気軽にお立ち寄りください。
(鈴木育男 記)
・信号処理研究室(鈴木正清研究室)
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか?
信号処理研究室は、教員1名と技術員1名に加え、CS科目の3年生4名と卒業研究の4年生2名で、「センサアレイ信号処理」の研究と、「サケ自動追跡ロボット船」、「国際会議の電子投稿システム」および「北見市内立小中学校の備品と図書の管理システム」の開発を行っています。
卒業生の皆様、近くにお越しの際には是非ともお立ち寄りください。
(鈴木正清 記)
○知識工学分野
・医療情報・医用画像工学(早川吉彦研究室)
プログラミングコンテストRICOH & Java Developer Challenge Plus 2012 & 2013では、2年連続で「オラクル賞」を獲得しました。素晴らしい挑戦と成果です。2年目の写真を1枚添付します。表彰式後のパーティーで日本オラクル社の方々と撮影したものです。さて3年目、2014年度は4年生8名のチームで挑戦しています。10月1日、チームに一次選考通過の通知が届きました。最終選考会は12月7日に日本科学未来館で開催です。
2014年9月、D3の董建君に博士号が授与されました。在籍中にImpact Factor のある学術雑誌に3編の論文を著しました。10月からは筑波大学研究員(工藤博幸研究室)です。M2の宮中君は、北米放射線医学会年次大会(RSNA2013)のMobile Connect Theaterで英語で講演し自信を深めました。M1の廣瀬さんは、カーリング選手として国際大会予選等の試合に挑戦中です。また、9月から新しい留学生の孫さんを迎えました。留学生は3名在籍です。
早川は、北見市医療福祉情報連携協議会(北まるネット)の会員ですが、地域医療連携のさきがけとし全国から注目されています。同じく医療情報の仕事として、日本歯科医学会のプロジェクト研究が新たに始まったところです。なお、10月には、分担執筆者として加わった本「画像処理」(未来へつなぐデジタルシリーズ、共立出版)が上梓されます。
(早川吉彦 記)

オラクル賞受賞後、喜びの記念撮影(日本科学未来館にて)
・テキスト情報処理研究室(桝井文人研究室)
卒業生の皆様如何お過ごしでしょうか。桝井研究室はスタッフ3名、学生17名の大所帯で、不夜城を維持しております。
新メンバーとして、3年生3名(大谷、佐々木、鈴木)と研究生の劉さんが加わりました。M2の上野、新田、ファム3名は早々に就職内定を受け、B4の畠山、平田、古澤3名は大学院進学が決まりました。M1の信太、福島はインターンシップに参加するなど、研究室の牽引役を担っています。9月には東京で初めてのOB会を開き、11名が参加して大いに盛り上がりました。
研究活動では、自然言語処理に加えて観光情報学、カーリング情報学の研究も軌道に乗り,今年度2件の学会表彰やカーリング全日本強化合宿での講義などの成果を挙げています。
以上、メンバーは変わっても雰囲気は変わらない桝井研です。お近くにお越しの際は是非お気軽にお立ち寄りいただき、スタッフや後輩達との交流をお願いいたします。卒業生の皆様のご活躍を祈念しております。
(熊本慎也 記)

・知能情報研究室(後藤文太朗研究室)
平成26年10月現在、研究室メンバーは、スタッフとして後藤、4年生が岩淵、森田の2人です。技術部からの派遣で奥山技術員の協力を得ています。CSセミナーの履修者(3年生)は前期5名、後期3名です。網走バス株式会社に協力していただき「バスロケーションシステム」に関連した研究開発をはじめています。
(後藤文太朗 記)
・知識情報処理研究室(前田康成研究室)
平成26年度の前田研は、M2黄君、トウさん、M1松浦君、B4上野君、佐々木君、坪井君、B3木村君、斉藤君、鈴木君、瀬崎君の計10名と技術員の奥山さんに前田です。
黄君はマルコフ決定過程の設備保全への適用、トウさんは料理レシピ発想支援方法、松浦君はマルコフ決定過程のロールプレイングゲームへの適用に関する研究を進めています。学部生の皆も頑張っています。
プライベートや出張でオホーツク方面にお越しの際には、是非、母校にもお立ち寄りください。
(前田康成 記)
・核科学情報工学研究室(升井洋志研究室)
研究室は今年で10年目になりました。今年のメンバーは M1の宮川さん、4年の青木君、伊藤君、阿久津君、酒井君です。近年の研究室のテーマは核反応データベース活用と、観光情報学の2本立てです。オホーツク地区の放射線測定、データ共有とクラウド利用、観光の様々な観点をパラメータ化したことで新たな可能性を見いだす研究も行っています。今年は、秋季入学でタイからの留学生の Dittapon Sanitin さんがM1として来ましたので、研究室も国際的になってきました。
(升井洋志 記)
○光情報工学分野
卒業生の皆さんお元気ですか?昨年から情報システムの同窓会誌原稿は、情報システム工学科改組に伴って変更した4つの新研究分野で執筆しております。「光情報工学分野」は従来から光学、光情報工学および画像処理に関連した研究を行ってきたメンバーが集まってできていました。そこに所属するメンバーは、旧情報メディアネットワーク分野に所属していた亀丸俊一教授、三浦則明教授、原田建治准教授、桑村進助教と旧計算機科学分野に所属していた原田康浩准教授、曽根宏靖准教授の合計6名です。
亀丸研究室では、今年度は4年生の卒研配属は横田、中村の2名です。これに大学院学生の佐藤(周)を加えた3名で研究室が成り立っています。大学院生の佐藤もデジタル教科書の研究に励み、8月の札幌(江別)での全国大会で発表し、この後、中国武漢でのシンポジウムで発表する予定です。2名の4年生も頑張って研究に励んでおり、特に観光情報学分野で、温根湯温泉、層雲峡温泉、阿寒湖温泉などへのフィールド調査を予定しています。
三浦研究室では、M2の大石、M1の金沢、4年の阿部、大石、野口、八木、3年の河原崎、清信、工藤、熊川の総勢10名が補償光学、天体画像処理、道路画像処理などの観測、実験、ゼミに励んでいます。
原田建治研究室では、M1の原、菅原、4年の浅野目、氏家、神成、鈴木、3年の辻、桃井、松崎、楊の総勢10名がホログラム、偏光色、光学教材開発などの卒業研究や、セミナーに励んでいます。3年の楊は、現在フィンランドに留学中です。また、他の3年生は全員大学院に進学を予定しています。
今年の原田康浩研究室(光工学研究室)は、M2の藤田、淵脇、M1の松尾、学部4年の高桑、柳沢、ワフィ、CSセミナーの3年・田中、鳥羽、中井、長津の合計10名の学生で構成されています。それぞれ、ディジタルホログラフィの高性能化、逆フィルタリングによる3次元像回復、低温型雪結晶の生成と3次元計測、斜め写真の視点補正と解析、Raspberry Pi/Arudinoを使った教材開発等をテーマとして、先輩達の研究成果を参考に、日夜研究・ゼミにと励んでいます。原田は1年間の就職担当がようやく無事に(?)終了しそうで胸を撫で下ろしているところです。
曽根研究室では、M2の加藤、M1の福山、Ge shuai、4年の遠藤、大友、玉村、三田、3年の小竹、伊藤、河野、岩男の総勢11名が、光ファイバーを用いた光情報処理やLEDを使った可視光通信などの研究やゼミに励んでいます。
OB、OGの皆さん、北見へお越しの際には、北見工大をお尋ね下さい。そして遠慮せずぜひ私たちの研究室を訪れ、焼肉の街北見の夜の繁華街へ私たちをお連れ下さい。お互いの近況報告で盛り上がりましょう!
(原田建治 記)
○情報数理研究室
大学院生は三波研究室に2名在籍しております。M2の可瀬孝介君は「GPUによる周期25位上の複素エノン写像の周期点算出の高速化」が研究テーマです。研究成果がいろいろ出てきており、1月の研究集会において研究成果発表予定です。また関東地方にあるソフトウェア会社に就職内定しました。M1の榎本亮士君は「高次元エノン型写像の周期点計算とその可視化」が研究テーマです。就職はIT関係を希望とのこと。
4年生は4名在籍し、大槻麻衣子さんは河野研究室で数論を学んでおり北大大学院数学専攻に進学予定、佐藤工紀君は鈴木範男研究室で確率論を学んでおり北大大学院数学専攻に進学予定、吉良仁考君は渡辺研究室にて幾何学を学んでおり北大大学院数学専攻に進学予定、牧田真朋さんは山田研究室で準同型暗号を学んでおりやはり大学院進学希望です。
(三波篤郎 記)
バイオ環境化学科
卒業生の皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。化学システム工学科からバイオ環境化学科に学科名が変更され、現4年生が4期生になります。本学科の建物は工業化学科と環境工学科の建物を改築して使用しています。環境工学科設置以前の工業化学科には四つの研究室がありました。1研(佐々木満雄先生)を継承している研究室はありませんが、2研(荒瀬晃先生)は精密有機資源化学研究室が、3研(本間恒行先生)は炭素変換工学研究室が、同じく3研(福井洋之先生)は環境物理化学研究室が、4研(多田旭男先生)は無機物理化学研究室が継承しています。その中で、炭素変換工学研究室を長らく運営してこられた鈴木勉教授が本年度をもちまして定年退職されます。鈴木先生には35年以上にわたり北見工業大学における教育研究に従事していただき、多くの優秀な卒業生を輩出されてこられました。長い間、本当にありがとうございました。これからの日々が鈴木先生にとってさらに豊かでありますよう祈念しております。
3月に定年退職された青山先生の後任に、齋藤徹教授が名古屋大学から4月に着任されました。齋藤先生の専門は分析化学、反応・分離工学で、新しく環境分析化学研究室を立ち上げました。講義科目は水環境化学、分析化学演習、機器分析学で、担当学生実験はバイオ環境化学実験Iです。着任早々、教務委員を担当していただき、公開講座や授業等の改革に手腕を発揮されています。
大学も新陳代謝をしながら、時代の要請に応えていかなければなりません。
現在の北見工業大学は、工業化学科や環境工学科があった当時と比較して明るくきれいになっています。北見近郊にお寄りの際は、是非本学にお立ち寄りください。卒業生の皆様のご健康とご活躍をお祈りしています。
(学科長 星雅之 記)
○環境分析化学研究室
環境分析化学研究室は平成26年に誕生したばかりで11月に3年生が合流します。近年、医療行為や日常の健康維持で使用される薬物による生態系への影響が懸念され、対策が求められています。本研究室では、薬物をはじめとする高生理活性物質の分析技術を開発するとともに、これらの物質を迅速かつ一斉に水中から除去する新たな発想の医療排水および公共排水処理技術の開発と実用化を予定しています。さらに、新たな分離科学を基盤とする資源回収技術の開発に着手し、北見の地に魅力的な産業を興すことを目指します。皆様の暖かいご支援に支えられながらチャレンジ精神に溢れる若者を育成します。
(齋藤徹 記)
○生物化学研究室
卒業生の皆様、お元気でご活躍のことと拝察いたします。26年度の生物化学研究室は吉田教授を筆頭に、学部学生:15名、M1:3名、M2:3名、D1:1名、D2:3名、D3:5名、研究員:2名、助教:3名の総勢36名でギネス登録なみの超大所帯です。昨年の秋に、内モンゴルからの留学生バイさんがめでたく学位を授与されました。続いてこの秋にも中国からのチョウさんが学位修得の予定です。吉田教授は、新たに理事(副学長)に選任されました。これまで以上に大学運営に関わる会議、研究、授業、さらには我々への指揮、指導と多忙を極められ、加えて本学と文科省の間を月に何往復もし、もちまえのスーパーマンぶりを存分に発揮されておられます。小俣助教は複数の学部学生を担当するかたわら、博士後期学生にとって博論を仕上げるために要となる難度の高い精密な実験を労をいとわず補完されています。韓助教も有用な整理活性を付帯する、デンドリマーをベースとした新規糖鎖化合物の新たな合成法の創作に余念がなく、夏休み返上で実験に取り組んでおられます。沖本助教は相変わらずで、最近やっと学生の顔と名前が一致するようになりました。住佐研究員は多くの学生の指導にあたり、主に微生物やDNAにかかわった研究を精力的にこなしています。最近、努力の甲斐が実りその成果が論文に掲載されました。今では吉田研にはなくてはならない人材となっています。もう一人の研究員リョウさんは吉田研出身で主にバイオエタノール系の研究を進める学生を指導し、着実に研究結果を進展させ、今秋国際学会での発表を念頭にその準備に尽力しています。ちなみに、6月の学校祭では吉田研所属の留学生が企画したモンゴル料理店と中国料理店が、食材の珍しさのためかことのほか繁盛していました。お近くこられた際には是非お立ち寄りください。
(沖本光宏 記)
○バイオプロセス工学研究室
OBの皆様いかがお過ごしでしょうか?
本年度の学生はMC3名、4年目6名で、相変わらず楽しくやっております。学生の就職状況ですがなかなか大変で苦労しています。OBの方で採用を検討している方は是非情報をご提供ください。研究面では、バイオリファイナリー研究や光合成微生物による物質生産に注力してきましたが、最近はゲノム解析やプロテオーム解析に基づく有用物質生産菌の分子育種に取り組んでいます。研究内容は研究室ホームページを参照ください。
また近況を是非堀内宛にメールが電話でお知らせください。(horiucju@mail.kitami-it.ac.jp、電話0157-26-9415)楽しみにしています。こちらに来る機会がありましたら是非研究室にもお立ち寄り下さい。
(堀内淳一 記)
○精密有機資源化学研究室
卒業生の皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。北見は6月3日に記録上最高の37.2℃の気温をマークしました。湿度が低いので、真夏の暑さほどではありませんでした。お盆を過ぎてから気温が急に下がり、夜は窓を閉めなければならなくなりました。
4月から霜鳥先生が当研究室のスタッフに加わりました。これまで青山先生(3月定年退職)の研究室に4年間所属され、専門分野は有機化学、研究テーマは主にリパーゼ触媒を用いた光学活性化合物の合成とその抗酸化作用の評価について研究されています。今年度から「毒性学」の授業を担当され、学生実験はこれまでと同じ「バイオ環境化学実験I」を分担されています。霜鳥先生が加わったことによる研究室のいろいろな変化が楽しみです。
今年度の研究室は博士1年1名、修士2年2名、学部4年7名と昨年と同様に大所帯となっています。修士課程を修了した及川飛鳥君が博士課程に進学しました。自分の研究はもちろん、後輩の面倒をよく見てくれています。私はいつものように授業のない日は実験をしています。就職は修士2名及び学部5名とも内定し、今年は就職希望者全員が決まりました。学部2名は本学の大学院に進学する予定です。今年も恒例の屈斜路研修所での宿泊研修を行いました。今回は久しぶりに裏摩周と神の子池にも足を伸ばしましたが、霜鳥先生が学会で参加できなかったのが残念です。写真は屈斜路湖の砂湯でのスナップです。
北見にお寄りの際は、ぜひ研究室にお立ち寄りください。皆様のご健康とご活躍をお祈りしています。
(星雅之 記)

○炭素変換工学研究室(平成26年度)
最後の研究室メンバーはM2の百﨑、4年生の大塚、亀山、清水、相馬、平岡、技術補佐員の鈴木(計7名)で、木質バイオマスの触媒炭化によるキャパシタ、導電性炭素、ナノグラフェン、水素製造の研究に励んでいます。全国をゲリラ豪雨が襲うなど確実に地球温暖化が進む昨今、35年前から研究を続けてきた触媒炭化による木材利用技術が注目されるようになり、鈴木教授は成果を発信すべく、講演や原稿執筆等で忙しくしています。あの熱い炭化炉やタールの臭いの中で青春を過ごした皆様方の努力がいよいよ報われる時が到来しそうです。長い間の応援、ありがとうございました。今後もどうぞお元気でご活躍下さい。
(技術補佐員 鈴木京子 記)
○環境有機化学研究室
卒業生の皆様におかれましては、お元気にご活躍のことと存じます。
今年度の環境有機化学研究室は、兼清泰正准教授、修士2名、および学部4年生4名から構成されています。研究室創設から8年がたち、この間の学生の皆さんの努力が、目に見える研究成果として実りつつあります。例えば、昨年10月には、当研究室で開発した糖センサーを取り上げた書籍が出版されました。また、ボロン酸を用いた超分子システムに関する書籍の執筆が目下進行中です。
現在当研究室では、従来取り組んできた糖センサーの研究に加え、シックハウス症候群の原因物質や活性酸素など、バイオ・環境・食品に関わる様々な化合物をターゲットとして、新規センシングシステムの創製に取り組んでいます。今後とも研究のさらなる発展に向けて一同邁進していく所存ですので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
(兼清泰正 記)
○食品栄養化学研究室
今年度の学生の構成は、4年生6名(岡島俊貴、菅井椋太、鈴木悠太、玉田しおり、米谷萌美、渡辺江美子)、修士2年2名(関本将吾、戸田一也)、博士2年1名(楊立風)です。卒業生の進路は、6名が民間企業への就職を決めております。また、新たに博士後期課程大学院生をモンゴルから受け入れる予定です。研究は、ハマナス花弁、ウーロン茶、黒ニンニク、ヤブマメ、大豆などの食品成分によるアレルギー抑制効果および活性酸素ストレス抑制効果について進めています。同窓会の皆様の御指導・御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
(新井博文 記)
○生物無機化学研究室
卒業生の皆様、お元気ですか。2014年度のメンバーは、菅野の他に、M2:1名、M1:2名、4年生7名(内仮配属1名)の総勢10名、再び二けたの人数となり例年同様にぎやかです。“無機材料の機能を活用する”という大研究テーマのもと、アパタイト、ホタテ貝殻(炭酸カルシウム)、粘土(無機層状化合物)を用いた薬物徐放材料や環境浄化材料の開発、さらにチタン金属表面における骨生成挙動の解明に関する研究を行っています。本年10月末に中国で開催されるワークショップに院生2名と参加し、1件の口頭発表、2件のポスター発表を行う予定です。さらに、2015年1月に北見で開催される化学工学・粉体工学発表会、2月の修論発表会、卒論発表会、3月の年会に向け頑張っているところです。
メンバーの進路は、M2および4年生合わせて7名のうち、2名が本学大学院進学予定であり、他もほぼ会社の内定を得ています(2014年9月現在)。
最後になりましたが、皆様の益々のご健勝を祈念しております。機会があれば、研究室にも足をお運びください。
(菅野亨 記)
○無機物理化学研究室
▼スタッフ:岡﨑准教授。▼学生:博士前期2年2名、1年3名、学部4年5名の総勢10名。進学希望者は3名(他大学2名)。就職戦線は概ね内定が決まり、残り1名。▼大学祭はオープンキャンパスで参加し、新エネルギーについて説明。人が入れるシャボン玉、瞬間アイスは子供に大人気。▼今年も美幌小学校でソーラーカー工作を行う。「北見科学の祭典」と同様に理科離れを食い止めるように活動。▼キャンプは浜頓別温泉コテージ2泊3日で開催。雨模様の中、浮き世を忘れて、焼き肉しながらひたすら飲んで、遊んで、温泉三昧。▼大学院生2名とTOCAT7(京都開催)に参加。久しぶりの京都観光。▼ホームページ公開中。リニューアルは思うように進まない。▼岡﨑:De-NOx反応、メタン直接分解、LIB用電極材料、廃プラスチック接触分解に研究を展開中。オホーツクエネルギー環境教育研究会委員長として、網走管内小中高の先生と連携を模索中。出張講義で飛び回っています。▼今年も多数のビール券ありがとうございました。卒業生のなんでも相談をいつでも受け付けます。0157-26-9420(岡﨑)、FAX 0157-24-7719。zaki@catal.chem.kitami-it.ac.jpまでメールを。
(岡﨑文保 記)

2014/9/8宗谷岬にて
○生体分子化学研究室
卒業生の皆様、お元気ですか。ここ、北見は大きな変わりなく日々が過ぎています。本年度、当研究室は教員のみで講義・研究に多忙な毎日です。担当科目が4つに増え、実験する時間があまりなくなりました。皆様のご健康とご活躍を祈念しています。
(服部和幸 記)
○環境高分子化学研究室
同窓生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。私共、環境高分子化学研究室は今年度、教員の中谷久之教授、宮﨑健輔助教、博士3年三浦雅弘君、博士2年に浜舘雅人君、修士2年に佐藤亮作君、佐藤宏明君、学部4年に小山春紀君、越智貴己君、佐々木達平君、佐藤直樹君、木村大輝君、高橋弘貴君、松本直也君というメンバーで日々研究に勤しんでおります。研究内容は、可視光分解型プラスチックの開発、塩化ビニルのアップグレードリサイクル、劣化センサーを持つプラスチックの開発、リサイクルプラスチックの高付加価値利用を研究しております。
同窓生の皆様で、上記の研究内容を含めプラスチック関係に興味がある方がいらっしゃいましたら、お気軽にお声をかけてください。
(宮﨑健輔 記)
○環境物理化学研究室
同窓生の皆さんにおかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。今年度の研究室のメンバーは三浦と松田技術員、学生は学部4年生が2名、M2が2名とこぢんまりした構成で研究などを行っています。昨年もお知らせしましたが、機器分析センターに導入された600MHz NMRは松田技術員の日頃のメンテナンスなどの努力により順調に稼働しておりますが、何せ強力なアイテムということで共同利用装置としての稼働率が異常に高く、当研究室の測定時間の確保にも苦労している次第です。
私事になりますが、大学時代の同級生もそろそろ一線を離れる方も多くなり、久しぶりに北見において9月に同期会を開催しました。北海道外からの4名を含めて16名が参集して学内や学生寮などの見学もしましたが、大学の発展ぶりや施設の充実などに驚いておりました。また別途、後輩でもある卒業生の大坂君、香川君、津川君が来北されて福井先生も交えて懐かしく懇談しました。
卒業生の皆様におかれましては健康に気をつけてお過ごし頂き、もし来北の機会があれば是非とも大学や研究室にもお立ち寄り頂きたくお願い致します。
(三浦宏一 記)

平成26年度環境物理化学研究室
○食品科学研究室
同窓生の皆様には、お元気にご活躍のこととお喜び申し上げます。当研究室では、本年3月に、学部生5名と大学院生(修士)1名が巣立ちました。一方、今年度は、大学院修士課程2年生が2名、4年生6名の8名の学生が在籍しております。学部生6名のうち、3名は本学大学院に、2名は他大学への進学が確定しております。
研究内容は、遺伝子組換え技術を利用した食用担子菌シイタケによる有用酵素発現、シイタケ・分泌ラッカーゼ発現メカニズムの解析、シイタケ栽培廃液に含まれるラッカーゼの解析、きのこ発酵食品の解析などです。
皆様のご活躍とご健康をお祈り申し上げますとともに、今後のご支援・ご指導をよろしくお願い申し上げます。
(佐藤利次 記)
マテリアル工学科
卒業生の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平成26年3月末に髙橋信夫先生が定年を迎えられましたが、平成26年4月1日からは本学の学長に就任されました。皆様もご承知のように、髙橋先生は、工業化学科の時代から今日のマテリアル工学科・同専攻・生産基盤工学専攻に至るまで、永年にわたって教育と研究指導に当たられ、さらに副学長・理事として大学の運営に貢献されました。国立大学には改革が強く求められていることから、今後は髙橋先生の全学的なリーダーシップの下、本学科も教育、研究、運営の各面で新しい取組みをして行くことになります。
昨年度の就職決定率は学部と大学院を合わせてほぼ100%に近い良好な結果となりました。今年度も、企業の採用意欲が高まっていることもあって、9月末時点で大学院生は9割、4年生は8割に達しています。
こうした動向の中で、教育と研究ならびに学生達の就職活動等の種々の面で、今後とも卒業生の皆様のご支援とお力とを頂ければ幸甚に存じます。
(学科長 平賀啓二郎 記)
○電子材料研究室
卒業生の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
今年度の電子材料研究室のメンバーは、阿部先生、川村先生、金のスタッフと学部4年生8名、大学院博士前期課程7名(M2・3名、M1・4名)です。
現在の主な研究テーマは、引き続き、エレクトロクロミック、有機ELや有機太陽電池などの様々な電子材料を用いたデバイスの特性評価や性能向上を目指し、日々熱心に研究教育に取り組んでおります。
今年も3月の応用物理学会をはじめ、学生の学会発表への参加も積極的に指導しています。10月には台湾で開催されたVASSCAA(Vacuum and Surface Sciences Conference of Asia and Australia)という国際学会で3名のM1が参加・発表を行っています。達成感を経験させて自信を高めると共に社会へと旅立つための良い経験になるように指導していきたいと心がけています。また、研究だけでなくバーベキューなどを通じて、楽しい思い出作りができるようにしております。
今年の研究室の大きなニュースは、阿部先生が指導されてきた韓国人留学生の李慶武(イギョンム)君が「ヘキサシアノ鉄酸金属錯体及びコバルト酸化物薄膜の電気化学的特性とそのエレクトロクロミックデバイスへの応用」のテーマで3月に博士後期課程を無事修了した事です。
卒業生の皆さんもお忙しいとは思いますが、北見近くにお越しの機会がありましたら是非お気軽に研究室にお立ち寄り下さい。皆様のご健康とご活躍をお祈りしています。
(金敬鎬 記)
○機能有機材料研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年度も、渡辺眞次教授、村田美樹教授、浪越毅助教の指導のもと、日々研究に励んだ充実した毎日を送っています。研究室のメンバーは、院生7名(M2・4名、M1・3名)、学部生7名の計14名となっています。昨年度と比較すると、水野綾士さんをはじめとするユーモアあふれる先輩方が卒業されてしまったこともあり、研究室が寂しく感じられた時期もありました。現在は全員の進路が決まり、全員が集まることも多くなり、再び活気が戻ってきたところです。
研究テーマは例年通り、有機合成グループは遷移金属触媒を用いたカップリング反応、高分子合成グループは異形高分子微粒子(主にポリスチレン、ポリイミド)の合成、リビングカチオン重合を中心に研究しています。どちらのグループも、週に一度の雑誌会や中間報告会も欠かさず続けており、学会への参加や学術論文の投稿による研究発表も積極的に行っています。
恒例行事であった山登りについては、学会等の都合上、行うことができませんでした。研究室でイベント等があった際は、掲示板や写真を更新していきたいと思いますので、是非ご覧になって下さい。
卒業生の皆様もお忙しいとは思いますが、北見付近にお越しの機会がありましたら、ぜひ研究室にお立ち寄りください。皆様の益々のご健康とご活躍を、心よりお祈り申し上げます。
URL http://www.mtrl.kitami-it.ac.jp/~watanabe/shoukai.htm/toppu.html
(2研 岡本梢 記)
○無機材料研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年の北見は雨が多く、地球温暖化を感じさせないような寒い日が多いように感じました。
今年度は伊藤先生のご指導の下、B4が5名のみのメンバーとなりましたが、少人数ですが非常に活気良く日々を過ごしております。
現在行っている研究は、光触媒、ホタテ貝殻、強誘電体を扱ったテーマとなっており、日々実験に励んでおります。
進路状況についてですが、今年も例年通り就職活動は困難なものとなっています。就職希望者の内半数以上は内定をもらうことができ、決まっていない学生も一生懸命に就職活動を頑張っています。B4は4名が就職希望、1名が大学院への進学希望となっています。
大学院は北大への進学となっていますので、今年に引き続き来年の研究室は少しさびしくなってしまうかもしれません。
伊藤先生は、例年と同様にご多忙な日々を過ごされています。教授会などの会議の参加、学部生や院生の講義、国際学会の発表の準備、共同実験の打ち合わせ、私たちへの指導など、忙しそうにされています。
最後になりましたが、卒業生の皆さんのご活躍、ご健勝を心より祈りつつ、日々の仕事などでお忙しい中、なかなか機会はないかもしれませんが、出張、旅行など大学の近くにお越しの際は、ぜひ研究室にお越しください。伊藤研究室一同、心より歓迎いたします。
(B4 奈良岡泰輝 記)
○微結晶材料研究室
卒業生の皆様、元気でご活躍のことと思います。本研究室では、平賀が酸化物系の微結晶粒材料の合成と超塑性を含む高温変形特性を、また、古瀬が透光性セラミックスの合成と物性値評価ならびにレーザー装置の開発を担当しています。材料科学の観点からみると、両テーマとも、陽イオンドープ、微粒子プロセシング、微細粒での高密度焼結を駆使して新しい特性を引き出すことが鍵となります。最終段階の焼結過程では、粒界偏析、応力下拡散、粒界すべり、結晶粒成長などの素過程が関与しており、その制御が重要です。このような共通の観点から、学内および外部機関・他大学との連携の下に研究を進めています。
今年度の研究室構成はスタッフ2名、4年生4名、大学院1年生2名、同2年生2名の計10名です。4年生は3名(石井、木村、小林)が就職内定、1名(梅津)が大学院進学、大学院2年生(印藤、近藤)も志望先への就職が内定し、それぞれ卒論・修論研究に励んでいます。また、大学院1年生(清水、高井)は新たな気持ちで勉学と実験に取り組むとともに、TAや学会での発表を経験中です。ご興味がございましたらぜひ研究室にお立ち寄り頂ければと存じます。
(平賀啓二郎 記)
○触媒機能材料研究室
卒業生の皆さんは、いかがお過ごしですか。本年度の無機物質工学研究室は、松田教授、大野准教授のスタッフ2名、大学院生1名、学部生6名の計9名と少数精鋭?で頑張っています。スタッフの近況としましては、高橋教授は退官され学長を、松田教授は精力的に研究活動を、続けておられます。また私大野も学会活動、自分の研究にと忙しい日々を過ごしております。学生の近況ですが、本年度は学部生を中心に就職状況が比較的良く、卒業研究テーマについてそれぞれ日々勤しんでおりますし、修士課程の学生は国際会議での発表など、研究活動を活発に行っております。
卒業生の皆さんも忙しいとは思いますが、機会がありましたら是非研究室にお立ち寄りください。お待ちしております。また、皆さんの住所や勤務地等変更がありましたら、メールで結構ですので、ご連絡頂けると幸いです。
E-mail: ohno@mail.kitami-it.ac.jp
(大野智也 記)
○機能界面材料研究室
平成26年度のメンバーはBS3名です。滝川1、山形1、茨城1です。今年も山田さんに技術部から来てもらっています。
有機ケイ素を用いた金属酸化物触媒の表面修飾の研究もいよいよ大詰めです。4年前の札幌でのTOCAT6に引き続き、6月、京都でのTOCAT7(第7回東京国際触媒コンファレンス)にて口頭発表をして来ました。また、10月山田さんは石油学会旭川大会にて発表しました。教育・研究生活も余すところ1年となりましたので、来年は海外に出かけて成果報告の予定です。
本年3月、触媒学会「教育賞」を多田旭男本学名誉教授、菊地英一早稲田大学名誉教授、瀬川幸一上智大学名誉教授、服部英北海道大学名誉教授の各先生とご一緒に受賞致しました。本賞は、触媒に関する教育および普及啓発を目的とする活動に顕著な貢献を果たした個人またはグループに授与されます。今回は「触媒化学に関する参考書の発刊による教育活動への貢献」が評価されました。大変名誉なことです。
卒研生は全員就職内定しました。技術セミナー、北の国触媒塾(最近は派遣していません)、文献ゼミ(今年で4回目の屈斜路研修所、帰りにサンゴ草を観賞)は例年通りです。今年もおもしろ科学実験(サッカーボール(フラーレン)を折り紙で作ろう)を担当しました。通算5回目のベテランです。また、屈斜路研修所へのオリゼミを復活させ、6月末に実施しました。屈斜路研修所にはネット環境、自販機や冷蔵庫、電子レンジ、などが整備され便利になっていますが、一方、卓球場は老朽化のため残念ながら今年取り壊されました。なお、夕食のメニューは変わりません。
近況などをお知らせ下さい。皆様の益々のご活躍をお祈りしています。E-mail: imizuyo@mail.kitami-it.ac.jp
(射水雄三 記)
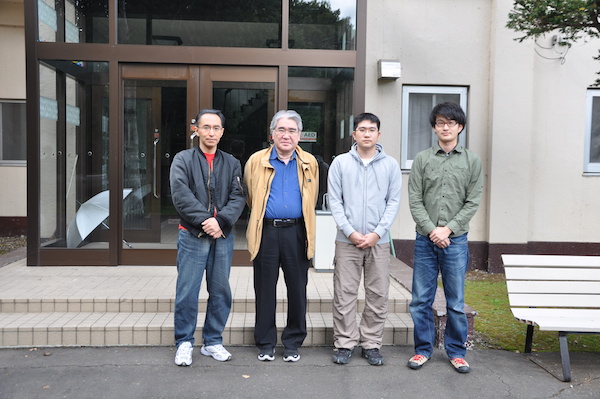
○材料分析研究室(宇都研究室)
今年3月大学院修了の梶原さんが凸版印刷(株)、菊池君は(株)原燃、松田君は菱栄テクニカ(株)に、学部卒業の小川さんが(株)ミネベア、竹中君が岡山県貨物運送(株)へ就職し、新しいスタートを切りました。
26年度は社会人ドクターの工藤君、M2の河島君、M1の姚さん、4年の近藤君、東山君、原田さん、望月君、山本君の8人が大腸菌と人工細胞膜を相手に頑張っています。相変わらず厳しい就職戦線ですが、ほぼ全員が進路を決めることができました。
今年5月と9月の分析化学会全国大会では前田君(H21年度修了)と会うことができました。福島の日本原子力研究開発機構に出向中で、研究成果を立派に発表していました。7月には岡山大勤務の藤尾君(16年度修了)がきれいな奥さんと可愛い子供連れで訪ねて来てくれました。卒業生の活躍や幸せそうな話題は大きな励みになります。
毎朝のミーティング、週に一度のまとめ報告も欠かさず続けています。やはり健康で踏ん張りのきく体力と規則正しい生活習慣が“ここぞ”というときに役立つと信じて。
卒業生の皆さんも体には気をつけて頑張ってください。近況報告をお待ちしています。
(宇都正幸 記)
○分析化学研究室(南研究室)
卒業生の皆さまにおかれましては、ますますご活躍のことと思います。
平成26年度の研究室メンバーの近況を、お知らせいたします。昨年度M2の久保君、小竹君、李さん、昨年度B4の泉君、鈴木君は、それぞれの就職先で4月から新たな挑戦をしています。加地君と菊地君は進学しました。
現M2の佐々木君、笹村君、常盤君、平野君は、就職活動の最中にも後輩に対する親切丁寧な指導を忘れず、自らの研究も強い目的意識を持って進めていて頼もしい限りです。現M1の加地君、菊地君、佐々木君、高野君は、新しい手法による研究を積極的に取り組んでいます。4年生の石原さん、押切君、笠島君、佐々木さん、谷尾君、中澤君は、進学希望3名と就職希望3名ともに、毎日朝から夕方遅くまで努力しています。
髙橋先生の定年退職(現在は学長)に伴い、今年度より坂上先生と一緒に研究をおこなっています。坂上先生はガスの専門家なので、まさに「坂上研究室」としてM2、M1、4年の計4名が、坂上先生のテーマで研究しています。
摩周湖調査、サハリン沖調査、バイカル湖調査、紋別沖実習、十勝沖実習と、今年も多くの調査と実習があり、全員で取り組んでいます。M1の人たちは初めての海外研究調査にも関わらず、活躍が光りました。調査を縫うように、多くの自治体との共同研究をおこなっています。非常勤職員の波岡さんには、実験および取りまとめ等でご協力いただいています。
今年も多くの卒業生修了生が顔を出してくれました(不在でお会いできなかった方も多数)。後輩に対する差し入れもいただきました(送ってくださった方もいました)。お礼申し上げます。
皆さまのますますのご発展とご健勝を、心よりお祈り申し上げます。
(南尚嗣 記)

写真1:研究室メンバーでの集合写真

写真2:国際会議でのM2佐々木君の口頭発表
共通講座
インターネットは確かに便利です。先日、薬を処方され薬局で受け取った際、牛乳、チーズ、ヨーグルトと一緒に摂らないように言われました。家へ帰ってインターネットで調べると、その薬はカルシウムなどと一緒に摂ると吸収が悪くなると書いてありました。もしインターネットがなかったら私は単純に言われた食品だけを避け、いつもどおりサプリメントのカルシウムを摂っていたことでしょう。
インターネットは確かに便利ですが、もちろん濫用、悪用されれば困った道具になります。昨年まで4年間勤めた前任校ではインターネットを使ったいわゆる「コピペ」が横行していました。特に長い書き物、例えば卒業論文の場合は大変です。良心的な教員は卒論の締め切り前の年の暮れから正月にかけて「コピペ」がないか徹底的に調べ、あれば学生に書き直すようにメールし、書き直されたものを読み直し、という作業に追われます。しかし中にはまったくそんなことは意に介さず、それどころか学生が書いたものをよく読みもせず、適当に単位を出す人もいます。おそらく日本全国にそのような教員の指導の下、学士だけでなく、修士、博士の学位を得てきた人がたくさんいることでしょう。
残念なことに最近「コピペ」は急速に「赤信号、皆で渡れば怖くない」式の市民権を獲得つつあります。授業で学生に宿題でレポートを書かせると、必ず何人かは当たり前のように「コピペ」をしてきます(なので私は北見工大ではレポートを宿題にしないようにしています)。先日世間を騒がせたように、某私立大学では「コピペ」で書かれた論文に博士号を出し、「コピペ」が発覚したあとも博士号を剥奪しませんでした。今の学生は自分で考える力がなくなった代わりにインターネットを使う能力に長けているのだと、前向きに考える人もいます。その内論文・レポートの全文字数の半分未満であれば「コピペ」可という規定を設け、時代の最先端を行こうとする大学がきっと出てくると思います。冗談ですが。
(木村章男 記)
マネジメント工学コース
○各学科共通マネジメント工学コース
マネジメント工学コースの4年生が配属されている研究室のうち、ここでは共通講座、社会連携推進センターの研究室便りをお届けします。各学科の研究室と情報処理・機器分析両センターの研究室については、それぞれ関連学科の研究室便りで近況をお伝えしていますのでそちらをご覧ください。
本コースからは今年卒業研究を終えた12人を含め、これまで3期に亘り合計37人の学生が14の研究室から巣立っていきました。機械工学科冨士・渡辺・ウラ3教員の研究室、社会環境工学科大島・川村(彰)・高橋(清)・渡邊・白川・中山6教員の研究室、情報システム工学科桝井・前田・原田3教員の研究室、共通講座の山田教員の研究室、そして社会連携推進センター教員の産学官連携価値創造研究室です。
今年のコース4年生は17人です。配属先は、社会環境工学科の川村(彰)研究室・中山研究室、情報システム工学科の桝井研究室・後藤研究室、情報処理センターの升井研究室、マテリアル工学科の南研究室、共通講座の照井研究室そして社会連携推進センターの産学官連携価値創造研究室です。そこで今回は、これまでにコース学生が配属になっている共通講座の山田・照井両研究室と社会連携推進センターの産学官連携価値創造研究室からの便りをお送りします。
(鞘師守 記)
○社会連携推進センター 産学官連携価値創造研究室(CVR)
社会連携推進センターのCVRも、平成23年にマネジメント工学コース学生の第1期生が配属されて以来、今年で4年目を迎えています。研究室同窓生は、1期生6人、2期生5人、今年の3期生4人を合わせて15人になりました。3期生の就職先・赴任地は北見・札幌・名古屋です。
研究室には今年、機械工学科・社会環境工学科・電気電子工学科・バイオ環境化学科・マテリアル工学科の5学科から大挙9人の学生が配属となりました。マネジメント工学プロジェクトでは、6次産業やスポーツなどによる地域振興、学生によるベンチャー企業、学生による小学生への理科教育、大学の特色有る研究施設の活用、さらには留学生の交流活動などのテーマが取り上げられています。オープンキャンパスでのコース説明や学園祭での3年生を巻き込んだコースプロモーション、近隣市町村で開かれる様々なイベントへの貢献などはすっかり定着してきています。特に学外に出掛けての諸活動は年々忙しさを増してきています。指導にあたっている有田・内島・鞘師の3人も、相変わらず学生と一体となって奮闘中です。
(鞘師守 記)

4/22-23屈斜路研修所でのオリエンテーションゼミ(H26CVR研)

屈斜路研修所オリエンテーションゼミの後、砂湯にて
○共通講座 山田研究室
山田研究室卒業生のみなさん、お元気ですか?といっても当研究室卒業生は相変わらず1期生のおふたりのみ、その後新しい学生はまだきてくれていないので、研究室の動向としては特に変化なく、マネジメント工学コースに対する当研究室の貢献も3年生の授業のみ、というのがここ何年かの様子です。みなさんのときには3年生の授業も、(配属希望者がいた場合の)卒業研究にどう結びつけるか試行錯誤しながら行っていましたが、このごろは難しいことを考えず、受講者にとって有益なテーマをそれぞれに探してもらって、それぞれに掘り下げ、発表してもらうという形ですっかり定着しています。去年も書いたと思いますが、みなさんのときと同様、マネジメント工学コースには意欲的かつ個性的な学生が多いので、こちらもおおいに楽しんで授業をしています。最後になりましたが、お体に気をつけてお過ごしください。気が向いたら近況を知らせてくれるとうれしいです。
(山田健二 記)
○共通講座 照井研究室
今年度のマネジメント工学プロジェクトでは、照井研究室に2名の卒研生が所属しています。
卒研のテーマの一つは、現代日本における芸術マネジメント、とりわけ美術の領域におけるマネジメントを対象としたもので、具体的には、現代のさまざまな美術館の状況を踏まえながら、マネジメントに関わる美術館の学芸員の仕事の内容、日本におけるその実態、といったものを、日本の公共的芸術文化政策の状況をも視野において、展開するものになっています。
もう一つのテーマは、フィルムを用いる、いわゆる「銀塩写真」の実質的な衰退をもたらしつつ、近年、めざましい発展を遂げたデジタル写真の状況について、社会的な背景や、光学上の技術的側面等を対象として、研究するものです。
いずれも、多くの資料を限られた時間のなかで読みこなさなければならず、工学部の卒研とは、かなり異質なものですが、両名とも、卒論の完成をめざして努力している最中です。
(照井日出喜 記)
機器分析センター
卒業生の皆様、元気に頑張っていますか?悪い女性に騙されていたりしていませんか?まずは研究室の近況をお伝えしますね。今年度の研究室メンバーは、4年生が4名、M1が2名、M2が2名という構成なのですが、なんと、4年生のうち3名は女子学生です。そのため、これまではお下品な会話が多い研究室でしたが、今年度はとってもさわやかな雰囲気の研究室に生まれ変わって(いや、猫をかぶって)おります。会話内容は多少変わりましたが、実験研究の様子は相変わらずです。メンバーは、日々、研磨して、処理して、測定して、育てて、数えて・・を繰り返しています。細胞培養と菌培養実験は、最近、研究室内で順調にまわっています。この実験に関わっていた卒業生たちにとっても感謝しています。ありがとう。3月の学会に合わせて、東京にて現役&卒業生飲み会を企画しております。都合が合えば、是非来てくださいな。
(大津直史 記)

女子学生が増えてしまった最近の様子