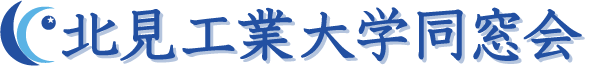母校だより 2013(平成25年度)
- 会誌発行に寄せて 学長(名誉会長) 鮎田 耕一
- 会誌の発行に寄せ 会長 谷 浩二
- 定年退職を迎えるに当たって
- 北見工大での34年間を振り返って 理事・副学長(マテリアル工学科(兼務)) 高橋 信夫
- 北見工業大学での25年間を振り返って 理事・副学長(機械工学科(兼務)) 田牧 純一
- メタンハイドレート研究のスタート 環境・エネルギー研究推進センター(社会環境工学科(兼務)) 庄子 仁
- 小さな大学の大きな利点 社会環境工学科 高橋 修平
- 定年退職に思うこと 社会環境工学科 後藤 隆司
- 10年を振り返って バイオ環境化学科 青山 政和
会誌発行に寄せて
北見工業大学学長(同窓会名誉会長) 鮎田 耕一
同窓会の皆様方におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
平成22年度から始まりました北見工業大学創立50周年記念基金には、多数の同窓生の皆様にご寄付をいただき誠にありがとうございます。また、KITげんき会事業を通して、大学院学生奨学金や語学研修助成、大学広報等へのご支援をいただき重ねて御礼申し上げます。さらに、同窓生の皆様のご尽力のおかげで、大卒就職率が6割程度にとどまる厳しい状況のなか本学は9割以上の高い就職率を保っています。このように、本学の活動には同窓生の皆様の日頃のご協力、ご支援が欠かせないものとなっております。この場をお借りして心から感謝申し上げます。
さて皆様に、本学のここ一年の主な動きをご紹介したいと思います。
昨年8月、本学を含む研究チームが網走沖でメタンハイドレートを採取したとの報道を目にした方もおられると思います。メタンハイドレート等の未利用エネルギー研究は本学が以前から力を入れてきた分野で、化石燃料や原子力に代わるエネルギーの研究開発が脚光を浴びる中、重要度がますます高くなってきております。
また昨年10月、社会連携推進センター(旧:地域共同研究センター)が創立20周年を迎え、記念式典や、ノーベル化学賞を受賞した鈴木章北海道大学名誉教授を招いて記念講演会を行いました。
本学学部の入学志願倍率は国立大学の中で常にトップテンに入る高い人気を誇っており、今年の入試においても7位にランクインしました。本州各県の国立大学の学生が自県出身者で占められているのと比べ、本学は道内出身と道外出身の学生がほぼ半分ずついます。引き続き全国の学生にとって魅力であるよう、良き仲間と出会いじっくり勉強に打ち込める環境の充実に努めて参ります。
昨年、学長に再任された際、2期目は地域貢献に最大の力点を置きたいと話しました。昨年連携協定を結んだ北見市教育委員会とは、小学生がものづくりの楽しさを体験する「冬休み親子工作教室」や、小学校教諭の理科実験技術向上のための「理科実験研修」を実施しました。また今年3月、陽気堂クリエート工業株式会社及び北見市と太陽光発電事業推進に関する協定、東京農業大学生物産業学部、日本赤十字社北海道看護大学、網走開発建設部との間で、オホーツク地域活力支援包括連携協力協定を締結しました。これらの協定により、北見が新エネルギー・省エネルギーのまちとして活性化することや、医農工の大学と行政機関が連携した効果的な地域支援の推進につながることを期待しています。
さて私事ではありますが、平成26年3月をもって学長としての6年の任期を終了します。同時に、45年にわたる大学人生に一つの区切りをつけることになります。私が北見工業大学に着任したのは、本学が4年制大学に昇格した3年後の昭和44年で、第1期生が4年次に進級した年でした。あれから早40数年、短期大学としてスタートした本学が大学院博士課程を備えるまでになり、また国際化が進みつつある中で、100人を超える留学生が本学で学ぶようになりました。また、設立当初には一つの建物しかなかった本学が、学科棟、付属図書館、大学会館、講堂、情報処理センター等の各センター、総合研究棟等の新設とともに設備面でも見ちがえるほど充実してきました。教員及び学長として本学の発展に寄与することができたのは私の誇りであり、平成22年、創立50周年の節目を学長として迎えられたことは大学人生の中で一番のハイライトと言っても過言ではありません。
しかし何といっても私の一番の誇りは、教員として、そして学長として社会に送り出してきた卒業生の皆さんです。同窓会名誉会長として同窓会総会や各支部の会合に顔を出させていただきましたが、共通して感じることは、同窓会員の皆様方の本学への並々ならぬ熱意と愛情でした。皆様方のご協力がなければ学長及び同窓会名誉会長の職務を全うすることはできなかったでしょう。これからも様々な場面で同窓生の皆様のご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げますとともに、皆様のご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げます。
会誌の発行に寄せ
同窓会長(昭和53年機械工学科卒業) 谷 浩二
同窓会会員の皆様方には、益々ご健勝でご活躍のことと心からお慶び申し上げます。
私は、今年6月8日に開催されました同窓会総会において、小田桐前会長の後任として、同窓会長に選任されました谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、世界の経済を見ますと、まだまだ不況が続き出口の見えない状況となっています。また国内を見ますと、東日本大震災からの東北地方の復興も、具体的な復興計画が発表されず、この先のビジョンが見えない状況が続いています。さらに福島第一原子力発電所では汚染水漏れが続き、確実な汚染水の封じ込め対策による、汚染水の海への流出防止が求められ、福島原子力発電所の廃炉へ向けた日本の取組みを、世界が注目している状況です。
自然界を見てみますと、毎年各地で局所的なゲリラ豪雨による水害、竜巻による災害が発生するようになり、地球温暖化による気候変動の問題が大きく取り上げられています。
さて、暗い話題ばかりではなく、9月8日には日本国民が待ち望んでいた、2020年東京オリンピック開催が決定され、日本に明るい目標が掲げられました。
東京オリンピック開催までには、東北地方の復興計画が完成し、計画に沿って津波災害に強い、新しい東北の街が出来上がり、今までにない街の景観になることと思います。また、福島第一原子力発電所で行われている廃炉作業も、現在発生している色々な問題が解決され、さらに今後発生する問題の予測が立てられ、汚染水の確実な封じ込め、放射能の分離除去が進むことにより、発電所周辺の放射線量が下がりより安全に廃炉作業が進む状況になっていることと思います。
地球温暖化に対応するため、国を挙げて脱炭素社会の推進により、自然エネルギーの採用、化石燃料使用量の削減、二酸化炭素の吸着・貯留技術等の開発・実用化が進められています。
このような明るい未来を創っていくのは、技術立国日本を背負って立つ、北見工業大学の同窓生の皆様だと思っています。
さて同窓会活動を見てますと、各支部は同窓会活動活性化のため、同窓生の参加率向上を目標にして、各支部の特色を生かした活動を展開していますが、なかなか参加率の向上につながらない状況が続いています。
また、新規加入の卒業生はというと、ここ数年卒業生の同窓会加入率の低下が続き、さらに卒業後の連絡先不明者が増えています。
つまり、各支部が把握している同窓生数が、卒業生の増加に比例していない状況となっています。支部活動に参加する同窓生の年齢は高齢化が進み、若い同窓生の積極的な参加が要望されています。
これからは若い同窓生が積極的に支部活動に参加し、支部活動の運営に携わっていただくために、若い同窓生が支部活動に積極的に参加する支部活動の在り方、若い同窓生にとって魅力ある同窓会活動とは、との問いかけを行い、支部活動の活性化、同窓会活動の活性化を図っていきたいと思います。
若い同窓生が支部活動に、支部運営に加わることにより、マンネリ化した支部活動も活性化していくことと思います。
支部活動が活性化し、同窓会活動が活性化することにより、同窓生の連携の取れた力強い同窓会となります。
同窓生皆様の知恵と行動力を結集して、北見工業大学の最大の応援団として大学とともに同窓会も大きく成長していきたいと思います。
最後に同窓生皆様のご健勝とご活躍をご祈念申し上げます。
<定年退職を迎えるに当たって>北見工大での34年間を振り返って
理事・副学長(マテリアル工学科(兼務)) 高橋 信夫
ありきたりの表現で申し訳ありませんが、まさに「光陰矢の如し」の想いです。昭和54年6月末に、現在の女満別空港ではなくその前の古い空港に、東京から3時間ぐらいの時間をかけて着きました。飛行機はYS-11型機でした。北海道は、それまでに一度訪れたことがあっただけで、親戚がいるわけでもなく、全く新しい生活の始まりでした。
7月1日に、当時の学長の小池東一郎先生から、「工業化学科勤務を命ずる」の辞令をいただき、北見工業大学の一員としての生活を始めることになりました。工業化学科では小林正義先生の研究室に属し、私の部屋は、現在のバイオ環境化学科1号棟の4階で螺旋階段のそばにありました。
北見では、研究課題として、「ゼオライトに担持したロジウム種の触媒作用」に関する研究を始めました。理由は簡単で、装置的にやれることが限られたことと、消耗品の面で前任地の東工大の研究室からの支援を得ることができたからです。ただ、実験的にはとんでもなく効率の悪いもので、2時間おきにサンプリングが長時間にわたって必要となる、ひたすら体力が要求される実験でした。一緒に取り組んでくれた学生が頑張ってくれたことは、嬉しかったです。しかし、若いとはいえ、学生に徹夜の連続をさせることは無理なことで、私も時には、徹夜で実験をしました。しかし、ついついソファーで寝入ってしまい測定に穴があくこともありました。そんな中で、嬉しかったことは、私の実験には関係のない他の研究をやっている学生達が、代わりにサンプリングしてくれたことです。このような、優しくそして元気の良い卒研生たちとの協働作業は、今も楽しい思い出として残っています。助手の見陣さんにもいろいろとお世話になりました。その後、工業化学科の生活は、平成4年度まで13年間続きました。その間、学科の先生方及び事務の方々にいろいろとお世話になりました。この紙面をお借りして、工業化学科時代の教職員の皆様及び卒業生の皆様に感謝の意を伝えさせていただきたいと思います。
平成5年度に、工学部が改組され学科組織が大きく変わることとなりました。工業化学科と環境工学科が一緒になって化学システム工学科(学生定員60人)になるとともに、機能材料工学科(50人)が新設されることとなりました。この改組は、H4年度当時の平林学長、厚谷学生部長、佐々木克孝電子工学科教授をはじめ当時の執行部及び事務局の方々のご尽力があって実現したものです。この機に、私は幸いにも機能材料工学科教授に昇任させていただきました。平成7年度には、松田先生と坂上先生が加わり、研究体制も整備されました。平成9年度には、これまでの触媒研究に加えて、当時の厚谷学長の勧めもあり、「ガスハイドレート」に関する研究に関与することとなり、その後、社会環境工学科教授の庄子仁先生のご尽力があり、「未利用エネルギー研究センター」の設置につながりました。
機能材料工学科(H20年度にマテリアル工学科に名称変更)には、定年までの21年の間お世話になることになりました。その間、H9-10年度の技術部長から始まり、その後いくつかの役職を務めさせていただき、最後の6年間は理事・副学長として、鮎田学長のもとで仕事をさせていただきました。その間、教職員の皆様には、大変お世話になり、感謝申し上げます。また、いろいろとご迷惑をおかけした事と想います。お詫び申し上げます。特にマテリアル工学科の先生方には、小さい学科で教員数がただでさえ少ないところ、そのうちの一人を欠くような状況が続き、多大なご迷惑をおかけしました。中でも、松田・坂上両先生には、言葉では言い尽くせないほどお世話になりましたし、また、ご迷惑をおかけしました。改めて、感謝申し上げます。学生の皆さんにも、教員室を不在にすることが多く、十分な指導ができなかったことをお詫びしたいと思います。
最後になりますが、教職員そして同窓生の皆様が一丸となって力を合わせ、北見工大の発展に貢献されますことを心から願っております。そして、皆様のご健勝と益々のご発展を心から祈念し、私の退職の挨拶とさせていただきます。本当に、有難うございました。
<定年退職を迎えるに当たって>北見工業大学での25年間を振り返って
理事・副学長(機械工学科(兼務)) 田牧 純一
私は平成元年4月1日に機械工学科助教授として赴任しました。前任地での大学教員経験年数は16年ですから、大学教員としての人生41年の6割をこの地で過ごしたことになります。配属研究室は切削工具の摩耗に関する研究を活発に行われていた北川武揚教授が所掌する機械加工学講座で、久保明彦助手(現在助教)と杉野豪技官(現在技術員)が研究室スタッフとしてすでに活躍なされておられました。したがって、赴任当初から充実した研究スタッフに恵まれており、研究環境を迅速に立ち上げることができたのは私にとって大変幸せでした。平成11年に北川教授が定年ご退職なされた後も、久保助教、杉野技術員とも引き続き現在の研究室(マイクロナノ加工学研究室)の運営と教育研究活動を支援していただいており、お二人には深く感謝申し上げます。
さて、大学教員の最も重要な業務は授業に代表される教育です。私の前任者は前川克廣助教授(現在茨城大学工学部教授)でしたので、その後任として「材料物性」、北川教授の後任として「生産工学」の2科目を担当しました。いずれの科目とも私の研究専門分野とは異なる領域でしたので、講義内容の自学自習とテキストの作成、学生への授業を平行して行うという自転車操業の日々でした。また、知り得た知識の全てを学生に教授したいという意気込みだけが強く、学生にとっては悪い教師であっただろうと反省しています。退職を間近に迎えた最近になって授業のコツが少しは解ってきたのかなという感もありますが「時既に遅し」です。ただし、材料物性や生産工学を自学したことはその後の教育・研究活動に大きく役立ちました。生産工学の知識はウラ准教授が現在担当なされている科目である「CAD・CAM」の教育設備として結実し、材料物性の知識は私の研究専門分野である精密加工を半導体材料や光学ガラスのマイクロナノ加工に展開する動機となりました。
大学教員のもう一つの重要な業務である研究については、先も述べたように、新任教員としては恵まれた人的環境にありましたが、研究環境を構築するためにはそれなりの財政的基盤が必要です。赴任当時は工具研削盤の主軸にインバータを取付け、手動テーブルをDCサーボモータ駆動に改造することによってダイヤモンド研削ホイール搭載の正面研削盤に改造しました。その後、学内経費による平面研削盤(現在はエアスピンドル搭載研削盤に改造)の導入、文部科学省大型設備費による小径内面研削盤の導入に至っています。
さて、大学教員としての職を終える際に誰もが思うことは「研究者として社会に貢献できただろうか」ということではないでしょうか。研究成果の社会貢献を評価する指標は多様であり、評価すること自体が意味を持たないのですが、私が本学に赴任した際、私の胸のうちに秘めた研究目標は、前任地の学位指導教員である松井正己教授(現在東北大学名誉教授)の生涯研究論文数(112件)を超えることでした。本学研究スタッフの他、二俣正美教授(現在北見工業大学名誉教授)、井山俊郎岩手大学工学部教授、閻紀旺准教授(現在慶応義塾大学理工学部教授)、ウラシャリフ准教授のご支援のもと、9月16日時点で129件、国際会議プロシーディングス、解説記事等を含むと176件の文献数を達成することができ、自己満足しています。このような研究環境を与えていただいた北見工業大学に感謝いたします。
最後に感謝申し上げたいのは、常本秀幸前学長、鮎田耕一現学長の下で、技術部長、副学長あるいは理事としての職務を任されたことでございます。これらの職務を通じて国の高等教育機関としての大学、国立大学法人の一員としての北見工業大学を俯瞰できたことは私にとって意義深いものでありましたが、特に、職務を通じて多くの教員・職員の方々を知り得たことは私の一生の財産となりました。北見工業大学の益々の発展を祈念しております。
<定年退職を迎えるに当たって>メタンハイドレート研究のスタート
環境・エネルギー研究推進センター(社会環境工学科(兼務)) 庄子 仁
私は、もうじき定年退職いたします。これまで色々お世話になり、本当にありがとうございました。これまでの生活を少し振り返らせて頂きます。
私は、札幌で生まれ札幌で育ちました。南極の深層氷コアを用いた力学解析で学位(北海道大学)を頂いたのですが職が無く、アメリカ(バッファロー)に渡ってNY州立大学の研究助手(のちの研究助教授・准教授)になりました。アメリカには9年居りました。グラントの切れ目を恐れていつもヒヤヒヤでした。プロジェクト(GISP)はアメリカ(コア物理・化学・力学解析)、デンマーク(コア掘削・同位体解析)およびスイス(ガス解析)による国際協力でした。これは、最初の本格的な深層コア研究として、いまも世界中のお手本です。渡米中は、ありとあらゆる恥ずかしい失敗の連続でした。1981年のグリーンランドフィールド調査中に、世界で初めて空気ハイドレートを発見できたことは稀な幸運でした。1987年に富山大学の助教授に採用され、帰国できました。
1993年に教授に採用され、北見工業大学に移りました。土木開発工学科が担当する全学教養物理学チームのメンバーです。帰国後も研究は、グリーンランドと南極のコア解析を続けました。フィールド調査はグリーンランド深層コアばかりでなく、富山では南極バード基地浅層コアに、北見に来てからは日本の南極越冬隊員としてドームF基地の建設作業にも参加しました。
2001年に、私にとって大きな変化がありました。当時北見工業大学では、改組・新設・建設ラッシュが進んでおりました。確か2月頃だと思いますが、当時の厚谷学長から電話を貰いました。「今度、本学に未利用エネルギー研究センターができて、メタンハイドレート研究を進めることになった(学長)」「それはおめでとうございます(私)」「何を言っている。君がやるんだよ(学長)」。まさに青天の霹靂でした。悩みは、「いまここでハイドレートをやるなら、深層コアはもうできない。でもハイドレートは、新しいチャレンジである」です。結局、センター教員学内公募に応募し、それが認められてセンターに移りました。
新設されたセンターのスタートには、世界の研究所の創設例を手本にしました。先ず、一流の先生を探しました。ロシア(サンクト・ペテルブルグの海洋鉱物資源研究所)で見つけた先生(V.ソロビエフ博士)に教えられて、サハリン沖の浅層ハイドレート調査を始めました。調査船を管理している太平洋海洋学研究所(A.オブジロフ教授;ウラジオストク)と物理探査の海洋学研究所(B.バラノフ博士;モスクワ)を仲間に引き入れました。韓国の局地研究所(Y.キム博士;インチョン;物理探査)も加わりました。運よく科研費申請が採択されて、調査1回分の傭船料が手に入りました。大学の骨折りで概算要求(2件)が認められ、センター整備と長期調査の経費確保ができました。センター教員は私と八久保先生でしたが、二人とも物理系です。化学系強化のためにマテリアル工学科の高橋先生、南先生、坂上先生に加わって頂きました。堆積物には、社会環境工学科の山下先生に加わって頂きました。こうして、ガス・水・堆積物の3要素相関解析のための基礎ができました。技術部支援と学生(社会環境工学科兼務)も手に入りました。
厚谷学長の紹介で、バイカル湖の陸水学研究所(M.グラチェフ博士;イルクーツク)とも共同研究がスタートしました。泥火山(表層ハイドレートの有力候補地)のエキスパートであるベルギー・ゲント大学(Mデバティスト教授)にも参加して頂きました。
サハリン沖とバイカル湖で、過去12年間に新たに発見したメタンハイドレートの生成地点は、計40箇所を超えています。北海道沖調査もスタートしました。
大学の目的は、教育・研究・社会貢献であるといわれます。より一層の研究を目指して学内改組が行われ、未利用エネルギー研究センターは、環境・エネルギー研究推進センターに変わりました。さらに最近は、研究活動が教育に与える効果を重視した改組が検討されているそうです。進歩は絶え間ない改組であり、それはWork Hardの連続なのでしょう。これからの皆様のWork Hardに期待いたします。
<定年退職を迎えるに当たって>小さな大学の大きな利点
社会環境工学科 高橋 修平
自分では若いと思っていたのに、いつのまにか定年が近づきました。私が北見工大に赴任したのは1979年(昭和54年)4月、一般教養等・自然系の物理学教官としてでした。当時の学科は1学年学生数40人の小学科制であり、8学科目の応用機械工学科が出来たために私の採用枠ができたのでした。
講義は2学科を受け持ち、週6回の講義、さらに物理学実験も受け持ち、学生の実験レポートノートのチェックもし、レポートには必ず一言書くようにしました。すると次第に交換ノートのようになり、40冊のノートを家に持ち帰って付けたものです。そのことは今も生きていて、力学講義の演習でも学生のコメントには必ず返事をつけるようにしています。
当時、学生とは年齢が近いせいもありよく遊びました。授業でクラスに行くと「ソフトボールをしたい」と黒板に大書きしてあり。「では、しよう!」と言うと大歓声が上がりました。当時のオリゼミは学生が企画することになっていて、担任の他に必ず呼ばれ、屈斜路湖のオリゼミに毎年2回行ったものです。
1981年11月から第23次日本南極地域観測隊に参加することになりました。1年前に物理の上司である大野先生に、恐る恐る申し出ると、「いいよ、いいよ、行っておいで。講義は皆で面倒見るから」と言われ、大変ありがたいことでした。当時は、まだ南極観測が珍しく、色々なグループが壮行会を催してくれました。うれしかったのは、教えていた機械工学科、応用機械工学科の1年生がそれぞれに壮行会をしてくれ、胴上げは飲み屋の天井までぶつかるほど高くはね上げられました。その時にプレゼントされたピッケルとサバイバルナイフは今でも大切に持っています。
南極では昭和基地ではなく、標高2200mにある「みずほ基地」で越冬しました。暖かい建物は6坪の部屋が3つだけ、越冬の前半は5人、後半は3人だけの小さな基地でした。1年通してみずほ基地にいたのは私だけで、毎日、地吹雪、積雪量、気象の観測を行い、とくに地吹雪観測は、その後の吹雪研究の貴重なデータとなりました。
南極観測から戻り、物理講義で必ず一回は南極の話をしました。私の授業を受けたという山下先生に「先生の受けた講義で南極の話はよく覚えています。でも物理のことは覚えていません」と言われ、そういうものからと思いました。
その後、ヒマラヤの氷河、シベリアの氷河、アラスカの氷河など各地の氷河観測をし、氷河熱収支や地球環境変動等の研究をしました。とくにシベリアの氷河は、最近、北極温暖化に伴い、政府指導の北極観測研究に組み入れられ、北見工大からも何人も研究者が参加しています。
1993年に物理教官は土木開発工学科(現社会環境工学科)に所属することになり、卒論生を持つことになりました。学生さんがいると研究も進みましたし、それぞれの個性が面白く、山登りも一緒に楽しみました。今年も雌阿寒岳、羅臼岳に登りました。
最近は学部講義として力学基礎、雪氷学を教えています。「毎回の授業が楽しい」、「物理が好きになりました」、「新しい知見を得ました」等という学生からの言葉が何よりうれしいものです。
私の専門は、雪や氷のことを研究する雪氷学です。寒冷地域にあり、観測場所が身近にある北見工大の特色ということで、周囲の方々のご理解を頂き、雪氷研究者が次々に増え、南極観測に行く人も何人も出て、身近な雪氷現象から雪氷災害、地球環境問題まで研究範囲も拡がりました。また今年は雪氷学会・雪工学会の全国大会である雪氷研究大会(2013・北見)が北見工大で開催され、盛会のうちに終えられたのもありがたいことでした。
2006~2010年には地域共同研究センター(現社会連携推進センター)長として工業・農業の連携教育など様々な活動をしました。鞘師先生、有田先生、内島さん等センターメンバーと楽しく社会連携活動ができました。帯畜大、網走の東農大生物生産学部の方々と合宿を行ったのもいい想い出です。
北見工大は小さな大学ですが、おかげで他学科の多くの先生と顔見知りになり、学科を超えた研究グループを組むことができました。職員の方ともサイエンスキャンプ等、いろいろな活動ができました。北見工大の特長である教員・職員の交流が盛んな「小さな大学の大きな利点」をこれからも生かして欲しいと思います。
<定年退職を迎えるに当たって>定年退職に思うこと
社会環境工学科 後藤 隆司
あと半年あまりで定年退職、毎日が日曜日の生活が始まります。その中でたった一つ決まっていることは、誕生日(6月20日)はセントアンドリュースにいることだけです。昭和50年(1975年)4月、27才の時、本学に勤め始めました。それから38年間いろいろなことがありましたが、楽しい38年間でした。卒業生の皆さんへということですので、最近、考えていることをいくつか書きたいと思います。
校舎については、開学以来一番整備されています。昔では考えられないくらいの設備が教室には整っていて、全てではありませんが冷房設備があります。コンピュータの講義室では、一人一台の端末が使えます。
プログラミングという科目を通して学生の変化について書きます。
プログラミングを講義からはずした学科もありますが、開発、土木開発、社会環境と名称は変わりましたが、ずーっと続いてきました。私も含めて自分でプログラムを作ることは、将来ないかもしれません。しかし、この科目が存在してきたのは、解決手順を見つける方法を学んで貰いたかったからです。自分で作ったプログラムが正常に作動し、答えが求められる。それを達成した学生は「よっし!」とか声に出します。その瞬間が、この科目の目的が達成された瞬間なのです。その後は、放っておいてもどんどん問題を解いていきます。
学生がどう変わったかの前に、教師がどう変わったかというと森(訓)先生、後藤、中村先生と3代にわたります。その間、支え続けてくれたのは平松技官です。私と平松技官は全期間担当してました。最初にプログラミングを教えたのは、着任の年、1975年でした。正式な科目になっていませんでしたので、希望者だけを実験室で教えました。当時の環境は、大学にコンピュータが1台、カードパンチ機が数台でした。これを読んでいる卒業生の中には「そうだった」と視点を少し上に向け、遠い昔を懐かしむ表情になっている人もいると思います。自分で作ったプログラムをコーディングシートに書き、それをカードにパンチして、電子計算機センターにコントロールカードを付けて提出します。翌日、ラインプリンタの出力が返還される仕組みでした。出てきた結果は、パンチミスは文法ミスでした。ミスを修正して再提出。何度かこの手順を経て、結果を得ることができたのです。確か、最初の問題は、素数を求めるものだったと思います。こんなに苦労して求めた結果ですから、感動も大きかったのでしょう。感動こそが学ぶ喜びであり、深く記憶に残るのです。今の学生は、物心ついた時にはテレビゲームがあり、カラーのきれいな画面が当たり前の時代を生きています。面倒なプログラムを作って、求めた結果が、モノクロの画面に数字だけというのは、感動せよと言っても無理なのかもしれません。
設備はコンピュータの発達もあり、年々右肩上がりで良くなってきました。では学生はどう変わったかの結論ですが、残念なことに右肩下がりで悪くなってきています。これはこの科目の最終目標が年々低くなってきていることから分かります。設備が良くなっているのに、成績は悪くなっている。この結果は、学生の考える力の低下に原因があります。学力低下の問題はそれ自体、大学が考えていくべき大きな問題です。しかし、その他に理解よりも暗記の考え方が原因のように思います。暗記が一番ふさわしくないプログラミングだからこそ結果がはっきり出たのでしょう。理解から感動への道筋ができにくくなっています。昔は結構多くの学生が感動を経験したはずなのに、今はごく少数になってしまいました。これから先、ますます困難な時代になることが予想されます。最後に、解決策を提示できない自分への反省を込めて若い先生方に希望を書きます。学生が授業や研究で感動を経験できる大学にして下さい。
大学の皆さま、卒業生の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。
<定年退職を迎えるに当たって>10年を振り返って
バイオ環境化学科 青山 政和
平成16年1月に化学システム工学科に教授として赴任して10年と数ヶ月、平成26年3月で定年を迎えることになりました。赴任して2週間後、1月14日の未明から根室の海上に停滞した低気圧による記録的な豪雪で、JR石北線はもとより国道39号線も数日間不通となり、大学構内も背丈をはるかに超える積雪となったことを今でも鮮明に記憶しています。この時ばかりは旭川に長らく住居を構え、ドカ雪になれている私でも大変驚き、除雪が追い付かない大学構内と東陵町宿舎の間を腰まで雪に埋もれながら往復しました。赴任直後の豪雪が前触れでもなかったのでしょうが、私が勤務した10年は北見工大においてもまさに激動の10年、大きな組織改正が断行されました。
平成16年4月には国立大学が独立法人化され、身分も、所謂、国家公務員ではなくなり、さらに本学においては全国の国立大学に先駆け、教員の任期制が導入されました。今から考えれば再任要件はさして高いハードルでもなかったのですが、申請に当たり一抹の戸惑いもありました。
平成20年4月には化学システム工学科はバイオ環境化学科に改組され、学生募集もバイオ・マテリアル系の系列入試となりました。とりわけバイオ環境化学科は、それまでの化学システム工学科とは名実ともに大きく様変わりしました。カリキュラム編成に際しては、量子化学などの科目が削除され、食品系の講義が新たに加わりましたが、工学部の化学系としてこのようなカリキュラムで良いのかどうか、学科教員会議で大いに議論されました。当時の学科長や教務委員の先生方が取りまとめに大変ご苦労されていたことを思い出しています。本学が農村地帯の工学部であり、地元に大規模製造業と言う受け皿がない地域性や、少子化にともなう女子学生の取り込みなどを意識し、食品科学分野の2つ研究室を新設し、バイオテクノロジーや環境科学関連の講義も充実されました。このことは、当時の化学システム工学科が置かれている状況を考えれば誤った判断ではなかったように思います。しかしその一方で、食品分野の研究室の新設や食品関連科目の開講が、新規増設ではなくスクラップアンドビルドに留まったために、理論化学や分析化学分野の研究室の枠を振替ざるを得ず、まさに学科として苦渋の決断でした。
初年度には4名の卒業研究着手者が配属され、木質廃材や炭化物を用いた内分泌攪乱物質や有害重金属類の除去、食用きのこに含まれる血圧上昇抑制成分に関する研究に取り組みました。平成18年から、新進気鋭の斉藤伸吾先生(現埼玉大学工学部准教授)が星座先生の退職に伴い私の研究室に新たに加わり、金属類の蛍光分析などの研究課題にも取り組むようになりました。翌年、斉藤先生が埼玉大学にご栄転されましたが、その後数年間は研究室の大学院生を研究指導して頂き、Journal of Chromatography、The Analyst、Electrophorensisなどレベルの高い専門誌に研究成果を発表することができました。中谷先生(環境高分子化学研究室)や服部先生(生体高分子化学研究室)と共同で取り組んでいる樹木精油を用いた発泡スチレン減容化の課題についても、担当学生の頑張りの結果、Journal of Environmental Science and Health、Environmental Chemistry Letters、Advances in Polymer Technology、Journal of Wood Scienceなどの専門誌に研究成果を発表しています。その研究成果の一部を特許出願したのですが、出願の数カ月前の精油およびテルペン討論会に共同研究者が発表した要旨が公知の事実とみなされ、拒絶通知を受け取ることになりました。この学会の発表要旨は3項、少し詳しい内容になることをうかつにも忘れていた私の大失態です。これに懲りて、ビートパルプから選択的にアラビノースを水解分離する研究については、出願まで研究発表を差し控えたので、未だ拒絶通知は受け取っていません。
平成20年には、前任地(道立林産試験場)での勤務以来、長らく中断していた私のライフワークである木質資源の水解と糖液の利用に関する課題に着手しました。また、この年、分子生物学の講義でベストティーチング賞を頂くことができましたが、これは私の北見工大在職中のハイライトです。この時ばかりは齢50半ばにして北見工大に職を得て本当に良かったとしみじみ思いました。
最後に、この誌面に拙文を載せて頂く機会を得て、研究課題に真摯に取り組んだ多くの卒業生、研究を遂行する上でご協力頂いた先生方、また、縁の下で支えてくださった職員の皆様に深く感謝しています。何よりもまして、歳の差が40もある私にいつも元気を与えてくれた多くの卒業生の皆様、ありがとうございました。北見工大が地域社会を牽引し、益々発展していくこと、同窓の皆様の益々のご活躍とご健勝を祈念し、退職の記といたします。
=学科便り=
機械工学科
卒業生の皆さま、毎日お変りなくお過ごしでしょうか。本年度は、2020年日本でのオリンピック開催という明るいニュースが国内を駆け巡った年でした。機械系分野においても、以前にも増してスポーツ競技を支える技術の研究が盛んに行われるようになってきました。当学科、鈴木聡一郎教授が手がけておられる日本人の体型を考慮して世界のトップ選手と競い合えるスキーブーツの開発研究もその一例かと思います。今後益々機械工学の様々な応用分野への広がりを予見させる出来事のようです。
さて、機械工学科においては平成24年度から25年度にかけて教員の異動がありました。まず、平成2年4月に赴任された小林道明先生が、平成25年3月をもって定年ご退職なされました。先生は、23年の長きにわたり200名を超える材料力学研究室の卒業生を輩出されてきました。平成25年3月20日ご退職記念祝賀会も開催されました。一方、同年4月、新たに生体メカトロニクス研究室の助教として、星野洋平先生がご着任されました。システム制御分野をご専門とされ、非常に精力的な研究活動をなされている若きホープです。今後、当学科において教育・研究両面でご活躍いただけるものと皆期待を寄せています。今年度は、前年度の小林先生に続き、長年当学科そして本学でご活躍なされた田牧純一先生もご定年の節目にあたり、今後さらに当学科には新旧交代の波が押し寄せるようです。
平成24年度卒業生の就職状況についてですが、平成25年3月時点で民間企業への就職決定率は学部・大学院合わせてほぼ100%と、昨年同様良好な結果となりました。つづく今年度については、内定率も8月時点で大学院・学部併せて9割近くに達しており、就職担当としてご尽力いただいた大橋教授、佐藤准教授に感謝申し上げ安堵しているところです。その他、大学院博士前期課程進学予定の者も来年度以降の新たな勉学の場を心待ちにしているようです。
今年も羽二生教授の熱心なご指導の下、6月9日の本戦出場(東京)を勝ち取ったNHKロボコン「チームOnion」ですが、惜しくも決勝トーナメントには進めませんでした。次年度に向けリベンジを期するところです。なお、同窓会関東支部のご関係各位にはご支援を賜りました段、この紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。
最後に卒業生の皆さまにおかれましては、どうぞ健康にご留意され、益々のご活躍ご発展をいただけますよう心よりお祈り申し上げます。
(学科長 山田貴延 記)
◯材料力学研究室
卒業生の皆さま、お元気ですか。小林道明先生は今年3月末日をもって定年退職されました。先生の退職記念パーティーにご出席あるいは記念品贈呈にご賛同頂きました卒業生の皆様にこの紙面をお借りして御礼申し上げます。これにより平成25年度のスタッフは柴野、三浦先生と技術部大森さんの3名となり、学生はM2:6名、M1:3名、4年生:6名とこれまでの大所帯から縮小されました。社会人博士後期課程に在籍していた釧路高専の石塚和則氏も博士の学位を取得され無事修了されました。4年生の進路とM2の就職も全員決まりました。4年生は3名が大学院進学です。三浦先生はAEや超音波による研究指導や実験装置の製作に相変わらず大忙しです。超音波顕微鏡復活で生体骨の共同研究も再開しました。ソフトボールは決勝トーナメント敗退です。大森さんのGo on Footも続いております。末筆ながら皆様のご健康とご活躍を祈念しております。
(柴野 記)
◯計算力学研究室
今年度の計力研究室は大橋教授、長谷川技術員、新たに特任研究員の安田さん、研究室の事務補佐員として木山さんが加わり佐藤を含めスタッフ5名体制です。学生は後期課程にリディアナさんが残り、大学院生7名、学部生8名です。学会活動では大橋先生、私がハワイ島で開催の国際会議に参加、国内では函館、九州佐賀での講演会の準備で院生は大忙し、4年生は卒研中間発表会の練習真っ最中です。恒例の登山では今年もメカトロや材力の学生も参加し、総勢19名の大パーティーで雲海からのご来光を眺め、大雪山のお鉢を1周してきました。天気は良好でしたが、残雪が今までになく多い大雪山でした。
大橋先生と佐藤の今年度の就職担当の仕事も一段落ついたところです。来年4月から皆さんの後輩達が新社会人として巣立ちます。同じ会社に入社しましたら、どうぞ温かい目でご指導のほどお願いいたします。
皆様の益々のご活躍をお祈りしています。また、皆様の近況を是非ともご連絡下さい。
(佐藤 記)

北海岳山頂(標高2149m) 2013年7月14日
◯設計工学研究室
現在設計工学研究室は学部生4名、菅原先生を含め5名です。学部生は9月の卒業研究中間発表に向けて研究を進めています。現在の研究のテーマは人体モデルの数値シミュレーションとVR空間における降雪現象の再現です。VR降雪の研究では今年の6月の学校祭で一般の方々や大学の関係者に体験してもらう展示を行い、その来場者数は200人を数え好評の内に終えることが出来ました。研究室には大学院前期課程及び後期課程の先輩がいないのでこれまでの先輩の研究成果などを見て手探りで研究を行っていましたが、研究室配属から5ヶ月が過ぎ今では自ら研究に取り組めるようになりました。卒業までの時間後悔が無いよう研究に取り組んでいきたいと思います。
(4年 薮 記)
◯エネルギー・環境工学研究室(佐々木研)
卒業生の皆様、お元気でご活躍のことと思います。研究室のスタッフは、佐々木教授、遠藤助教、学生は社会人ドクター1名(燃料電池)、M2・2名、M1・2名、4年生・5名、の計12名で構成されています。研究テーマは、地中熱ヒートポンプ冷暖房システムの性能予測と設計ツールの開発、湖沼から大気に放出される温暖化物質(メタン)フラックスに関する研究および大気と内水面間の温暖化物質(メタン)交換過程の解析となっています。
卒業生の皆様、来北の際は、ぜひ研究室にお立ち寄り下さい。
(遠藤 記)
◯伝熱システム研究室
今年度の当研究室には、大学院にはM2:川原、内藤、繆、M1:増山の各君が所属し、ここに4月に配属された4年生:5名(内田、大島、嵯峨、塚本、高橋の各君)が加わって、チームワーク良く研究室での毎日を送っています。今年も中西さんを中心に、8月3日に学生諸君の汗だくのご協力の下、小学校低学年向けの「おもしろ科学実験」を実施しました。さらに1ヶ月後の9月3日には、私が所属する伝熱学会主催のキッズエネルギーシンポジウムに研究室単位で参加し、紋別市内外の小学5年生を集めて「スターリングエンジンキット」の作製・実験を行うなど、普段接している学生よりも随分と若い力(ちびっ子たち)への育成に寄与した夏となりました。9月9日?11日の間、川原君、内藤君、中西さんらと岡山で開催された機械学会年次大会に出席し、学生二人とも堂々とした発表をしてくれました。さて、学科長任期も後半に入った私は、翌春の年季明け!?を心待ちにしつつ、次期学科長にスムーズにバトンを手渡せるよう気を引き締めています。最後に、卒業生皆様の今後のご活躍・ご健勝をお祈り申し上げます。
(山田 記)
◯エンジンシステム研究室
卒業生の皆さま、景気が回復しつつある中(8月現在)、益々ご活躍のことと存じます。今年は卒研生が6名配属されましたが、例年同様クルマ好きの学生が多く、研究室は和気あいあいとした雰囲気です。恒例のママチャリレースでは今年も上位入賞を果たすことができました。ご支援をいただきましたOBの方々には心より御礼申し上げます。石谷先生には待望のお孫さんが誕生され、いよいよおじいちゃんの仲間入りをされました。私の方は特に変わりありませんが、四十近くとなり体力と記憶力の衰えを感じます。
研究の方は、今年は高出力YAGレーザを新たに導入しました。今後はこのレーザを燃焼および噴霧解析に活用する予定です。また、ヤンマーの単気筒エンジンにはコモンレールシステムを搭載しました。このエンジンを低温室に設置し、ディーゼルエンジンの低温始動時の筒内燃焼詳しく調べることを計画しています。このように研究室は年々進化しておりますので、しばらく研究室に足が遠のいている方は是非お越しください。
(林田 記)
◯流体工学研究室
卒業生の皆様方におかれましては、元気にご活躍のことと存じます。今年度の流体工学研究室は、羽二生教授、小畑技術員、高井のスタッフ3名とD3が1名(社会人)、M2が1名、M1が他研究室からの移籍1名を含めて4名と学部生が6名です。
羽二生教授は2年前の当欄に自ら「衰えを感じ」と書かれておりましたが、端からはそのような感じは見受けられず、様々な雑務の他にロボコンチームを率い、研究室では噴流制御、渦構造などの基礎研究とGPSを活用した空撮システムの開発を継続して進められています。小畑技術員は実験室と技術部の仕事で多忙ななか、畑の収穫物を持ってきてくださり、研究室に技術と食料を提供してくれています。高井はさらなる成果を残すべく、流力振動問題に取り組んでいます。また、インターンシップに参加して将来に備える学生など、研究室ではそれぞれ日々努力を積み重ねています。
北見・道東方面にお越しの際には、ぜひ研究室にお立ち寄り下さい。
(高井 記)
◯流体制御工学研究室
異常気象が続く中、卒業生の皆さまは医科がお過ごしでしょうか。4月から大学院に進んだ谷川君は流体工学研究室に移り、今年は私(宮越)と就職希望の4年生4人でのスタートとなりました。学生はそれぞれ大学最後の?夏休みを謳歌したところです。
研究は、異径2円柱を用いた噴流制御をはじめ、共通講座の柳先生との共同研究でカーリングのスウィーピング力測定ブラシ(特許出願中)や身体的負担を軽減する除雪シャベルの開発などを進めております。なお、装置製作や解析システムの改良では、技術部の佐藤敏則さん・長谷川稔さん・ものづくりセンターのみなさんに多くのご支援を頂きました。大変感謝しております。一方、学生にも使用する装置やモデルを自ら製作することで、もんづくりの「大変さ」「面白さ」「奥深さ」の理解を深めてもらうようにしています。来北の際には当研究室にもお立ち寄り下さい。皆さまのご活躍とご健勝をお祈り致します。
(宮越 記)
◯計算流体力学研究室
卒業生の皆さま、元気でお過ごしでしょうか? 現在の計算流体力学研究室は、三戸先生のご指導のもとで、博士前期課程2年2名、学部4年4名が研究に励んでおります。研究に関しましては、今年は学部生、院生ともに固気分散流/マイクロバブル分散流の物理現象の理解に取り組んでいます。我々、院生においては、研究の意義や独自性を出すためのストーリー展開やまとめ方について苦戦しながらも、前向きに研究しています。2月初旬にはOBの川本さんが来室し、研究室生活の思い出や就職活動について話してくださいました。道東に出張で来ることはあまり無いと思われますが、OBの方々ともっと交流を深めたいと思いますので、機会がありましたら是非当研究室にお立ち寄りください。卒業生皆様のご健康と益々のご活躍をお祈りしております。
(M2 牧野 記)
◯応用流体工学研究室
今年度は4名の新4年生を迎え、M1が1名、M2が5名となりました。5名のM2は、あと数ヶ月で学位論文を完成させる必要があるため、追い込みの実験や学会発表(函館、福岡)で大忙しです。春は例年通り「ゆうゆコテージ」での研修打ち上げに始まり、6月の大学祭では、伝統の焼肉レイノルズを実施しました。全国的に多発している大学内での飲酒事故等の影響で、今年度の大学祭は、禁酒となってしまい、ビール販売できず、その分、収益は減少したようです。しかし例年通り夏のキャンプは盛大に行なわれ、今年は様似のアポイ岳山麓に行きました。ただし天候には恵まれず、アポイ岳登山は中止となり、長年使用していた私のタープやテントは強風で飛ばされ、ズタズタに壊れてしまいました。無念です。キャンプでは、今年も多くのOBのご支援をいただきました。この場をお借りしてOBの皆様に感謝申し上げますとともに、益々のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。
(松村 記)
◯マイクロ・ナノ加工学研究室
卒業生の皆様におかれましては、ご壮健にてご活躍のことと存じます。今年度の当研究室では、D3が2名、大学院生5名、学部生7名、また8月で留学を終え帰国した留学生2名が、スタッフ4名の下で活動しています。田牧教授、ウラ准教授、久保助教、杉野技術員の下で学生に対して熱心なご指導をしていただいております。研究室の近況としまして、院生3名が国際会議ICMDT2013(韓国)、精密工学会北海道支部大会(北見)に参加し、他の院生1名も9月末の国際会議ISAAT2013(中国)に参加予定です。さらに、精密工学会北海道支部大会において院生1名が優秀プレゼンテーション賞を授与されました。D3の留学生Ashrafulさんは来年3月の学位習得に向け、日夜研究に励んでいます。最後に、今年度をもって退職される田牧教授に感謝と、皆様の益々のご活躍をお祈り申し上げ、挨拶とさせていただきます。
(M2 新井 記)
◯光計測研究室
今年の構成人数は、M1生の立花侑也君、学部4年生の小芦直樹君、加藤賢太君、矢野敬大君、和波志門君と私の6名で、例年通りの少数ユニットです。
4年生は全員が就職希望で、この文章を書いている8月21日時点において、内定を得た者は卒研に大いに、あるいはまあまあ頑張っています。内定を得ていない4年生は東奔西走していますが、たえず資料や参考論文と光学書をたずさえていますので、実験こそしていませんが、それなりに卒研を進めています。M1生は、授業に出席することと宿題をこなすことに忙殺されていますが、それでも、入学時に作成した研究計画を着々と実行しています。
今年度末、はたまたそのつぎの年度末にどのような果実が実るのか、たいへん楽しみです。
(尾崎 記)
◯生体メカトロニクス研究室
卒業生の皆様、元気でご活躍のことと思います。今年度は、本研究室にとって大きな出来事がありました。新たなスタッフとして、北海道大学から星野先生が助教に着任しました。早速、若い力で活躍していただいています。そんなわけで今年の研究室は、スタッフ2名に加えD2が1名、M2が5名、M1が3名、B4が6名というメンバー構成となりました。4年生は5名が大学院に進学し、1名が就職内定をもらいました。M2の岩本さんは9月で修了し、10月から地元愛知の会社で社会人生活をスタートします。研究面では、本邦初のコンピュータ制御スキーシミュレータが導入され、スキーブーツの研究で多くの選手が来訪しています。受動歩行ロボットも登坂やターンができるようになり、新たな展開に向かっています。パワーアシスト膝継手も実用化が見えてきました。除振台の研究もスタートしました。全日本8時間ママチャリ耐久レースでは、3チームが出場し、211チーム中総合6位、7位、50位と健闘しました。ご支援頂いた卒業生の皆様には心から感謝いたします。今年の4年生もスポーツ好きが多く、北見ハーフマラソンにも出場します。是非、研究室に遊びに来て元気な顔を見せてください。
(鈴木 記)
4月1日に本研究室の助教として着任いたしました星野洋平と申します。北見市出身で今年37歳になりました。大学入学とともに北見を離れておりましたが、この度、故郷に帰ってまいりました。前任の北海道大学では、制御工学(振動制御)、メカトロニクス、機械力学を専門として除振台のアクティブ制御に関する研究等を行ってまいりました。北見工業大学では、引き続き除振台のアクティブ制御、機械システムの振動制御を主な研究テーマとし、さらに受動歩行ロボットなどの研究テーマにも積極的に取り組んでいきたいと考えております。そして研究室の一員として研究室の発展に尽力させていただく所存です。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
(星野 記)
◯生産工学研究室
3月に、4年生4名が無事に卒業しました。大学院への進学者いませんでしたので、現在の陣容は、前期課程2年生1名、4年生4名です。相変わらずこじんまりしており、和気あいあいで研究をやっています。院生と4年生3名の就職が内定し、4年生1名は求職中です。研究は相変わらずの摩擦圧接です。私は、あと2年半でお役御免となりますが、来年からは院生無しの体勢となります。研究室のコンパでは、めげずに「たこ焼きの最適加熱条件の設定実験」を続けています。多少、景気も戻っているようですが、まだまだ卒業生の皆様もご苦労が多いかと思います。ご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
(冨士 記)
◯知的システム工学研究室
研究室の名前の由来は、遺伝的アルゴリズム(GA)、人口ニューラルネットワーク(ANN)、機械学習(ML)、人工生命(AL)、エージェント等の技術がスマートエンジニアリング(知的工学)と呼ばれ、これらの新技術を用いて工学的に色々な実問題へ取り組みたいとの思いから付けました。主な研究内容は、進化計算と機械学習による自律的な行動獲得、大規模問題によるハイパフォーマンスコンピューティング、物理法則に基づくアニメーティッドロボットの三本柱となっております。
今年の研究室は、学部4年生4名、大学院1年生1名と2年生2名の合計7名の学生で構成されています。研究室では、屋外でジンギスカンやバーベキューパーティーを行ったり、屋内でカレーライスや焼きそばなどを作ってコミュニケーションを深めています。また、今年の9月には、北海道大学自律系工学研究室、北海道情報大学古川研究室、北見工業大学鈴木研究室と知的システム工学研究室の4研究室(40名)で1泊2日の夏旅行(帯広)へ行き、学生同士の親睦を深めたようです。
本年度の研究室学生は、日本機械学会ロボット・メカトロニクス2013学術講演会で1名、2013年度精密工学会北海道支部学術講演会で7名、情報処理学北海道シンポジウム2013学術講演会で3名が発表しました。また、計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2013)で3名が発表する予定になっています。
卒業生の皆様、北見にお越しの際には是非知的システム工学研究室にお立ち寄り下さい。
(渡辺 記)
社会環境工学科
卒業生の皆様にはますますご健勝のことと存じます。
本年は、3月に発達した低気圧の影響で北見近郊を猛吹雪が襲い、市民生活に大きな影響を与えました。また、北見だけではなく局所豪雨災害や竜巻さらには台風による被害が日本のあちこちで発生した年でもありました。自然環境の保全とともに防災・減災の分野で当学科の果たす役割が非常に高いものであることを再認識させられております。同窓生の皆様方も社会に大きく貢献され、お忙しくされているものと推察しております。
社会環境工学科の近況をお伝えいたします。
今年度は、9月に日本自然災害学会および雪氷研究大会が北見工業大学で相次いで開催され、内外から研究者が集まり、当学科の研究も含めて熱心な討議が行われました。卒業論文や修士論文作成への良い刺激になったものと思います。
教員の異動では近年になく少ない年となりましたが、4月1日付で国立極地研究所から大野浩先生が助教として着任され、雪氷の分野でご活躍されております。
昨年度から学生の自主性と問題解決能力の向上をより一層図る新たなカリキュラムとなりましたが、2年目の今年から学科での本格的な指導となりました。具体的には、2年生前期の科目である「社会環境工学基礎」において、明確な解が無いような技術者倫理に関連する事例を教員から提供し、様々な観点から議論させるものです。後期からは、昨年度の母校だよりでもご紹介させていただきましたが、社会環境工学の分野に関する地域の抱える問題点を学生自らが発掘してその問題解決策を4人程度が一組になってチームワークで見つけ出す「オホーツク総合演習」が始まります。新たな試みではありますが、これらの科目によって、より社会に役立つ技術者になってもらいたいと考えております。来年秋には、その成果の公開発表会も予定しておりますので、ぜひそちらの方にも参加していただければ幸いです。
卒業生の皆様におかれましたは、ご健康に留意されますますご活躍されますことをご祈念申し上げます。
(学科長 渡邊 記)
◯河川防災システム研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。河川防災システム研究室は今年で6年目を迎え、渡邊教授、吉川助教の下、院生2名、学部生5名の計7名で活動しており、大変賑やかで活気あふれる研究室となっております。研究内容につきましては、北海道の河川をフィールドに、現地調査や学内外での水理実験、数値計算によるシミュレーションを行い、河川・河道内での現象の把握や機構の解明に努めております。近況といたしましては、6月に札内川において実施された擬似洪水放流の一端を我が研究室が担うこととなり、小型ADCP流速計を購入し、流量観測を行いました。また、毎年行われている常呂川調査では、今年より念願であった光波測量を実施できることとなったことから、調査に費やす時間と労力が大幅に軽減されることとなりました。
最後になりましたが、来北の際には是非当研究室にお立ち寄り下さい。卒業生の皆様との歓談の機会を研究室一同、心からお待ちしております。
(M2 島 記)
◯水圏環境研究室
今年度は新4年生3名に加え、パナマから国費留学生(大使館推薦)を1名、大学院前期課程に受け入れました。さらに、JSPSの外国人特別研究員制度を利用して、ベトナムからの研究者が2年間の予定で滞在を開始しました。非常勤研究員を中心とした知床での栄養循環に関する研究も順調に進んでおり、それも全てよい学生やスタッフにも恵まれた結果だと思います。国内外の共同研究機関が15を超え、学外との交流を通じた学生への教育も進めることが出来ております。今後とも、ご支援のほどよろしく申し上げます。
(中山恵介 記)

4年生&カルロス歓迎会

知床ルサ川観測

コムケ湖調査
◯水処理工学研究室
今年度も個性豊かな学生が集まり、日々、研究に奮闘しています。研究内容は引き続き、網走湖、釧路湿原、瀬戸内海、オーストラリア、ペルー等のフィールドを中心に、汽水域の水質や底質改善、湿原の生態系保全、浅場の環境再生、濁質対策、水資源予測等の研究を行っています。研究面での発展はもちろんですが、学生達には研究を通じて新しいことにチャレンジし、社会で活躍できる力をつけてもらいたいと願っています。学生たちは元気に研究活動を進めていますので、機会があればぜひ気軽にお立ち寄りください。どうぞよろしくお願いいたします。
(駒井克昭 記)
◯環境水理研究室
卒業生の皆様、お元気でしょうか? 私、中尾も何とか元気に毎日を過ごしております。
本年度、当研究室に配属となった学生は学部生3名でいずれも早々に就職、進学が決まり、卒業要件としては卒業研究のみとなり、この文章を作成中の夏休み(9月中旬)もほとんどとらずここ数年来、先輩の方々が残してくれた水文データベースの解析に熱心に取り組んでおります。昨年度は私が就職担当となり、お陰様で多くのOBの方々とお会いできました。皆様も来北の節はぜひ当研究室にお立ち寄りください。最後となりましたが、皆様も体に気を付け益々活躍されることを願っております。
(中尾 記)
◯河川・水文学研究室
今年の研究室メンバーはM2-1名、M1-1名、学部生-3名の計5名です。研究テーマは河川関係が釧路川の旧川復元河道や藻琴湖の流況調査・水理実験・数値解析、水文関係は中小河川の流出解析や畑地からの浮遊土砂流出の軽減対策などに取り組んでいます。現地調査で釧路や試験地のある東藻琴や藻琴湖へ出かけ、室内実験や数値解析などで、学生は各自のテーマと格闘しています。
おめでたいお知らせです。早川先生は今年4月に教授に昇任されました。学外・学内の委員会など相変わらず多忙な日々を過ごしています。研究室OBの皆様、近くに来る機会があれば、是非とも研究室にお立ち寄りください。
(M1 工藤 記)
◯都市・交通計画研究室
平成25年度春は、修士2年、修士1年、社会人博士課程に学部4年と、久しぶりにフルメンバーによるスタートとなりました。研究テーマとしては防災・減災、ディマンドバスの実証運行などといった公共交通を中心に行っています。特に今年は、北見・網走都市圏においてパーソン・トリップ調査が実施され、わが研究室も中心的な役割を果たすことになっています。PT調査をはじめとして交通研究を社会に役立てることの重要性を、研究室一同身を以って感じている次第です。
(高橋 清 記)
◯ハイドレート研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか?ハイドレート研(環境・エネルギー研究推進センター)では庄子教授、八久保准教授、百武技術員、布川技術員、三橋技術員の各スタッフ、学生では卒論生のチョウ・杉森・笛木・松田・岩本・清水、研究生の阿南の計7名が研究活動に勤しんでいます。今年度はサハリン島沖(6月)、バイカル湖(8月)、北極海(8-9月)、網走沖(9月と11月)、5つもの天然ガスハイドレート調査があり、スタッフ総出で手分けしててんてこ舞いです。今年の雪氷学会(9月)は北見で開催され、実験室研究で良い結果を出した卒論生が発表予定です。皆様もお忙しい日常かと思いますが季節の変わり目は体調を崩しやすいので、くれぐれも風邪など召されぬようご自愛下さい。北見に来られる際には、是非とも研究室にお立ち寄り下さい。8月でも雪の舞う北極海より。
(八久保 記)
◯岩盤工学研究室、寒地岩盤工学研究室
卒業生の皆様、お元気でしょうか?昨年度、中村が准教授となり、寒地岩盤工学研究室をスタートさせました。研究やコンパ等は岩盤工学、寒地岩盤工学、さらに凍土・土質(川口先生)、三つの研究室合同で行っています。メンバーは教員が後藤准教授、平松技術員、中村准教授の3名、学生が8名に増え、随分にぎやかになりました。今年度は6月に資源・素材学会北海道支部・春季講演会を北見で開催いたしました。懇親会をオホーツクビール園で行い、道内から集まられたみなさまに地ビールや海産物を味わっていただきました。後藤先生は本年度(平成26年3月31日)いっぱいで定年退職されます。退職を迎えられるとは思えないほど気力・体力ともに充実しておられ、毎週末のようにゴルフ場に通っていらっしゃるようです。退職後には、毎年訪れたスコットランドに行くと宣言されている位元気です。後藤先生の定年退職まであと半年となりました。卒業生のみなさま、是非来北し、研究室へ顔を出して下さい。
(中村 記)
◯地圏環境防災研究室
卒業生の皆様、お変わりありませんか?今年の研究室は4年生3名と少数ですが、知床カムイワッカ川での渓岸調査、津別チミケップ湖での地すべり調査や北見市低地域の地盤解析など、一緒に汗をかいています。
私たちの生活を支えるインフラの劣化は、ソフト面も含めて確実に進行しています。皆さんが担っている生活面での“安心・安全の確保”、“自然環境の保全”や“健康環境の創造”といった役割はますます重要になってきています。先日、31年前の卒業生が立ち寄ってくれました。顔も体もふっくらしていて、一瞬、あれ?と思いましたが、目をみて「◯◯くん?」と声を掛けました。「はい!!」と答えてくれました。還暦を過ぎ、病に倒れた身には皆さんの活躍が大きな励みになります。近くに来た際には是非、顔を見せて下さい。健康第一!慶事は是非、一報を!
(伊藤陽司 記)

飛び入りもあった恒例の“ウィンブルドン焼肉パーティー”
◯地盤工学研究室
卒業生の皆様、元気にお過ごしでしょうか。地盤研究室も発足して間もなく20年を迎えます。今年の研究室のメンバーは、三浦君(M2)、小川君(M1)、学部3名(1名進学予定)、平田さんと山下です。卒業、修了予定者は皆就職先等も決まり、研究活動に没頭しています?山下は久しぶりにロシアサハリン沖調査に出かけてきました。院生は相変わらずバイカル湖、サハリン沖、網走沖調査に強制参加です。来年は潜水艇調査も行う予定です。
(山下 記)
◯凍土・土質研究室
卒業生の皆様、お元気でしょうか?一昨年の4月に赴任して、勝手ながら“新生”凍土・土質研究室を引き継がせていただき、2期目の卒業生も無事に輩出させることができました。3年目に入った本年度は研究室に最初の大学院生2名も誕生しましたし、土質実験室には他の地盤系研究室の学生さんも幾人か一緒におりますので、これまでに比べると大変賑やかな研究室になってきております。次年度も大学院生が増える予定ですので、さらに活気あふれる研究室になるよう努めていきたいと思っています。学生さんの数とともに研究テーマも増え、屋外での実験も年々増えてきておりますので、平田さんに助けてもらう割合も心苦しいながら増える一方です(いつもすみません、平田さん・・・)。卒業生の皆様、お近くにお越しの際は是非凍土・土質研究室にお立ち寄り頂き、少しずつですが実験装置や屋外実験フィールドも充実しておりますので、新しい研究室を覗いて頂ければ幸いです。また、特に鈴木先生時代の凍土・土質研究室出身の皆様には、我々新メンバーに研究室の思い出話をお聞かせ頂けますと幸いです。お会いできる日を楽しみにしています。
(川口貴之 記)
◯構造・材料系研究室(維持管理工学研究室・地震防災工学研究室・コンクリート工学研究室)
卒業生の皆様にはお元気でご活躍の事と存じます。本年度も構造・材料系3研究室合同で研究活動を行っています。また、本年度はM2が5名、M1が5名ということで大学院生が豊富な年となりました。そして、昨年度と同じく、大島特任教授、三上教授、宮森准教授、井上准教授、山崎助教、齊藤助教、岡田技官、坪田技官、研究補助員の北尾さんにご助力頂きながら、総勢28名で日々研究や講義に励んでおります。
維持管理工学研究室では、M2が2名、4年生が3名で研究を進めております。主な研究内容は、PVDF加速度計を用いた振動測定システムの検討、局部振動加振による損傷検出に関する研究、画像データを用いた橋梁健全度モニタリングに関する研究、橋梁点検データを用いた劣化予測の検討、電磁波レーダー法を用いた床版の劣化予測などの研究を行っております。
地震防災工学研究室では、M2が3名、M1が4名、4年生が3名で研究を進めており、主な研究内容は、モード振幅の変化を利用した橋梁の損傷位置同定、スマートセンサーを用いた橋梁振動実験、釧路市における既存構造物を用いた津波避難に関する検討、サブストラクチャハイブリッド実験システムの構造実験部分の複数個所対応などの研究を行っております。
コンクリート工学研究室では、M1が1名、4年生が3名で研究を進めております。主な研究内容は、亜硝酸系補修剤の浸透性および耐候性評価、CTSによる既存コンクリート構造物の劣化診断技術に関する研究、亜硝酸系混和剤と減水剤を併用した新型耐寒剤の開発、などの研究を行っております。
最後になりましたが、北見にお越しの際には是非研究室にお立ち寄り下さい。また、その際には実社会での体験などをお聞かせ頂ければと思います。卒業生皆様のご健康と益々のご活躍お祈りしております。
(M1 齋藤 記)

4年生の歓迎会
◯交通工学研究室
現在、研究室には、川村教授を代表に、筆者(富山)、博士前期課程3名(内留学生1名)、学部生3名が在籍しています。今年度は、海外の大学との共同研究がスタートし、「人?車?道路」を基盤としながら、新たな研究テーマにチャレンジしています。川村教授は、日中間で行われた舗装技術のワークショップで、日本の代表として、路面評価の重要性を交え挨拶し、多くの関心を呼んでいました。また、在学生も国内外の学会や会議で研究成果を発表するなど、積極的に活動しています。卒業生の方々のご活躍ぶりを耳にすることも多く、ご多忙のこととは存じますが、近くにお越しの際には、是非研究室にお立ち寄り頂き、ご歓談の機会を持てますと幸いです。
(富山 記)

日中舗装技術ワークショップで挨拶する川村教授
◯雪氷系研究室(雪氷防災研究室A、雪氷防災研究室B、雪氷科学研究室、寒冷地環境工学研究室、氷海環境研究室)
卒業生の皆様、お元気にお過ごしでしょうか。今年度の研究室メンバーは教員6名(高橋、亀田、堀、舘山、白川、大野)、院生(博士後期課程)4名(平松、横山、田中、日下)、院生(博士前期課程)4名(佐々木、星野、村上、小倉)、4年生16名の計29名です。今年度より新たに大野先生が着任され、学科の中でも大所帯となりました。また今年も昨年度同様、研究室恒例の大雪山系の雪壁雪渓に行きました。今回は亀田先生、白川先生とが学生5名が融雪末期の大きさを測量してきましたが、涼しかった5月、6月を反映してこれまでになく大きな規模でした。今年は天候にも恵まれ、秋の紅葉風景を眺めながら充実した観測を行うことが出来ました。さらに合同のゼミなどで研究の経過を発表する機会を増やすなど活動を充実させています。

大雪山系高根ヶ原での雪壁雪渓測量隊

雪壁雪渓(高根ヶ原からの崖に位置している)
各研究室の教員と研究の近況をご報告します。雪氷防災研究室Aには4名の学生(外山、中村、木村、宮澤)が配属され、高橋先生のご指導のもと、冬期の路面摩擦に関する研究(外山)、光学的特性を用いた路面凍結判別に関する研究(中村)、光を用いた積雪深の測定(木村)、南極での調査の歴史(宮澤)など、他分野にわたる研究が着々と進められております。また、大学院博士後期課程の日下さんは今夏シベリアでの観測を行い、ワールドワイドな研究を視野に入れています。大学院博士前期課程佐々木は北見と陸別の盆地冷却現象の研究を進めており、小倉は昨年に引き続き地中探査レーダを用いた積雪情報の解析手法の開発を進めております。
亀田先生の雪氷科学研究室は3名の4年生(秋保伸介、猪股将弘、今野拓也)が配属されています。秋保は昨年の成田による卒論を引き継ぎ、技術員の信山さんと一緒に南極氷床で掘削された氷床コア氷の含有空気量を測定しています。猪股は雪結晶の生成実験をしており、生成される雪結晶の形態を詳細に調べる予定です。今野は昨年の近藤による卒論を引き継ぎ、南極ドームふじ基地で観測した無人気象観測データに含まれているバイアスを補正する方法を検討しており、成果を今年の雪氷研究大会でポスター発表しました。亀田先生は厚さ1cm程度の水に飽和したぬれ雪表面に現れる白い斑点模様の研究を続けられており、今年の雪氷学会で4回目の発表をされました。大野先生は南極氷床コアに含まれるエアロゾル起源物質や空気ハイドレートの形成過程に関する研究を行っています。
堀先生の寒冷地環境工学研究室は今年で8年目を迎え、今年度も3名の卒研生が配属になり、大学院生1名と合わせて4名になりました。M1の村上は雪氷学会支部会(札幌)や北見で開催された雪氷研究大会で研究成果を発表しました。卒研生3名のうち1名は既に就職は内定しましたが、2名は公務員志望の学生も含めて現在も就職活動中です。卒業研究のテーマは、例年と同様に南極やグリーンランドの氷、南極の浅層コアの密度測定、ガスハイドレートに関する研究(の予定)です。
氷海環境研究室は今年で2年目となりました。舘山先生は7月に近年海氷面積の減少により物資輸送などで注目されている北西航路にてカナダ砕氷船を利用した海氷観測に参加されました。写真はそのときに現れた北極熊です。今年度より研究室に復帰したD3田中は6月にアラスカ州バロー、8月に舘山先生と入れ替わりでカナダ砕氷船に乗船し北極海の海氷観測に参加しました。今年の北極海は海氷が多かったです。M1星野は11月末から3月中旬まで日本南極地域観測隊に海氷部門の同行者として参加します。4年生の島崎、白川、湊谷はそれぞれ株式会社ドーコン、ケアホームひだまり、西村組に内定をもらい残すは卒業研究のみとなりました。
白川先生の雪氷防災研究室Bは今年で2年目になりました。この研究室では、雪氷学と土木工学の知見を融合し、雪氷災害の軽減防除や、利雪・親雪のための調査研究を行っております。先生のご指導の下、3名の学生がこれからの研究室の更なる発展を目指して、日々研究を進めております。
最後に卒業生の皆様の近況も是非お知らせ下さい。また、近くにお越しの際には是非お立ち寄り下さい。教員・学生共々皆様との歓談の機会を楽しみにしております。皆様のご健康と一層のご活躍をお祈りしております。
雪氷研究室HP: http://snow.civil.kitami-it.ac.jp
(M2 佐々木 記)

砕氷船に興味津々な北極熊
電気電子工学科
暑かった夏もようやく終わりに差し掛かり、過ごしやすくなったこの頃ですが、皆様にはお元気でご活躍のことと存じます。同窓会の皆様にはいつも大変お世話になっとり、この場を借りて御礼申し上げます。
さて、今年度は同窓会関係で大変うれしい出来事がありました。9月13日(金)に、電気工学科第4期生(昭和48年卒)の方がた10名が、母校をお尋ね下さいました。中には卒業以来初めてという方も何名かいらして、母校の変わりように驚くとともに、その発展ぶりを大変喜んでくださいました。
ご一行は大学に到着後、田牧副学長を表敬訪問され、そのあと電気電子工学科をご訪問になられました。学科の変遷と現状を学科長から簡単にご説明したあと、旧電気工学科に源流を持つ4つの研究室を順次ご見学になられました。皆さんの在籍時の教員・職員は全員退職されてどなたも残っていらっしゃらない筈でしたが、見学先には何と退職された元技官の大内さんと小竹さんが再雇用で勤務中でした。お互いに名前を確認しあい、非常に盛り上がった瞬間の写真を掲載させて頂きます(写真では盛り上がりが全然表現できていませんが、ご勘弁ください)。ご一行は、見学終了後、温根湯温泉に移動して品田雄治先生などをお招きして旧交を温める予定を伺いました。
米国の大学などでは卒業生が母校を訪ねるHome coming dayという行事があるそうですが、電気電子工学科ではいつでもOB・OGを歓迎いたします。北見で同期会などを開催する折にはぜひご訪問下さい。
もうひとつの大きな出来事として、本学始まって以来の、電気学会電子・情報・システム部門大会開催があります。9月4?6日の3日間にわたって全国から600名以上の方々が参加されました。ホスト役は学科対応ということで、田村淳二教授が開催地区実行委員会委員長となり、教員はじめアルバイト学生を含めてハードワークを勤め上げました。おかげさまで電子・情報・システム部門大会としては過去最多の論文投稿件数と過去第2位の参加者数(1位に2名及びませんでした)の実績を残し、成功裏に開催することができました。また、本学で開催という地の利を生かして電気電子工学科からも多数の発表があり、その中から、学生ポスター発表賞の一人として本学科の院生が選ばれました。写真は学生ポスターセッションで発表する受賞者の様子です。
最後に学科の様子ですが、3月に吉田公策教授と保苅和雄助教が定年で退職され、柳沢英人助教も退職されました。また、4月1日付けで、新たに杉坂純一郎助教が着任されましたことをご報告させて頂き、学科だよりとさせていただきます。
同窓生の皆様にはお元気でお過ごしください。
(学科長 谷本 洋 記)
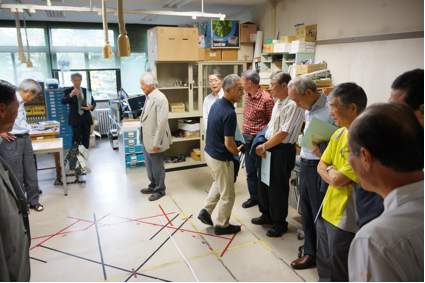
電気工学科第4期生ご一行の研究室見学のひとこま
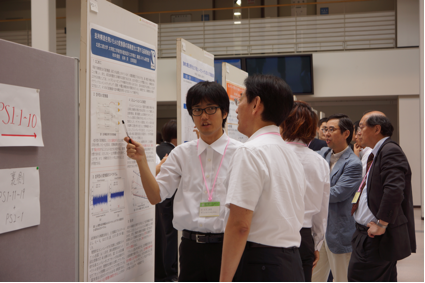
ポスターセッションで熱心に説明する学生
◯電気基礎研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。電気基礎研究室では、昨年度で吉田教授がご退官なされ、川村先生の制御班のみとなっており、学部生が6名、M2が2名の学生が配属されています。
川村先生は、各種ロボットの開発に精力的に取り組んでおります。例えば、3球輪車両では人を載せるべ補強の実施、4脚ロボットでは新たな動きの制御、そして、RFIDの車の誘導では周波数の950MHz帯から920MHz帯へのシステム移行に伴い新たなタグの埋め込みなど多くの課題に取り組んでいます。
大内先生は昨年度、退官でしたが、再雇用で継続して学生実験のサポートやロボットの部品の加工や、他研究室のサポートなどをおこなっています。
吉田先生も前期は電磁気の非常勤講師として講義を受け持っていましたが、後期からは新任の先生が来る予定で、ようやくゆっくり出来るようです。
岸本は制御班に移行し、新たにRFID関係のプログラムを開発しており、ビジュアルC#やAndroidアプリの開発に奮闘しております。
皆さまの益々のご活躍を期待しております。また、北見を訪ねる機会がありましたら、ぜひ研究室にお立ち寄り下さい。
(岸本 記)
◯応用電気研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか?
応用電気研究室の学生は全員元気にしております。今年は長年努められていた保苅先生が退職されました。実験やTAのときには大変お世話になりました。研究室一同感謝しております、本当に今までありがとうございました。
さて、現在の応用電気研究室の近況についてご報告いたします。今は、医用生体工学を研究している谷藤教授、プレイン・マシン・インタフェース(Brain-Machine Interface;BMI)の研究をしている橋本准教授のもとで日々研究に精進しております。今年度の研究室のメンバーは、修士2年生が3名、修士1年生が2名、楽譜4年生が11名です。
平成25年9月には修士の学生が北見工大での電気学会電子・情報・システム部門大会で研究発表しました。大勢の聴衆に堂々と自分の研究内容を話す姿はとても頼もしく、今後の研究室の発展に貢献してくれることでしょう。学部の学生も皆それぞれの卒業研究テーマにそって日夜研究に取り組む一方で、進学あるいは就職活動にも励んでいます。
卒業生の皆様、お忙しいとは思いますが北見にお越しの際はぜひお気軽にお立ち寄り下さい。教員・学生共々、皆さまとの歓談の機会を楽しみにしております。皆様のご健康と一層のご活躍をお祈りいたします。
(M2 中村 記)
◯電力工学研究室
平成25年度は、博士課程3名、修士課程10名、学部10名、研究生1名の全24名の学生と、小原のほか、植田先生、仲村先生、そして熊本大学で学位取得されたモレル・ホルヘ特任研究員のスタッフ4名で合計28名の構成です。来年修了予定の修士2年生と就職希望の4年生は、関電工や北海道電力などから内定を頂きました。また、本年度の2月に赴任されたモレル・ホルヘさんは、パラグアイご出身の電気機械の専門家で、現在は北見市全域のマイクログリッドのデザインについてご研究されています。ホルヘさんには研究室の国際的な活動のほか、地域貢献活動から留学生のお世話まで広くご活躍して頂いております。本年度の10月からは、金来憲さん(韓国)とMd. Rashidul Islamさん(バングラデシュ)が修士課程に入学されます。また、近いうちにガスハイドレートの専門家である、中国の博士研究員が当研究室に参加されます。本年度の10名の新4年生(日本人)は例年になく高成績者が集まり、そのうち4名で大学院へ進学します。新4年生は既に全国規模の学会でポスター発表をしており、さらに、オホーツク流氷科学センター(紋別市)にて小学生の科学教室を支援しています。
(小原 記)
◯電気機械研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。現在の電気機械研究室は博士課程1名、修士課程11名、卒研生10名と田村教授、高橋准教授、梅村助教、小竹技官に、本学の博士後期課程を今年3月に修了されたロシャディ・マルワン研究員が新たに加わり、総勢27名と大所帯になっております。
研究室の状況といたしましては、国内での学会参加の他、10月に韓国で開催されたICEMS2013や11月にオーストリアで開催されたIECON2013などの国際学会にも参加しております。
近年の地球環境問題や原子力発電の見直しから本研究室で行っている風力発電の研究はますます重要になってきており、各々の学生が研究に取り組み、隔週で研究成果の報告会を行ったり、学生同士で集まって勉強会を開くなど、学生間または先生を含めた議論も活発に行われております。その他、研究室の近況はホームページ(http://pullout.elec.kitami-it.ac.jp)に記載され、随時更新しておりますので、ご覧いただけると幸いです。
このように、電気機械研究室は賑わっておりますので、卒業生の皆様、お近くにお越しの際はぜひ研究室にお立ち寄りください。卒業生皆様の益々のご健康とご活躍をお祈りいたします。
(M1 吉田 記)
◯集積システム(旧電子基礎)研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年は、谷本教授、吉澤准教授、大学院生5名、学部生11名、計18名の体制で日々励んでおります。柳沢先生は今年3月に退職されております。本来ならば後任の助教の先生を迎えるはずなのですが、昨今の大学の厳しい財政事情もあり、しばらくは教員2名体制で続けなければならないようです。学生実験の指導が大変ですが、学生と直接話ができるので何が理解を妨げているかの洞察を得られる利点もあります。時間的には大変ですが、大学院生に実験のTA(ティーチングアシスタント)をお願いして何とかやっています。今年の就職活動状況は、電子コース全体にも言えることなのですがかなり苦戦している状況です。就職活動を本格的に始める時期が遅れるなど積極性に欠けているのが一因かと思われますが、これからでも挽回してもらいたものです。
研究室の活動報告及び予定ですが、9月上旬に本学で開催の電気学会C部門大会でM1の3名が成果発表を行いました。今後も10月下旬に室工大で行われる北海道連合支部大会など、学生が日々の研究成果を発表したり、大学や企業の方と交流する機会を得るようにしていく予定です。また、5月に4年生歓迎会、6月にバーベキューパーティ、8月に送別会(9月卒業の学生)と昨年とほぼ同じ研究室行事がありました。写真は学生が撮影したバーベキューパーティの様子ですが、谷本先生から影響を受けたのか一眼レフカメラを始めた学生が増えているようです。北見近くにお越しの機会がありました際には是非研究室にお立ち寄りください。
(吉澤 記)

集積システム研究室2013
◯波動エレクトロニクス(旧電子応用)研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年度の波動エレクトロニクス研究室は、大学院生2人、卒研生7人、研究生1人です。平成21年の電子等改修工事によって、大学院生も学部生も明るく広くなった部屋で、快適に研究に励んでおります。コンピュータを駆使した光・マイクロ波デバイスの解析と雪渓が研究の中心ですが、マイクロ波回路の作製・測定も継続して行っております。
平成25年4月に、杉坂純一郎先生が当研究室の助教として宇都宮大学から着任されました。光エレクトロニクスや電磁界解析がご専門で、新進気鋭の研究者としてご活躍されております。教育では学生実験と電気回路演習をご担当されています。
安井崇先生は、光導波路デバイスを中心として、活発に研究活動をされております。教育では電気回路I、電磁波工学等を担当されております。
平山は光・マイクロ波のデバイスの最適設計やマイクロ波・ミリ波帯での材料定数測定法の研究に取り組んでおります。
北見にお越しの際には研究室にも是非お立ち寄りください。卒業生の皆様のご活躍を祈念しております。
(平山 記)
◯通信システム(旧電子機器)研究室
卒業生の皆様におかれましてはお元気でご活躍の事と存じます。現在、通信システム研究室の構成は柏教授、田口准教授、今井助教の教員3名、そして、学部生8名の計11名となっており、日々研究に励んでおります。
本研究室では、現在、主に高度情報化社会及びユビキタス社会を見据えた高度な移動通信システムを構築するための研究を行っております。その一環としてITS技術を利用した自動車衝突防止システムに関する研究、マイクロ波・ミリ波・光波に関する研究、自動車搭載アンテナの最適設計に関する研究等を行っております。また、電波吸収体に関する研究も行っております。他にも、科学研究費テーマ及び企業との共同研究等に対しても研究室一丸となり精力的に取り組んでおります。
尚、研究室近況は通信システム研究室ホームページ(http://kashiwa-lab.net/)にて公開し、随時更新しております。お時間がある時にでもご覧頂けると有り難いです。因みに、研究室Webサーバの移転に伴い新ドメインを取得し、今年から新しいURLとなっっております。
(柏 記)
◯集積エレクトロニクス(旧電子物理学)研究室
卒業生の皆様お元気でお過ごしでしょうか、今年もこのたよりを書く季節となりました。今年の夏は毎日どこかで雨の振る日が続いて、いつもの北見ではないようでした。35度の名古屋を体験してきた武山先生には快適と写ったようです。研究室は野矢、武山、佐藤とスタッフに変更はありません。武山先生は研究に釣りに全力投球のご様子です。佐藤は元気いっぱい空回りの感も拭えませんが、「あのなぁ?」と言われる頻度は下がってきているのでしょうか?最近は実験をおやりになる学生さんが少なく、昔のような、装置の開くのを待っているということはなくなりました。実験室は結構空いており、気が向くと実験のできる環境にあります。それだけ、学生さんの指向や趣味も変遷を遂げているように思えます。それでも、研究室として、6月の金沢の国際会議、8月の釧路での研究会、9月の福岡の電子情報通信学会、10月の新潟の研究会、10月の東京の国際会議と学会活動は精力的に行っております。金沢、福岡は某佐藤の飲み食いプランとの噂も無きにしもあらずですが・・・。いずれにしても、元気で研究ができるということの幸せを感謝して日々を過ごす好々爺でありたいものだと思っている野矢のこの頃でございます。
(野矢 記)
情報システム工学科
卒業生の皆様、お変りなく元気で御活躍のことと思います。
情報システム工学科の近況を御知らせ致します。今年度から、長年情報システム工学科の事務を担当されていた谷口さんの後任として田中さんが着任し、谷口さん同様、しっかり、頼りない学科長のサポートをしてくれています。亀丸俊一教授は復職されて1年、至って健康そのもの、学生の指導にご活躍されており、毎日のビールが楽しみの様子です。また、鈴木正清教授も変わりなく元気に理屈をこねて居ります。河野正晴教授は今年還暦を迎え、一層風格に磨きがかかって来ました。来北の折には、赤いちゃんちゃんこの御用意を。
さて、大学を取り巻く環境が大きく変わってきて久しいですが、職員一同変わりなく元気で研究・教育等に頑張っております。卒業生皆様におかれましても、社会の変化に惑わされる事無く、一層の御活躍を願っております。
(学科長 山田 記)
◯知的システム設計分野
・システム制御研究室(榮坂俊雄研究室)
卒業生の皆様お変わりありませんか?今年は学生13名が在籍し、昨年から在籍している社会人博士の方を講師に英会話教室を行うなど、研究以外の活動も積極的に行っています。
研究では、修士学生が9月にポスター発表をしたものの、4年生は就活の関係で本格的な研究はこれからというところです。ただ、例年より9月現在で内定を頂けた学生も多く、後期からの研究活動に期待が持てそうです。また、今から自分の考えたテーマで研究をしたいという3年生も居て楽しみな状況です。
最後に、来学された折には、ぜひ研究室にも立ち寄ってください。そして、大学と卒業後の経験談を聞かせて頂ければ、学生には新しい刺激になるかと思います。
(宿院 記)
・情報通信システム工学研究室(中垣淳研究室)
卒業生の皆様いかがお過ごしでしょうか。当研究室では、中垣、技術職員の宇野さんをはじめ、院生2名、4年生5名、3年生4名が日々ゼミや研究に励んでいます。厳しい就職環境の中、就職組は依然・・・。進学組は面接の出来・不出来はありましたが無事合格し、やっと研究に集中できるようになりました。研究では、音声分析、雑音抑圧法の開発、音声の評価システムの構築をすすめています。今年の歓迎会では幹事の後藤君が自ら中華鍋を振り振り、シェイカーを振り振りで頑張ってくれました。その他、焼肉パーティーや秘密の夜会(?)など和気あいあいとやっています。次は石山君の釣ってきた鮭で石狩鍋かな。当研究室出身のOB・OGの皆様、近くにお越しの際には是非お気軽にお立ち寄り下さい。
(中垣 記)
・鈴木育男・岩館健司研究室
本研究室は、M1:1名、4年生:5名の学生を鈴木育男准教授、岩館健司助教の2名の教員で研究指導を行っています。昨年4月に始動したばかりの研究室ですが、(1)人間行動解析システムの構築と運動学習支援に関する研究、(2)仮想物理環境下における仮想生物の行動生成・学習に関する研究、という研究テーマで研究活動を行っております。また、上記の各研究テーマに関して、同じ知的システム設計工学分野の榮坂研究室(榮坂俊雄教授)、機械工学科の知的システム工学研究室(渡辺美知子准教授)との共同研究も実施しております。卒業生の皆様、お近くにお越しの際は是非お気軽にお立ち寄りください。
・信号処理研究室(鈴木正清研究室)
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか?信号処理研究室では、「センサアレイ信号処理」の研究と、「サケ自動追跡ロボット船」、「国際会議の電子投稿システム」および「北見市内立小中学校の備品と図書の管理システム」の開発を行っています。
卒業生の皆様、近くにお越しの際には是非ともお立ち寄り下さい。
(鈴木正清 記)
◯知識工学分野
・医療情報・医用画像工学(早川)研究室
RICOH & Java Developer Challenge Plus2012に挑戦した4年生3名は、13年1月最終選考会でオラクル賞を獲得、5月オラクル主催“Java Day Tokyo 2013”に招かれアキバでプレゼン。詳細はhttp://dip.cs.kitami-it.ac.jp/にあるリンク先を見てください。13年度の同コンテストにも新チームで挑戦中です。今年も一次選考を通過し、2014年1月の最終選考会に出場します。また大学院生の宮中君と董君は、採択率4割を突破して12月に北米放射線医学会(RSNA2013)で学術発表・デモンストレーションを行います。董君は3年連続。なお董君はドイツとの共同研究を論文にしました。さて、4年生3名が大学院進学予定ですが、研究テーマはカーリングのバイオメカニクス、脳波インタフェイスと医療情報クラウド。チャレンジする学生さんたち。
・テキスト情報処理研究室(桝井文人研究室)
卒業生の皆様如何お過ごしでしょうか。
桝井研究室は今年も構成員数が高めを維持しており、例年通り不夜城の様相です。4月からプタシンスキさんが助教として着任され、研究室スタッフに加わりました。学生は、D1:中島さん、3年生(CS研究):畠山、平田、古澤、渡部さんを新たにメンバーとして迎え、スタッフ3名・学生16名と、昨年にも増して多岐に渡る研究活動を行っております。
また、今年も学生全員の進路が決まり、福島、信太、羅さんの3名が本学大学院へ進学し研究に励んでくれる予定です。お近くにお越しの際は是非お気軽にお立ち寄りください。
(熊本 記)

・知能情報研究室(後藤文太朗研究室)
今年から研究室名が「知能情報研究室」になりました。これにともない、学生部屋の名称が「パターン情報実験室3」から「知能情報実験室」に変更になりました(部屋自体は変わっていません)。
平成25年9月現在、研究室メンバーは、スタッフとして後藤、4年生が上野、北谷、水野、吉川の4人です。技術部からの派遣で奥山技術員の協力を得ています。当初いたCSセミナー・研究の履修者(3年生)が途中でやめてしまいましたが、少数精鋭のチームでやっています。
・知識情報処理研究室(前田康成研究室)
平成25年度の前田研は、M2米澤君、M1黄君、トウさん、B4池田君、河西君、佐々木君、樋口君、松浦君、横島さん、B3上野君、佐々木君、坪井君、本田君の計13名と技術員の奥山さんに前田です。
新ネタでマネジの横島さんと佐々木君が、殺処分ゼロを目指した保護目的の猫カフェやアニマルセラピーを研究中です。夏休みには1期生の高畠君が遊びに来て、昼間は知床、夜はオホーツクビールを堪能しました。知床は前田も初でしたが、よかったです。OB/OGの皆さんも機会がありましたら、是非、お越しください。
・核科学情報工学研究室(升井洋志研究室)
研究室も9年目になりました。今年のメンバーはM2の堀川君、4年の山本君、田澤君、宮川さん、若松君、三浦君、粟津君、秋田君です。近年の研究室のテーマは核反応データベース活用と、観光情報学の2本立てです。オホーツク地区の放射線測定、データ共有とクラウド利用、観光の様々な観点をパラメータ化し、物理モデルを適用することで新たな可能性を見いだす研究も行っています。
◯光情報工学分野
卒業生の皆さんお元気ですか?昨年から情報システムの同窓会誌原稿は、情報システム工学科改組に伴って変更した4つの新研究分野で執筆しております。「光情報工学分野」は従来から光学、光情報工学および画像処理に関連した研究を行ってきたメンバーが集まってできていました。そこに所属するメンバーは、旧情報メディアネットワーク分野に所属していた亀丸俊一教授、三浦則明教授、原田建治准教授、桑村進助教と旧計算機科学分野に所属していた原田康浩准教授、曽根宏靖准教授の合計6名です。
亀丸研究室は、昨年7月亀丸が病癒えて退院した後徐々に復調に励んでいる状況を考慮していただき、4年生の卒研配属は上原、金沢、佐藤(周)の3名に抑えてもらいました。当然のことですが大学院生以上は在籍しません。今年度は徐々に体調も整ったことから、新たに手がけている観光情報学の一環として温根湯温泉へのフィールド調査へ出かけてきたりしています。
三浦研究室では、M1の大石、4年の青木、倉知、滝口、三浦、茂垣、3年の阿部、大石、田崎、野口、八木の総勢11名が補償光学、天体画像処理、道路画像処理などの観測、実験、ゼミに励んでいます。
原田建治研究室では、M2の土田、4年の阿久津、稲葉、菅原、原、横川、3年の浅野目、氏家、神成、鈴木の総勢10名がホログラム、偏光色、光学教材開発などの卒業研究や、セミナーに励んでいます。4年の菅原、原は大学院へ進学予定です。
原田康浩研究室は、M2の米田、M1の藤田、淵脇、学部4年の佐々木、永井(マネージメント工学)、松尾、ワフィ、小湊、CSセミナーの3年・柳沢の合計9名の学生で、ディジタルホログラフィの高性能化、低温型雪結晶の生成と3次元計測に関連した研究、ゼミにと励んでいます。
昨年度開設した曽根研究室では、M1の加藤、4年の青山、緒方、福山、Ge shuai、3年の遠藤、大友、玉村、三田、市川の総勢10名が、光ファイバーを用いた光情報処理や今年度から開始したLEDを使った可視光通信などの研究やゼミに励んでいます。
OB、OGの皆さん、北見へお越しの際には、北見工大をお尋ね下さい。そして遠慮せずぜひ私たちの研究室を訪れ、焼肉の街北見の夜の繁華街へ私たちをお連れ下さい。お互いの近況報告で盛り上がりましょう!
(亀丸 記)
◯情報数理研究室
今年も3年次CS研究、4年次卒研、大学院修士課程に情報数理関係学生が多数在籍しておりにぎやかです。とくにM2新木君は修士論文の追い込みがかかっており連日山田教授とディスカッションの毎日です。
(渡邊 記)
バイオ環境化学科
◯生物資源科学研究室
工学部の化学系には珍しい生物資源科学研究室を立ち上げ10年、今年は最終年度となり、いよいよ3月で研究室の看板を降ろすことになりました。これまでに研究にご協力頂いた卒業生の皆様には深く感謝申し上げます。本年度のメンバーは、青山政和と霜鳥慈岳助教に加えて、大学院博士後期課程2年の三浦雅弘(札幌市厚別出身)、4年目の工藤大樹(岩手県出身)、佐藤栞(滝川市出身)、清野慶介(山形県東根市出身)、山根史也(鳥取県出身)の総勢7名です。なお、霜鳥助教は来年4月より星先生の精密有機化学研究室に配属替えとなり、これまで通り研究を継続されることになっています。
研究テーマは、三浦君、清野君、山根君の3名は、青山のライフワークであるタケ、ササ、シラカンバなどの木質未利用資源の水解と溶出糖の微生物変換、工藤君と佐藤さんはボロン酸基を有する機能性ポリマーの作成に取り組んでいます。研究成果の一部は、ゴールデンウィーク中にシンガポール市で開催された農産物および天然資源利用技術に関する国際会議(ICANRE 2013)や木質炭化学会(6月初旬に新潟市で開催)で発表され、Wood Science and Technology誌やHolzforschung誌に掲載あるいは掲載許可されています。
例年ですと夏休み明けには大半の卒業予定者の進路は決まっておりますが、今年の就職状況は大変厳しく、地元志向が強いこともあいまって大変苦戦しています。おっとりしているところが工大生の良いところでもあるのですが、やや積極性に欠けるとの誤解を受けるケースもあり、リーダーシップを前面に出すように指導しているところです。
青山は今年も6月中旬からの休日には船釣りを楽しんでおりますが、唐揚げサイズのマガレイが50?100枚程度、釣果はいま一つ、漁港近くの魚屋でホタテやホッケの開きなどを調達し学生達と賞味しています。最後になりましたが、卒業生の皆様のご健勝と益々のご活躍をお祈り申し上げます。
(青山 記)
◯生物有機化学研究室
卒業生の皆様お元気でご活躍のことと思います。今年の夏は全国的にたいへん暑いようですが北見ももれなく暑い日が続いています。本研究室(吉田研)は教授1名、助教3名、研究員3名、博士課程9名、修士課程6名、学部学生10名の30名余の大所帯ですが、微生物班とバイオエタノール班は、住佐研究員を中心に総合研究棟を拠点としているため、スムーズに実験を進められる体制となっています。吉田教授は副学長(研究担当)として大学運営の要職を担うと同時に博士課程学生の指導、各種会議への出席、かさねて国内外各地への出張と多忙を尽くされておられます。小俣助教は卒論学生の指導はもとより、操作法の熟練さを要する大型機器分析装置を駆使し、博士号修得に向けた留学生のデータ解析にご助力されております。昨年10月、内モンゴル大学から赴任された本学卒業生の韓助教は複数名の卒論学生の担当に当たると同時に、中国語は勿論、モンゴル語そして洗練された日本語を巧みに使い分け、中国とモンゴルからの留学生の良き相談役となっています。沖本助教は相変わらず電極反応から卒業できず、日々ガスクロ分析に一喜一憂しています。先に、博士号を修得したトグシさん、梁さんは研究員として着任しており、自分自身の研究に磨きをかけるかたわら後進の指導にも余年がなく貴重な戦力となっています。一方、研究の方も着実に進行しており、今年新たに西川君、ソリナさん、白君の3名がめでたく博士号を修得しました。それに刺激されてか博士号修得時期をまじかにひかえた後輩の院生達も休日返上で夜遅くまで実験にいそしんでいます。しばしば卒業生が研究室を訪ねて来てくれます。お近くにお寄りの際は是非お立ち寄りください。
(沖本 記)
◯バイオプロセス工学研究室
OBの皆様いかがお過ごしでしょうか?
本年度の学生はMC4名、4年目6名で、相変わらず和気あいあいと楽しくやっております。就職状況ですが、苦労はしますが比較的順調で就職希望者は全員決定しました。最近は、食品、JAなど食に関する会社への就職が増えています。研究では、最近はバイオプロセスによるバイオリファイナリー研究に注力してきましたが、小西助教の赴任に伴いゲノム解析やプロテオーム解析等の基礎手法を充実させ研究領域を拡大しようとしています。研究内容は研究室ホームページを参照ください(http://bioprocess-eng.com/)。また近況を是非堀内宛にメールか電話でお知らせください(horiucju@mail.kitami-it.ac.jp、電話0157-26-9415)。楽しみにしています。
こちらに来る機会がありましたら是非研究室にもお立ち寄りください。
(堀内 記)
◯精密有機資源化学研究室
卒業生の皆さん、今年は一昨年と同様に暑い日が続きましたが、お元気でお過ごしでしょうか。北見はお盆頃を過ぎてから気温が徐々に下がり始め、9月中旬になりますと、夜風が寒く感じられめっきり秋めいて来ました。
2020年に東京オリンピックが再び開催されることが決まり、今から楽しみにしている方も多いと思います。私もその一人です。前回開催された時私は9歳の小学生でしたが、テレビで入場行進を観ていたのを憶えています。この次は65才ですが、何かひとつ実際に競技会場に足を運んで観たいと思っています。
今年度の研究室は修士2年2名、修士1年2名、学部4年5名と昨年と同様に大所帯となっています。私はいつものように授業のない日は実験をしています。就職は学部4名が内定しましたが、修士2名はまだ決まっていません。学部1名は本学の大学院に進学する予定です。今年も恒例の屈斜路研修所での宿泊研修を行いました。天候にも恵まれ、楽しい思い出がまた増えました。写真は第三展望台から摩周湖と摩周岳を背景にしたスナップです。
北見にお立ち寄りの際は、ぜひ研究室にお立ち寄りください。皆様のご健康とご活躍をお祈りしています。
(星 記)

◯炭素変換工学研究室
アベノミクス、円安、デフレ脱却などの社会経済が国民の中心話題となっている平成25年の日本ですが、同窓生の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。北見は、寒い春、雨の降らない暑い初夏、高温多雨の盛夏を経て、結局ほぼ平年並みの実りの秋を迎えています。定年退職まで残すところ2年を切った鈴木教授の研究室では、院生は2名と少ないものの、常に朝10時には全員が揃うという研究好きの精鋭に支えられ、これまでの研究の集大成と社会への技術還元を目指して活動しております。本年度の研究室メンバーは、すっかり丸くなった…とはまだ言い切れない鈴木先生をはじめ、M2:1名(中川)、M1:1名(百崎)、4年生:5名(中山、永由、本保、山岸、山田)、非常勤研究員の私(鈴木京子)の計9名で、木材だけでなく、色々な植物バイオマスをターゲットとした触媒炭化によるキャパシタや誘電性の炭素製造やバイオマス炭素のガス化等の研究を行っています。特にガス化は、新時代に向けた高効率の水素製造・供給を睨んで画期的な触媒を発見し、科研費を獲得しての研究です。とはいうものの、全国各地からの出身者が多く、リケジョも加わった和やかな雰囲気にあります。お近くにお越しの際はどうぞお立ち寄り頂き、可愛い後輩達に先輩としての経験談などお聞かせいただければ幸いです。これからもどうぞお元気でご活躍下さい。
(鈴木京子 記)
◯環境有機化学研究室
卒業生の皆様におかれましては、お元気にご活躍のことと存じます。
今年度の環境有機化学研究室は、兼清泰正准教授、修士2年生1名、学部4年生7名、および技術補佐員1名から構成されています。現在当研究室では、従来取り組んできた糖センサーの開発に加え、ホルムアルデヒドや過酸化水素などバイオ・環境・食品に関わる様々な化合物をターゲットとして、新規センシングシステムの創製に取り組んでいます。
今後とも研究のさらなる発展に向けて一同邁進していく所存ですので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
(兼清 記)
◯食品栄養化学研究室
今年度の学生の構成は、4年生5名(鐙田麻衣、小塚太朗、平田美穂、水間卓哉、吉田悠一郎)、修士1年3名(関本将吾、戸田一也、長谷川誠和)、修士2年1名(笹山志穂)です。卒業生の進路は、1名が本学の大学院進学、2名が民間企業、1名が公務員への就職を決めております。また、今年度も留学生を2名受け入れており、活発に国際交流を行っております。研究は、引き続き食品成分によるアレルギー抑制効果について進めるとともに、活性酸素ストレス抑制効果についても進めています。これらの成果は、国際会議2回、国内学会2件の発表、論文2報を予定しています。今後もより一層研究室の活性化を行い、研究、教育、地域貢献、大学運営に貢献していく所存です。同窓会の皆様の御指導・御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
(新井 記)
◯生物無機化学研究室
卒業生の皆様、お元気ですか。2013年度のメンバーは、菅野の他に、M2 2名、M1 1名、4年生6名の総勢9名で昨年より2名減少しましたが、他研究室メンバーとの交流が盛んなようで研究室内はにぎやかです。“無機材料の機能を活用する”という大研究テーマのもと、アパタイト、ホタテ貝殻(炭酸カルシウム)、粘土(無機層状化合物)を用いた薬物徐放材料や環境浄化材料の開発を目指しています。学会活動では、化学会北海道支部大会(7月北見)において3名の院生が口頭発表を行いました。また彼ら3名は、セラミックス協会秋季大会(9月長野)に向け準備を行っているところです。さらに、他のメンバーも2014年2月に札幌で開催される化学工学・粉体工学発表会、あるいは卒論発表会に向け頑張っているところです。
メンバーの進路ですが、M2および4年生合わせて8名のうち、2013年8月現在、4年生2名が本学大学院進学予定であり、他に4名が会社の内定を得ています。
最後になりましたが、皆様の益々のご健勝を祈念しております。また、メンバーへの良い刺激、貴重な情報となりますので、是非皆様の状況をメールでお知らせ下さればと思います。機会があれば、研究室にも足をお運びください。
(2013年8月 菅野 記)

2013年度生物無機化学研究室 新歓コンパ(撮影者 菅野、2名欠席)
◯無機物理化学研究室
▼学科名がバイオ環境化学科に変更(2008年4月)。▼スタッフ:岡崎准教授。▼学生:博士前期2年1名、1年2名、学部4年6名、留学生1名の総勢10名。進学希望者は4名(他大学2名)。就職戦線は無事内定が決まり、早々と終結。▼大学祭はオープンキャンパスで参加し、液体窒素で手作りアイスクリームコーナを行う。人が入れるシャボン玉は子供に大人気。▼今年も美幌東陽小学校でソーラーカー工作を行う。北見の「科学の祭典」と同様に理科離れを食い止めるように活動。▼キャンプは丸瀬布いこいの森キャンプ場2泊3日で開催。雨模様の中、浮き世を忘れて、ただひたすら飲んで、遊んで、温泉三昧。▼大学院生3名とAPCAT6(台湾開催)に参加。中華料理で盛り上がる。▼ホームページ公開中。リニューアルは思うように進まない。(http://www.chem.kitami-it.ac.jp/ipc/index.html)。▼岡崎:De-NOx反応、メタン直接分解、LIB用電極材料、廃プラスチック接触分解に研究を展開中。オホーツクエネルギー環境教育研究会委員長として、網走管内小中高の先生と連携を模索中。環境・エネルギー関連の新演示実験テーマを模索中。▼今年も多数のビール券ありがとうございました。卒業生のなんでも相談をいつでも受け付けます。0157-26-9420(岡崎)、FAX 0157-24-7719。zaki@catal.chem.kitami-it.ac.jpまでメールを。
(岡崎 記)

2013/9/4 やまびこ温泉前にて
◯生体分子化学研究室
ご卒業の皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。早いもので当研究室が発足して2年が経ちました。昨年度は第一期生の3名が卒業していきました。うち1名は本学大学院に進学し、研究を続けています。よく実験するので少しずつ成果が現れ、今年は高分子学会、日本化学会、セルロースシンポジウム(予定)など、ようやく学会等でポスター、口頭発表ができるようになりました。現在の研究テーマは、セルロースと糖質高分子の合成。真空ラインが導入されましたので、イオン重合ができるようになっています。今後ともよろしくお願いします。
(服部 記)
◯環境高分子化学研究室
同窓生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。私共、環境高分子化学研究室は今年度、教員の中谷久之教授、宮崎健輔助教、博士1年に浜館雅人君、修士2年に新井孝行君、修士1年に佐藤亮作君、佐藤宏彰君、学部4年(共同研究含む)に奥島公大君、川村稜君、菊池慎平君、澁谷亮祐君、松本龍士君、山岸智也君、渡辺彩華さん、渡部大気君というメンバーで日々研究に勤しんでおります。研究内容は、ナノセルロースファイバーを用いた環境調和型プラスチック複合材料の開発、高分子材料の生分解化およびリグニンの光分解を研究しております。
同窓生の皆様で、上記の研究内容を含めプラスチック関係に興味がある方がいらっしゃいましたら、お気軽にお声をかけてください。
(宮崎 記)
◯環境物理化学研究室
同窓生の皆さんお元気でしょうか。早くも今年度の研究室便りの執筆時期(秋)がやってきました。今年度の研究室の構成メンバーは三浦と松田技術員、学生は学部4年生4名、M1が2名、M2が1名です。研究内容は本年も、「NMR」・「水」・「食品」をキーワードに行っております。今年度の特筆としては昨年末に機器分析センターに導入された600MHz NMRが本格的に稼働を始めたことでしょうか。この装置は15年近く使い慣れた500MHz NMRの更新として導入されました。この装置の導入と技術部業務の見直しなどもあり、松田技術員は機器分析センターでも仕事できるスペースを頂き勤務日の午前中はそちらでNMRの維持管理や液体窒素関連の業務を行っています。4年生の進路も少しずつ決まりつつあり、例年通りこれから卒研などに拍車をかける時期となってきました。
卒業生の皆様におかれましては、健康に留意されて仕事などに励んで頂くことを祈念して研究室便りといたします。
(三浦 記)

◯食品化学研究室
同窓生の皆様には、お元気にご活躍のこととお慶び申し上げます。当研究室では、本年3月に、学部生5名(うち2名が大学院進学)と大学院生(修士課程)3名が巣立ちました。一方、今年度は、大学院修士課程2年生が1名、同1年生2名、4年生5名の8名の学生が在籍しており、別途1名が仮配属となっています。
研究内容は、食用担子菌シイタケの分子育種のための基本技術の確立、有用酵素発現組換えシイタケの造成と解析、シイタケの新規ラッカーゼの解析、及びシイタケ栽培廃液に含まれる有用酵素類の解析などです。
皆様のご活躍とご健康をお祈り申し上げますとともに、今後のご支援・ご指導をよろしくお願い申し上げます。
(佐藤 記)
マテリアル工学科
◯電子材料研究室
卒業生の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
今年度の電子材料研究室のメンバーは、阿部先生、川村先生、金のスタッフと学部4年生8名、大学院博士前期課程10名(M2・7名、M1・3名)、同後期課程1名です。
現在の主な研究は、引き続き、エレクトロクロミック、有機ELや有機太陽電池などの様々な電子材料を用いたデバイスを扱ったテーマとなっており、日々熱心に研究開発に取り組んでおります。
今年も3月の応用物理学会をはじめ、大学院生も、積極的に国内・国際学会で参加・発表を行っています。達成感や自信を高める共に社会に旅立つための良い経験になるように指導を心がけております。また、研究だけでなくバーベキューなどを通じて、楽しい思い出作りを行っています。
今年の研究室の大きなニュースは、川村先生が指導されてきた中国人留学生の張 子洋(ジャン ズヤン)さんが「種々の表界面層を用いたAg薄膜の熱的安定性を電気抵抗率」のテーマで3月に博士後期課程を無事卒業した事です。研究室一同、新しい「博士」の誕生をお祝いしました。
卒業生の皆さんもお忙しいとは思いますが、北見近くにお越しの機会がありましたら是非研究室にお立ち寄り下さい。皆様のご健康とご活躍をお祈りしています。
(金 記)
◯有機材料研究室
卒業生・修了生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。
今年度も渡邉眞次教授、村田美樹教授、浪越毅助教の指導のもと日々実験に励み、厳しくも楽しい毎日を送っています。研究室のメンバーは院生10名(M2・6名、M1・4名)、学部生7名の計17名となっています(内、女子はM1・1名、B4・2名)。また、今年の4月をもって村田先生が准教授から教授に昇格しました!!本年度も昨年度に続き、就職活動が厳しい状況のためなかなか全員が集まることがありません。
実験テーマは例年通りに有機合成グループは遷移金属触媒を用いたクロスカップリング反応を、高分子合成グループは異形粒子の合成、リビングカチオン重合を中心に研究しています。また、多くのメンバーが学会への参加、学術論文の投稿などを行い、積極的に研究発表しています。
恒例行事であった山登りについては、5年ぶりくらいで復活しました!!大雪赤岳に登る予定でしたが天候不良のため雌阿寒岳及び阿寒富士に登頂しました。そして、有機研登山史上初の脱落者が出ましたorz。なんと、9.7合目で高所恐怖症により、途中下山www。
あまり更新していませんが研究室でイベント等があった際は掲示板や写真を更新していきたいと思っていますのでぜひのぞいてください。行事の掲示板、メールなどで近況をご連絡いただけると幸いです。
最後になりましたが、卒業生の皆さんのご活躍、ご健勝を心より祈りつつ、日々の仕事などでお忙しい中、なかなか機会はないかもしれませんが、出張、旅行等で大学の近くにお越しの際に、皆さんが研究室に遊びにこられるのをお待ちしております。
研究室のHP(http://www.mtrl.kitami-it.ac.jp/~watanabe/shoukai.htm/toppu.html)
(有機材料第一研究室 M1 岡田 記)

◯無機材料研究室
卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今年の北見の夏は地球温暖化の影響なのか、残暑が厳しく9月過ぎても暑い日々が続きました。
今年度は伊藤先生のご指導の下、M2が1名、B4が3名の計4名のメンバーで構成されており、少人数ですが非常に活気あふれる状態で日々過ごしております。
現在行っている研究は、チタニア系光触媒、ホタテ貝殻、強誘電体や粘土鉱物を扱ったテーマとなっており、日々の実験に励んでおります。
進路状況についてですが、今年は多少の景気回復が囁かれていますが、例年通り就職活動は困難なものとなっています。就職希望者のうち半数以上は内定を決めることができ、また決まってない学生も一生懸命に就職活動を頑張っています。
今年のB4は2名が就職希望者で1名は大学院への進学が決定しましたので、来年は院生が1名となり研究室が少し寂しくなってしまうかもしれません。
伊藤先生は、例年と同様にご多忙な日々を過ごされています。教授会などの会議の参加、学部生や院生の講義、国際学会の発表の準備、共同実験の打ち合わせ、私たちの指導で大忙しです。
最後になりましたが、卒業生の皆さんのご活躍、ご健勝を心より祈りつつ、日々の仕事などでお忙しい中、なかなか機会はないかもしれませんが、出張、旅行等で大学の近くにお越しの際に、皆さんが研究室に遊びにこられるのをお待ちしております。
(M2 松田 記)
◯微結晶材料研究室
平卒業生の皆様、元気でご活躍のことと思います。本研究室に、今年4月1日付で古瀬裕章先生が新任助教として着任されました。高出力レーザーや太陽光励起レーザーとそれに関わる要素技術の開発を担当します。後者は年間日照時間が長い北見の特徴を活かした研究としても今後の展開が期待されます。
レーザー用の発振材料や透明材料の分野では、高出力や大口径化といった課題に対して、単結晶よりも多結晶材料に高い可能性が見出されています。異種陽イオンドープ、微粒子プロセシング、微細粒での高密度焼結といった手法を駆使して新しい特性を引き出すことが鍵となり、その過程では粒界偏析、応力下拡散、粒界すべり、結晶粒成長といった素過程が関与します。このような材料学的観点から見ると、レーザー用セラミックスと超塑性セラミックスとは多くの共通項をもっています。外部機関との連携も含めて、このような観点からの研究も今後進めていく予定です。昨年度の4年生3名は本学(印藤、近藤)と北大(福西)の博士前期課程に進学し、気持も新たに勉学と研究に取り組んでいます。今年度は4名の4年生(井野、清水、高井、和田)が研究室に配属され、それぞれ2名ずつが進学と就職の予定です。学生・院生が総勢6名となって超塑性やレーザー材料の研究に携わることとなり、一層の活気となりました。ご興味がございましたらぜひ研究室にお立ち寄り下さい。
◯触媒機能材料研究室
卒業生の皆さん、いかがお過ごしですか。本年度の触媒機能材料研究室は、スタッフ4名、大学院生3名(M2 2名、M1 1名)と学部4年生9名の計16名で頑張っています。スタッフの近況としましては、高橋先生は引き続き理事・副学長を努められており、忙しい日々を過ごされています。松田先生は変わらず精力的に研究活動を続けておられます。大野先生もますます研究に打ち込む日々を過ごされています。坂上も装置の維持管理そして研究にと忙しい日々を過ごしております。また、今年はガスハイドレート関連の調査で数年ぶりにロシア・バイカル湖に行き、調査船に乗船しサンプリングをしてきました。さらに国内での調査もまだ2航海残っています。学生の近況ですが、本年度も学部生を中心に就職状況が非常に厳しいため悪戦苦闘が続いておりますが、皆それぞれの卒業研究テーマに沿って日夜?実験に取り組む一方で、進学あるいは就職活動にも励んでいます。
卒業生の皆さんも忙しいとは思いますが、機会がありましたら是非研究室にお立ち寄りください。お待ちしております。また、皆さんの住所や勤務地等変更がありましたら、メールで結構ですので、ご連絡頂けると幸いです。
E-mail: sakahr@mail.kitami-it.ac.jp
(坂上 記)
◯機能界面材料研究室
平成25年度のメンバーはBS4名、MS1名、総勢5名です。赤平1、美幌1、北見1、佐世保(長崎)1、出水(鹿児島)1です。今年も山田さんに技術部から来てもらっています。
有機ケイ素修飾によるジルコニア触媒の高機能化を主題にした研究はいよいよ大詰めの段階になりました。このうち、エチレン選択的三量化の研究を今年重点的に行なっています。活性点構造の研究は、西原口孝周君(M2)が8月の第16回国際均一不均一触媒会議@札幌で発表しました。
ロングセラーとなった教科書の「新しい触媒化学」が6月に新刊として刊行されました。これまで25年間41,000部が発刊され、大学の教科書として約70%、高専の教科書として15%、その他として15%使用されました。有り難い限りです。秋には看護学生向けの教科書として「コ・メディカルのためのケミストリー」が共著で刊行されます。
就職希望者はほぼ内定しました。技術セミナー、北の国触媒塾、文献ゼミ(今年で3回目の屈斜路研修所)は例年通りです。昨年に続きおもしろ科学実験(サッカーボール(フラーレン)を折り紙で作ろう)を担当しました。これでおもしろ科学実験の担当は4回目になります。
卒業生の石田君、井上君が尋ねてくれました。近況などをどしどしお知らせ下さい。皆様の益々のご活躍をお祈りしています。
E-mail: imizuyo@mail.kitami-it.ac.jp
(射水 記)
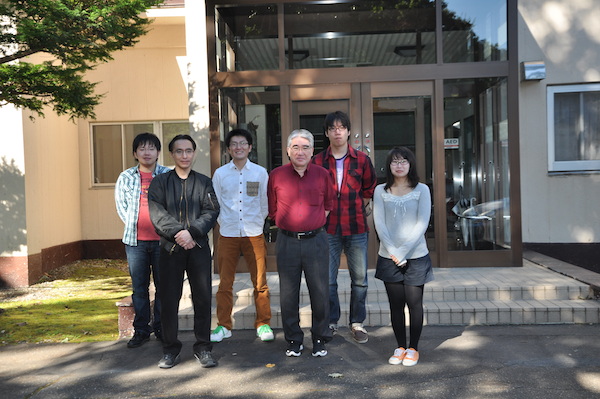
◯材料分析研究室(宇都研究室)
今年3月卒業の西田翔介君がシーテック、市橋拓真君は浦幌乳業(浦幌町)、阿部君はミズノ硝子(北見)、足立詩乃さんはサンデン(群馬)、斎藤匡騎君はジャパンテクニカルソフトウェア(札幌)、玉田拓也君はセブンイレブン・ジャパンへ就職し、新しいスタートを切りました。
25年度はM2の梶原さん、菊池君、松田君、M1の河島君、4年の小川さん、竹中君、姚さんの7人が頑張っています。相変わらず厳しい就職戦線ですが、ほぼ全員が志望する就職先に決まりました。
今年のお正月には札幌で富田さん、前田君、伊藤君、都筑君、長尾君、それに現役の菊池君も参加して小さな同窓会が開かれました。あいにく私は参加できませんでしたが、研究室を繋がりにして社会人となっても交流を持ってくれていることがすごくうれしいです。また、大西君がこの4月から旭川市役所勤務となりました。
毎朝のミーティング、週に一度のまとめ報告も欠かさず続けています。やはり健康で踏ん張りのきく体力と規則正しい生活習慣が“ここぞ”というときに役立つと信じて。卒業生の皆さんも体には気をつけて頑張ってください。近況報告をお待ちしています。
◯分析化学研究室(南研究室)
平成25年度の研究室メンバーの近況を、お知らせ致します。
川岸君、空本君、千葉君、藤原君、宮谷君は、これまでと異なる手法を積極的に取り入れて研究を展開し、博士前期課程を修了しました。久保君、小竹君、李さんは、忙しい中でも笑いを忘れず元気に研究室を引っ張っています。昨年の4年生では、佐々木君、笹村君、平野君が大学院に進学し、6月のサハリン沖調査に三人揃って参加しました。これまでの先輩方と同様、初めての海外調査と思えないほどの活躍でした。佐坂君と田口さんは、就職のために地元に戻りました。今年は、泉君、加地君、菊地君、鈴木君の4名が配属になりました。就職活動、大学院試験そして卒論実験、いずれも積極的に進めています。
すっかりとフィールド調査が多い研究室になりました。5月の摩周湖調査に笹村君、6?7月のサハリン沖調査に佐々木君、笹村君、平野君、8月のバイカル湖調査に佐々木君と平野君、9月の摩周湖調査に笹村君、9月の網走沖メタンハイドレート調査に久保君、小竹君、佐々木君、平野君が参加しました。11月の網走沖調査には、4年生を含めて多くの人が参加予定です。各自治体との共同研究では、今年も波岡さんのご活躍に助けられています。南は各フィールド調査で2ヶ月間ほど不在でしたが、研究室の各人は時間を上手に使って効率よく研究を推進しています。
この一年、何名もの卒業生が顔を出してくれました。後輩に差し入れを送ってくれた方々もいました。お礼申し上げます。修了生・卒業生がそれぞれの職場で活躍している話は、とても頼もしくそして嬉しいものです。皆さまのますますのご発展とご健勝を、心よりお祈り申し上げます。
(マテリアル工学科 南)

共通講座
2012年4月に共通講座に赴任しました笹川渉です。イギリス文学、特にイギリスの詩を専門にしています。イギリス詩を教えることで工学部の学生に何を伝えることができるだろうとあれこれ考えていたものの、それは余計な心配でした。古の作家の作品は、あらゆる分野―人生、歴史、宗教、芸術、科学等―について雄弁に語ってくれます。2012年度と13年度に担当した文学の講義とゼミでは、履修者に毎回コメントを提出してもらっていますが、才能あふれる作家たちの作品を、自らの体験を通じて理解しようとしている姿を見ることができました。
工学者や技師を意味する英語の「エンジニア」(engineer)はラテン語に由来し、「創造者」という意味で使われていました。動力源である「エンジン」も、元来人が持っている「才能」を表す言葉です。「才能に富んだ」という意味のingeniousも同じ語源に由来します。工学に携わる人は、まさに何かを生み出す創造力を持った人なのです。アメリカのSF作家、ロバート・R・ハインラインは、「ある人の『魔法』は他の人の『工学』である」と述べました。超自然性を否定した言葉ですが、工学に携わった人たちの才能により、夢物語でしか見られなかったような現代の発明がうまれてきたことは間違いありません。
今、私は学会で訪問中のイギリスのオックスフォードでこの文章を記しています。オックスフォードは、魔法にあふれる作品を描いた作家を生み出した場所です。『不思議の国のアリス』の作者(であり数学者)ルイス・キャロルや、『指輪物語』で有名なJ・J・R・トールキン、『ナルニア国物語』のC・S・ルイスが教鞭をとり、あるいは学んだカレッジが隣り合っています。ハリー・ポッターもここのボドリアン図書館やクライスト・チャーチが舞台になっています。これからの授業でも、作家の創造力の豊かさを通じて、学生の才能をいっそう刺激できるようにしていきたいと思います。
(笹川 渉 記)

マネジメント工学コース
◯各学科共通マネジメント工学コース
マネジメント工学コースの4年生が配属されている研究室のうち、ここでは共通講座、社会連携推進センターの研究室便りをお届けします。各学科の研究室については、それぞれの学科の研究室便りで近況をお伝えしていますのでそちらをご覧ください。
本コースは今年卒業した11人を含め、これまでに11の研究室から25人の卒業生を社会に送り出しています。機械工学科冨士・渡辺両教員の2研究室、社会環境工学科大島・川村(彰)・高橋(清)・渡邊・白川5教員の5研究室、情報システム工学科桝井・前田両教員の2研究室、共通講座の山田研究室、そして社会連携推進センターの産学官連携価値創造研究室です。
今年のコース4年生は12人です。配属先は、機械工学科の渡辺研究室・ウラ研究室、社会環境工学科の渡邊研究室・中山研究室、情報システム工学科の前田研究室・桝井研究室、そして社会連携推進センターの産学官連携価値創造研究室です。そこで今回も、これまでにコース卒業生を輩出している共通講座の山田研究室と社会連携推進センターの産学官連携価値創造研究室からの便りをお送りします。
(鞘師 守 記)
◯社会連携推進センター 産学官連携価値創造研究室(CVR)
社会連携推進センターのCVRは、マネジメント工学コース学生の第一期生が4年次を迎え配属された平成23年に発足しました。今年で3年目を迎えたことになります。一期生6人は、研究室に関連するあらゆる立ち上げを実現してくれました。昨年配属になった2期生5人は、一期生の成果を踏まえてプロジェクトに取り組み、今年、研究室を巣立っていきました。オープンキャンパスでのコース説明や学園祭での3年生を巻き込んだコースプロモーション、近隣市町村で開かれる様々なイベントへの貢献など、一期生が始めた学内外での諸活動もしっかりと引き継ぎ発展させました。2期生の就職先・赴任地は北見・札幌・小樽・東京で、当研究室卒業生が活躍する地域は更に全国に分布することとなりました。
今年、研究室には、機械工学科・社会環境工学科・情報システム工学科の3学科から4人の学生が配属となりました。マネジメント工学プロジェクトでは、技術を軸とした市施設の活性化、大学・学生の社会貢献、共同研究や知的財産活動から見た大学の強み評価などのテーマが取り上げられています。学内外での諸活動への参画・貢献は更に広がりを見せ、担当学生・教員とも東奔西走しています。指導にあたっているのは、学生の劣らず個性的な社会連携推進センターの有田・内島・鞘師の3人です。有意義な研究活動と研究室のより一層の充実に向け、今年も学生・教員一丸となって全力疾走です。
(鞘師 守 記)

◯共通講座 山田研究室
卒業生のみなさん、元気でおすごしでしょうか。こちらは相変わらずで、みなさんにもよく話していたように「哲学のよさはなんでもありなこと」をモットーに、関心の赴くままにいろんな話題に取り組んでいます。私にとっては専門外の分野をみなさんといっしょに勉強したこともよいきっかけで、頭のなかの抽象思考だけで完結しがちな哲学に、現実の人や物を「生々しく」組み込んでいくことの大切さをますます強く感じるようになりました。みなさん以降、当研究室に所属する学生はまだいませんが、4年生の授業は楽しくやっています。従来通りの発表授業ですが、なるべく制約をかけないようにするとみなそれぞれに個性的な話題、スタイルで発表してくれ、こちらも学ぶところが多々あったりします。ともに考えともに学ぶ。陳腐ながらやはりすばらしいことですね。機会があれば研究室にも遊びにきてください。
(山田 健二 記)
機器分析センター
(研究室の様子)
卒業生の皆様、お元気にしていますか? 研究室は相変わらずで、今年も、研究室の学生たちは、日々、楽しく(?)研究室で暮らして(?)おります。最近は、細胞だの大腸菌だの生き物を扱う実験が多くなってきたので、特に研究室滞在時間が増加してきているような気がしますね。でもその分、福利厚生が充実してきており、研究室内でカップラーメンの備蓄販売が行なわれていたり、ネスカフェバリスタが使えるようになったりしました。また恒例行事になりつつある「ままちゃりレース」には今年も参戦し、終了後は、帯広スイーツ巡りの旅を敢行しました。また、「おもしろ科学実験」も、ニューデザインのお揃いTシャツを来て、例年通り参加しました。「研究は一生懸命に!」でも、「遊ぶときは遊ぶ!」この雰囲気を大切にして、今後も、毎日楽しく、研究に励めればよいなぁと思っています。
(大津 記)